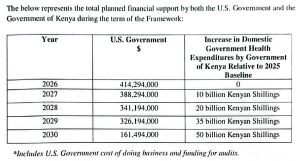The Future of “Two Sudans”Reflections from a Historical Perspective
【栗田禎子さんに聞く 2】
『アフリカNOW』97号(2013年2月28日発行)掲載
聞き手:『アフリカNOW』編集部
栗田禎子
くりた よしこ:千葉大学文学部教授。専門はスーダンおよびエジプトの近現代史。1985〜87年、1994〜95年、2005年にスーダンに長期滞在、現地調査を行う。著書に『近代スーダンにおける体制変動と民族形成』(大月書店)、『戦後世界史』(大月書店・共著)、『アリー・アブド・アッ・ラティーフと1924年革命』(アラビア語)など。訳書にW.S. ブラント『ハルツームのゴードン』(リブロポート)がある。2003年に参議院外交・防衛委員会で、イラクへの自衛隊派遣に反対する立場から意見陳述を行った。
― 栗田さんが解説の最後で話されていた「スーダンの春」は、日本ではほとんど報道されていませんね。
栗田 2012年6月から7月にかけては首都のハルツーム(Khartoum) だけではなく、スーダン共和国〔以下、スーダン(北)〕全土の町でデモが起き、約3,000人の逮捕者が出たと伝えられています。バシール( ‘Umar Hasan Ahmad al-Bashīr) 政権の打倒をめざす勢力は、基本的には二つあります。一方は、スーダン(北)の民主勢力が作っている国民的合意勢力(NCF; National Consensus Forces) で、これは1990年代の国民民主同盟(NDA; National Democratic Alliance) の後継者的組織といえます。全戦闘の停止、政権の打倒を主張しており、ダルフール(Darfur) 地方を含むスーダン国家全体の今後の体制のあり方を話し合う、憲法会議を開くことをうたっています。そしてこの目標を「アラブの春」と同様に、平和的・市民的抵抗によって実現していくと主張しています。
他方、南コルドファーン(South Kordofan) 州および青ナイル(Blue Nile) 州では、スーダン人民解放運動–北部(SPLM_N; Sudan People’s Liberation Movement_North) が、バシール政権に対する武装抵抗を継続しています。このSPLM_N と、ダルフールの抵抗運動とが連携し、協力してスーダン(北)内部の低開発地域の権利を要求していこうとする動きもあります。
以上の二つの流れはまったく無関係なわけではなく、対話や協力の試みも存在します。たとえばスーダン共産党(SCP; Sudan Communist Party) は平和路線ですが、SPLM_N などの勢力が自分たちの戦い方として武装闘争を選ぶことは非難しないし、干渉もしません。共産党はデモやストといった形で運動していますが、その一方で、低開発地域の人々の権利を守ろうとするSPML_N が武装闘争を行なうことは合法的だという立場をとっています。また、北部の伝統的保守政党の代表格といえるウンマ党(Umma Party) が、バシール政権打倒のため、ダルフールの武装勢力やSPLM_Nと内々で協定を結ぼうとしている、といった動きが伝えられることもあります。
ただ、政権打倒のために武装闘争路線に傾きすぎると、激しい弾圧を招くだけでなく、現在のシリアのように国際社会が関与する形の内戦にもつながりかねず、結局はスーダン(北)のさらなる分裂・解体という結果をもたらしてしまうのではないでしょうか。また、政権側も生き残りのため、SPML_N に対し厳しい軍事弾圧を加えながら、ある時点で電撃的に「和解」して政権に取り込むという手法、ちょうどかつてSPLM 本体に対して「南北和平合意」という形で行なったと同じことを、今度はSPML_N に対して仕掛けてくることも考えられます。国際社会の操る「内戦」や、スーダンのこれ以上の分裂・解体という事態に陥らないためにも、基本的にはあくまでも市民的、非暴力の抵抗によって政権を追い詰めていくべきだと、私は考えています。
― スーダンの現代史を振り返ってみると、歴代の軍事政権が弾圧を繰り返してきたにもかかわらず、それでも民主化勢力をつぶすことができなかったことがわかりますね。
栗田 独立後のスーダンには文民政権期と軍事政権期が交互に現われてきましたが、それは「軍事政権が打倒されてきた歴史もある」ということにほかなりません。スーダンでは1958年と1969年、そして1989年に軍事クーデターが起きていますが、現在のバシール政権の前の2回の軍事政権はどちらも民衆蜂起で打倒されています。1958年のクーデターで成立したアッブード(Ibrahim ‘Abbud) 軍事政権は、1964年10月に民衆がゼネストとデモという手段で行なった無血革命(10 月革命)によって倒され、1969年のクーデターで成立したヌメイリ(Gaafar Muhammad an-Numeiry)軍事政権も1985年4月にやはり民衆の決起(インティファーダ)によって打倒されました。「アラブの春」は世界的に注目されましたが、アラブ世界において独裁政権を非暴力の大衆行動で打倒するという経験は、2011年にチュニジアとエジプトで最初に起きたのではなく、スーダンではすでに2回、起きていることに留意すべきだと思います。
― 南スーダンにおいて、政権を担っているSPLM に対する批判の動きは存在しますか。
栗田 SPLM 政権に対する原則的な批判を行なっている政治勢力としては、南スーダン共産党(SSCP; South Sudan Communist Party) が、少数派ではありますが、注目に値するかもしれません。これは従来、SPC の党員だった南部の人が、南スーダンが分離・独立したことを受けて、新しくSSCP を設立したものです。SSCPの声明(2011年11月)を読むと、南スーダンの独立は住民投票で圧倒的多数の人たちが選んだことであり、尊重するが、SPLM 政権による誤った政策は是正していく、という基本的な立場が表明されています。
「誤った政策」の例としては、反体制派に対する態度の問題があります。南スーダンでは現在、SPLM に反対する新たな武装勢力が登場し、武力紛争が始まっています。南スーダンを不安定化させるため、背後で北のバシール政権が糸を引いている勢力も混じっていますが、SPLM 政府はこれらの反体制勢力に対し、基本的に武力弾圧一本やりで対応している。独立と同時に戦争が始まっている状態です。これに対してSSCPは、反体制派を武力で制圧するという手法をとると、これまでのスーダン北部のエリートと同じ道を歩むことになりかねない、南スーダンが独立直後から軍事的で非民主的な国になっていくことを憂慮する、と警告しています。
また現在、スーダン(北)では国際通貨基金(IMF)の方針に従属した緊縮財政策による公務員の削減や補助金の削減が行われていますが、南スーダンでも、国家予算はSPLM 政権がIMF に相談して、議会で予算案が審議される前に実質的に決めてしまっています。SSCP は、IMF の圧力のもとでSPLM 政権が「新自由主義」的な経済政策を推進していることを批判し、新しい国づくりにあたっては、国家が責任を持って教育や医療などの公共サービスを構築していかなくてはならないと主張しています。
SSCP は現在、南スーダン議会では議席を持っていませんが、書記長のジョゼフ・モデスト(Joseph Wol Modesto Ukelo) は、1989年にクーデターでバシール政権が成立する以前は、SCP の議員としてスーダン共和国の国会議員を務めていました。
― 石油資源の分割やスーダン(北)を通過するパイプラインの使用をめぐって南北スーダン間で紛争が起きましたが、現状はどうなっていますか。
栗田 現在、南スーダンは、一時ストップしていたスーダン(北)とのパイプラインの使用をめぐる交渉を再開しようとしています。現状では、南スーダンで産出された石油も、スーダン(北)のパイプラインを通って、ポートスーダン(Port Sudan) から積み出すルートしかありません。
同時に南スーダンとしては、常に紛争の要因になりかねないこのパイプラインだけに依存しているわけにはいかないので、周辺国と交渉して、スーダン(北)を通過しない新たなパイプラインを建設することも検討しているとされます。南スーダンからケニアに向かう、あるいはエチオピア経由でジブチに向かうパイプラインの建設が計画されているようです。ちょうどここ数日、スーダン国内の新聞で、日本の民間企業の投資を促すために南スーダンの財務経済企画相が来日中というニュースが報じられていますが、そこでは、ケニア・ルートに関しては、日本企業もパイプライン建設に参加するプランがあると紹介されていました。こうした動きに対して私たち日本の市民の側は、石油資ア源をめぐる日本の南スーダンへの関与が、ひとつ間違えば「新植民地主義」的性格も持ちかねないことを忘れず、注意深く見守っていくべきでしょう。
― 米国は1990年代にスーダンをテロ支援国家に指定し、バシール政権に対する攻撃や制裁を強化していました。ところが21 世紀になってからは、むしろ「和解」を進めているように見えます。2001年の9.11以降にイスラーム世界に対する攻撃を強めていく中で、バシール政権に対するこうした真逆ともいえる対応はなぜ生じたのでしょうか。
栗田 米国によって「テロ支援国家」と指定された結果、スーダンには1990年代には欧米諸国に代わって中国やマレーシアが進出し、石油開発にも参画して、経済的関係を強めました。このような状況に、米国は実は焦りを感じていました。21世紀に入って米国が「南北和平プロセス」に積極的に関与し始め、バシール政権とSPLM との和平を仲介するという動きに出たのは、それを介してスーダンに再び地歩を占めるためでした。
他方でバシール政権の側も、ちょうどこの時期、国際社会に復帰するための道を探っていました。1990年代には「テロ支援国家」に指定されており、実際にウサーマ・ビン・ラーディン(Usāma bin Muhammad bin ‘Awad bin Lādin) をかくまってさえいたスーダンは、理屈の上ではアフガニスタンのタリバーン政権と同様に9.11 後、米国によっていっきょにつぶされかねない状況だったと言えます。ところがバシール政権は9.11 後、ビン・ラーディンやアル・カーイダに関するすべての資料を米国に提供し、米国連邦捜査局(FBI) の事務所をハルツームに開くことを許し、事件の調査に全面協力することで、逆に米国との関係を一挙に改善することに成功したのです。ビン・ラーディンをかくまっていたことや「テロ支援国家」だったことを逆にカードにしたわけで、非常に巧妙に立ち回ったとも言えます。
2003年以降、ダルフール危機が深刻化し、「史上最悪の人道的危機」として注目を集めたときに至っても、バシール政権は「南北和平プロセス」の一方の当事者であることを利用して生き残りに成功しました。「和平プロセス」が進行中だったために、米国もバシール政権を追い詰めることはしなかった。ただし、南スーダンが独立してしまった現在では、米国にとってバシール政権は「用済み」になったとも言えます。ですから今後、ある時点で、米国が再度、バシール政権が「テロ支援政権」で「イスラーム原理主義」であると言い立てて、軍事介入するといった事態も生じうるかもしれませんね。
― 南スーダンはこれまで、スーダンの中でも周辺化され低開発地域にされ、いわば「何もない」ところから国づくりを開始していかなくてはならないために、NGO も含む国際社会の力に依拠して国家のインフラを整備しているという側面があると思います。こうした現状の中で、南スーダンが国際社会に対して自らの主権を守りながら同時に自ら国づくりを進めていくためには、どのような可能性があると考えられますか。
栗田 先ほど、SSCP によるSPLM 政権批判を紹介しましたが、もともとはSPLM も革命勢力で、スーダン全体の民主化を求め、権力と資源の公平な分配を主張していたのです。確かに独立後の南スーダンでは、SPLM による権力の独占とそれに伴う腐敗がもっとも大きな問題になっていますが、一方で、つい最近までバシール政権と戦っていたSPLM のメンバーの多くは、ポストや金が欲しくてたたかっていたのではなく、本当に住民の福利を考えてたたかっていたと思います。ですから、たとえばこうしたSPLM の草の根のメンバーが、SSCP のような勢力とも対話・協力していくような流れができれば、一握りのエリートや先進国の企業のためではない、住民のための経済・政治のあり方を模索していくことができるのではないでしょうか。近年はアフリカ全域で国際的なアグリビジネスの動きが活発になり、農地の大規模な収奪が進んでいますが、南スーダンでも米国企業などが石油資源だけでなく土地にも大きな関心を寄せていると伝えられており、こうした問題についての対応も必要です。
国家の今後の発展のあり方を考え、市場原理主義一本やりの新自由主義政策ではなく、住民の生活・福利を大事にするシステムを作っていくためには、まず何より、こうした問題について存分に議論できるように、言論や政治活動の自由を保証していくことが必要です。独立後の南スーダンでは弱小政党を政党法によって規制・排除する動きや、ジャーナリストの弾圧などが見られますが、これに対してたたかっていく必要があるでしょう。
― 2005年1月の包括的和平協定(CPA) の合意から2011年1月のスーダン南部の独立の賛否を問う住民投票までの6年間においても、SPLM のもともとの方針どおりに、南部の分離・独立ではなくスーダン全域の統一を維持するという動きは依然として有力だったのでしょうか。それともCPA22 アフリカNOW 97の合意は、SPLM の方針転換を意味していたのでしょうか。
栗田 個人の力量や資質を過大評価すべきではないのですが、「統一されたスーダン」のヴィジョンを体現していたとも言える一人の人物として、改めてジョン・ガラング(John Garang de Mabior) の例に立ち返ってみましょう。CPA 合意後の2005年7月に、当時SPLM の議長であったジョン・ガラングが乗ったヘリコプターが墜落し、彼が死亡したことは、その後の南北スーダンの行方に大きな影響を与えたと考えられています。ジョン・ガラングは1983年に、1950〜60代の南スーダンにおける分離主義の動きを批判して、SPLM の運動を始めました。南部の分離独立ではなくスーダン全体を立て直し、「新しいスーダン」を建設するということに、とても強い思い入れをもっていました。
一般的にはスーダンは、「北部はアラブ人のイスラーム教徒の社会、南部は非アラブで非イスラームの社会だ」という説明のされ方がされますが、興味深いことに、歴史的に北部のイスラーム化を担ったのは、実は非アラブのフール(Fur) を主体とするダルフール・スルタン国や、現在の青ナイル(Blue Nile) 州から興おこったやはり非アラブのフンジュ(Fuji)・スルタン国でした。また南コルドファーン州のヌバ山地(Nuba Mountains)に住むヌバの人々も、一説にはエジプト・スーダン国境のヌビア(Nubia) 地方の文化と共通性があるとも言われ、前近代以来のスーダンの歴史で重要な役割を果たしています。
こうして見るとスーダンは、まさにブラック・アフリカとアラブ・イスラーム圏の融合する場で、アラブ文化やイスラームも実は現地の文化に支えられる形で発展してきたと言えます。ジョン・ガラングは、こしたスーダンの歴史について良く知っていて、異なる文化の融合の場としてのスーダンというまとまりを崩してはいけないと強く信じていたようです。彼が「新しいスーダン」というヴィジョンを掲げ、SPLM を率いてNDA に参加したのも、北部の民主勢力を味方つけるための方便ではなく、本当にスーダン全域のまとまりを維持したいと考えていたと言われています。そして、これはジョン・ガラングが特殊だったのではなく、現在でも南コルドファーン州や青ナイル州でSPLM_N として戦っている人々は、まさにそのような考えを抱いているのではないでしょうか。この人々は、自分たちは「北部人」でも「南部人」でもなくスーダン人だという意識を強く持っており、スーダンの統一の維持を志向しています。
ジョン・ガラングが存命であれば、2011年の住民投票に向う過程でも、南部の分離・独立ではなくスーダンの統一を主張したでしょうし、また、仮に2010年の大統領選に彼が出馬していたならば、北部の住民の圧倒的な支持も集めたと思います。彼が死の直前にハルツームを訪れたときは、それこそハルツーム中の人間が彼を見に行ったのではないかというくらいの大歓迎を受け、北部の民主勢力は彼がスーダンの統一と民主化を守ってくれることを期待しました。ですから、今でも彼が死ななければスーダンの統一を守れただろう、と指摘する声もありますし、その死は事故によるものではなく、スーダンの統一や民主化を望まない勢力による暗殺だったのではないかという説もくすぶっています。
ジョン・ガラングが生きていたら、という議論のしかたは生産的ではありませんが、彼に象徴される、スーダンの統一を求める人々がもう少し力を発揮できていれば、統一が維持されることもありえたでしょう。実際、南スーダンの独立後の現在では、南コルドファーン州(ヌバ山地)や青ナイル州での危機がもっとも大きな問題になっており、これらの地域の抱える問題が南部の分離・独立では解決できなかったことが証明されています。南コルドファーン州や青ナイル州でたたかうSPLM_N は、SPLM_N の合法化を求めるなどスーダン(北)の民主化のために闘うと同時に、将来的には民主化された両スーダンの間で再び国家連合(Confederation) のようなものを構築することも展望しているようです。長期的には確かに、このような展望も考えられるでしょう。
ただし、南スーダンでは長年の苦闘の結果として圧倒的多数の人が分離・独立を選んだという事実があり、次の世代あたりまでスーダンの再統一について語られることはないのではないかと思います。スーダンが再統一するためには、スーダン全域が民主化されることが前提なので、現在の世代は、短期的には南北スーダンそれぞれの国内において民主化のためのたたかいに取り組まねばならないでしょう。スーダン(北)の民主化がなされなくてはならないことは明らかですが、南スーダンも最悪の場合は、米国やイスラエルに操られるアフリカ内部の傀儡国家になってしまう可能性も考えられます。そうならないためには、南スーダンにおける民主的国づくりも求められますね。
2012年9月8日