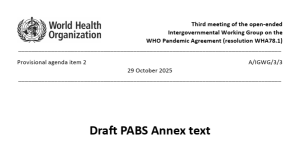『アフリカNOW』 No.17(1996年発行)掲載
執筆:大塚 朋子(会員/財団職員)
“アフリカの角”に位置するエリトリアは1993年4月、30年にわたる内戦をへて、エチオピアから勝ち取った分離独立を国民投票によって承認、アフリカで53番目の独立国になった。人口は350万人(国民投票時の調査で250万人との数値もある)、うち難民としてスーダンへ50万人、海外へ20万人と推定される人々の帰国も進んでいる。一人当たりのGNPがUS$100、GDPはUS$75-150。いずれにしても今世界でもっとも貧しい国のひとつである。長い戦争で荒れきった国土を復興し、社会、経済の再建などなど、すべてがこれからである。
“good day”の到来
首都のアスマラを訪ねたのは1995年の9月末だった。ちょうど雨季が終わって、1年中で一番いいといわれる季節を迎えていた。9月の花といわれる黄菊のようなマスカルやピンクのコスモスが咲き乱れる野原、うっすら緑に覆われた山々。標高2400mの高地には、思ったよりも美しい大地が広がり、ほっとしたのが第一印象だった。
エリトリアへの旅は友人との約束を4年越しに果たすものだった。1991年4月23日、エリトリア人民解放戦線(EPLF)がエチオピア人民革命民主戦線(EPRDF)と共闘してメンギスツ社会主義独裁政権を倒した。30年にわたる内戦に勝利したその日、私はエリトリア人グディ・カリブと一緒にBBC放送のワールドニュースを聞いていた。彼女はエリトリアを半ば亡命するようにして離れ、ロンドンで暮らしていた。
すでにその1週間ほど前から情勢が急転しそうな動きが報じられていた。時はちょうどベルリンの壁崩壊、冷戦の終結、東欧諸国に相次ぐ革命そしてソ連の崩壊へと激しく転換していくさなかだった。
エリトリアを離れて10数年たっていたグディはよく、「私の名前はgood day、いつかはエリトリアへ帰れるいい日が来る。」と言っていたが、彼女にとってまさに”いい日”の第一歩であった。
帰国した友
それから2年、グディからエリトリアのスタンプの付いた封書が日本へ届く。やっと帰国が実現、どうにか仕事と住まいを確保したものの、戦後の混乱はなかなか収拾しないことを思わせる知らせだった。彼女と出会った時以来の約束、”貧しくさせられた国”の現実をちゃんと知っておく、を早く果たさなくては、という思いは強かった。
ちょうど93、94年と続けてエリトリアを訪ねた知人からも、背中を押された感じだった。新しい社会建設の第一歩、なかでも女性たちの果たす役割を見ておいたほうがいいと。
こうして、私たちはエリトリアの一番いい季節にアスマラで再開を遂げたのだった。
ちょっと疲れた様子の私の友人は、連日のワークショップ研修のせいだと言った。米国に本拠をおくNGOの現地スタッフとしての仕事を得た。だが、援助プロジェクトなどもまだまだ試行錯誤の段階で、調査や試験的なものばかり、という。
国連などの援助機関のほかに大小さまざまなNGOが各国から競うように入っているが、本格的なNGO活動はこれからのようだ。
仕事がない、収入がない。
アスマラ近郊の村を訪ねた。両手に抱えるほどの食料を買い込んで、私の知人が世話になった家を訪問したのだった。
一時しのぎとわかりながら、わずかな食料で一家6人が食べつないでいることを聞くと、そうしないではいられなかった。町の外国人向けの商店には量、質ともそろった食糧が並ぶ。しかし地元の人たちには手の出ない値段である。パスタ類をおいしく食べさせるレストラン、こぎれいなホテルもある。イタリア植民地時代の名残だ。
雇用の創出、収入の創出は最優先課題となっている。運転手をしているルカスは、解放軍にいた元兵士で、現在8人の家族を月300ブル(1ブル約17円)で養っているという。そのうち家賃・光熱費に150ブル、糊口をしのぐのがやっとの苦しい生活振りだ。
それども仕事があるだけラッキーなのだ。彼のように解放戦争の担い手だった元兵士たちの処遇が今、なにより大きな社会問題になっている。給料面ではグディも似たようなもので、扶養家族が少ない分、ややマシというようだった。
経済発展は日本を見習え!?
高地にあるアスマラから紅海に面した港町マッサワでは車で約4時間。足がすくむような深い谷底を見下ろしながら急勾配のいろは坂をひたすら下る。まだガードレールの設備はない。しかしわずかこの半年で道幅は大きく拡張され、谷への転落事故は減少した。EUが道路などのインフラ設備を条件に資金援助を進めているからだ。
6~9月の気温が40度以上に上がるマッサワ、ここはエチオピア軍との壮絶な戦いが展開された激戦地だった。まだいたるところに爆撃で崩壊された建物の残骸がなまなましい。
途方もなく美しい紅海で泳いでみるとその塩辛さに驚く。戦前は日本まで輸出していたという良質の塩を産する海岸沿いの塩田、ここも激しい銃撃戦で真っ赤に染まったという。
30年間手つけぬままだった海は、いまでは天然資源の宝庫。この地域では魚をたべる習慣がなく、食糧難でも魚には手がでない。
ロンドンにいたグディをよく訪ねてきた解放戦線のメンバーがいて、しきりに魚の加工を知りたがっていたことがある。フィッシュ・ケーキといっているかまぼこやはんぺんなどの作り方にとっても関心をもっていたのだ。飢餓を克服するさまざまな試みをしていたようだった。
昨年の10月、エリトリアで水産指導にあたる日本人の国連職員がが、その功績に対して国連食糧農業機関(FAQ)から受賞した。日本の水産技術が持続可能な開発技術として紅海に生かされることを期待したい。
また、昨年7月、港には地球一周の船旅の「ピースボート」が寄港した。青年や女性たちとの交流が繰り広げられ、その後も町の語り種になっていた。一行は首都アスマラも訪れ、ちょっとした日本旋風を巻き起こし、エチオピア占領時代から日本にもっていた親近感を増すのに一役かったようだった。
そういえば、アスマラの町中では、”ECOLAC JAPAN”や”JAPAN”の文字をあしらったスポーツバッグを見かけた。敗戦直後のゼロから出発して、今日までの経済発展を範としたい、という途上国の”思い込み”がここまでも強かったのが心配だった。
女たちが変えるエリトリア
今回の旅のもうひとつの目的は、エリトリア全国女性同盟(NUEW)を通じて、女性たちの暮らしを知ることだった。まず、解放後のエリトリアは、反エチオピア戦争を主導した解放戦線のイサイアス書記長が、先の選挙で大統領に選出された。憲法の制定による本格的な選挙実施までの暫定政権である。
民族構成は、主流を占めるチグリニア族はじめ9つの部族から成る多民族国家。宗教的にはキリスト教コプト派とイスラム教がほぼ50%ずつで均衡を保っているのが現状である。周辺諸国とも友好を保っているが、つい先ごろ、エリトリア軍がイエメンの島を武力で占拠したばかり、とキナ臭い事件が起きて予断を許さない事態もある。だが、政情の安定と持続可能な経済の発展は車の両輪である。新しい国作りには女性たちの参加なくしては遂げられない。解放戦争の真の主役ともいわれ、解放軍の3分の1を占めて果敢に戦った元女性兵士たちのコンゴの”身の振り方”が鍵になる、といって間違いない。戦争が終わって除隊した彼女たちは、”女は家庭に”など、この国に根強い家父長制の巻き返しが起こることをなによりも警戒しているのだ。
1995年8~9月に北京で開かれた国連世界女性会議のNGOフォーラムで、私はアフリカン・テントの脇で小さなコーナーを出しているエリトリアの女性たちと出会った。この会議には政府代表を含めて23人も参加していることに驚いた。いずれもヨーロッパのNGOからの援助があったという。
女性同盟のアスカル・メンケリオス代表は世界の晴れ舞台で、各国の女性たちからたくさん刺激を受けたと話してくれた。
活躍するエリトリア全国女性同盟
会員20万人を組織する女性同盟は、1979年に設立され、1991年の解放までエリトリア人民解放戦線の傘下にあった。現在はエリトリアの女性の地位向上、自立のために活動するNGOであり、16歳以上の女性なら民族、宗教の違いなく誰でも入会できる、唯一の全国組織である。いま、女性たちの意識を高め、約9割にものぼる女性の非識字率に挑んでいる。30年に及ぶ教育の空白期間は、これから将来に向けて大きな痛手である。メンケリオス代表に日本に期待することを尋ねた。経済援助はもちろんのこと、やはり人材養成が急務で、学ぶチャンスを多く、たとえばスカラシップなどが必要であると強調していた。
また、優先順位の高い課題として、やはり元女性兵士とそれに戦争で夫を亡くした女性世帯主の経済的自立がある。戦後処理のひとつである。その第一歩として、女性同盟では、小規模企業を促進するための『小規模融資と訓練プロジェクト(micro credit project)』に取り組んでいる。詳細は資料も含めて
日本との接点を求めて
日本にはわずか数人しかいない、というエリトリア人のひとり、ネジャット・シャニノさんと話す機会があった。5歳の時、内戦を逃れて家族とオーストラリアへ移住した彼女は、昨年ピースボートに乗船、久々に故郷へ戻った。船の仲間ほとんどが、一番気に入った寄港地としてエリトリアをあげたという。この国をもっと知ってもらい、もっと訪ねてほしい、と彼女は日本との交流組織を作ってエリトリアを紹介したいという。
アスマラで見たあのスポーツバック、車の中でBGMとして聞かされたボブ・マーリーと日本の演歌。山岳地帯を走る日本車。いまは高嶺の日本製家電製品。これから日本への関心はいっそうひろがりそうだ。
市民サイドの情報交流の場として日本に”エリトリア・センター”、エリトリアに”ジャパン・センター”のようなものが作れたらいいね、という話になった。
94年12月、飛行機事故で亡くなったジャーナリストの沼沢均は解放直後をリポートして、エリトリア人の不屈な戦いと、合理的で勤勉な国民性をかって、「間違いなくいい国になる」とこの国の再建に強い願いを込めた。私もそう思う。そうあったほしい。ずっと、いい日、エリトリアであるように。見守っていきたい。