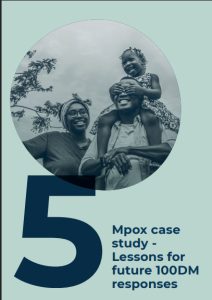『アフリカNOW』 No.29(1997年発行)掲載
執筆:金沢恵子
“キャンプ・サダコ”とは、緒方貞子国連高等弁務官の名にちなんだもので、難民援助の現場を体験し、難民への理解を深めるために国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が行う研修プログラムである。参加者は約3週間難民キャンプに滞在し、現地のNGOの指導のもとで活動する。費用の大部分は自己負担となる(ナイロビまでの旅費、ビザ、予防接種などで約30万)。1993年から95年までに、日本から27名が参加している。
このプログラムは、もともと日本人のみの参加から始まったため、初回の93年の8月と第3回目の94年9月は日本人だけ(計16名)だった。その後、他の国へ広がりを見せ、今では世界各国から参加者が集まっている。
「ケニアへ行きたい」という半ば不純な動機で応募した私の目に飛び込んできたのは、96年4月6日付、朝日新聞の社説記事「求む、語尾をはっきりいう人」だった。1次選考で、6人の日本人枠に約30人の応募があったこと、どういう基準で適任者を選ぶのか、また”キャンプ・サダコ”実現のいきさつなどについて書かれてあった。名称について緒方さんは困惑したらしい。「せめてキャンプ・オガタとしたのに」と。
まだそんなに知られていない新しいプログラムにもかかわらず、こんなに反響が大きいとは思わなかった。しかも朝日の社説にまで載ってしまったとは……。うーん、こりゃダメか……とあきらめかけていたら、一次選考の書類が通り、二次選考の英語と日本語の面接も奇跡的に受かり、私は第9回目の”キャンプ・サダコ”に参加が決定、ケニアの難民キャンプで活動することになった。
参加が決まってから出発までの間、当時やっていた仕事(教職)の退職準備、航空券の手配、ビザや予防接種、友人・知人へのあいさつなど、青年海外協力派遣隊でザンビアへ行った時のようにバタバタとあわただしく時間が過ぎていった。それでも、8月の夏休みがあったのでだいぶ助かった。職場には年度途中ということもあり、やはり最後まで迷惑をかけた格好になってしまった。
1996年8月31日、私は再びアフリカの大地を踏んだ。なつかしい香りが私を優しく包んでくれる。また来ちゃったんだな……
感慨深げにジョモ・ケニヤッタ国際空港から久しぶりのナイロビの街並みを眺めながらしみじみと思った。しかし、今回が、前回のザンビア行きの時と決定的に違うのは、日本に帰ってからは戻る場所がどこにもないということである。日本はまだ不況、この厳しいご時世の中、帰国後の予定はこの時点では全く立ってなかった。まぁ日本だから飢え死にはしないだろうし、なんとかなるだろう……と自分を奮い立たせてのケニア行きだ。不安はあるが、それを言ったらきりがないし、思い切ってやらねばならない時もある。
ナイロビに着くとすぐ、UNHCRケニアオフィスで研修の事前説明を受けた。ここで、他の参加者とも合流。
英語圏からの参加者はもちろん、そうじゃない国からの参加者もほとんどネイティブ並の英語を話す。自分も含めて、一番しゃべれないのは我々日本人(そのうち一人は英検準1級の資格保持者だったから彼はたいして苦労がなかったようだ)。正直なところ、最初のUNHCRの説明から、しっかりつまずいてしまい、ネイティブの英語についていくのがすっごく大変で、実は研修プログラム期間の半分くらいまで皆の言っていることがほとんどわからなかった。この時ほど自分の英語力をうらめしく思ったことはない。
今後、国際協力関係での分野での仕事を希望する私にとって、このショックはいい意味で帰国してからの英語に改めて取り組み直すとてもよい起爆剤になった。
96年9月の”キャンプ・サダコ”は、ケニアのダザーキャンプとカクマキャンプの2グループに分けられた。今回の日本からの参加者、女性3人、男性1人のうち女性1人だけがカクマキャンプ、他は私もいれてダザーキャンプに割り当てられた。
他の参加者の顔ぶれは実に多彩で、外交官養成学校に通っている人、元看護婦、保険会社の社員、ジャーナリスト、国際弁護士目指して勉強中、スカラーシップでドイツで経済協力の仕事をしていた人などなど。出身国はアメリカ、イギリス、オーストラリア、スウェーデン、ヨルダン、トルコ、ベルギー、そして地元ケニア、そして日本。文字通り世界中から主に20代半ばから後半の若者が集まった。必然的に私が一番年上になった。
日本からは大学生2人、大学を卒業したての社会人1年生と私。ダザーブとカクマへの割り当てはUNHCRの方ですでに決めており、ダダーブ11人(うちの1人欠席)、カクマ6人の構成だった。
初日のUNHCRの説明が終わると翌日の早朝、セスナ機でダダーブヘ移動した。この時期は乾期ということもあり、空の上からケニアは乾燥した赤茶けた大地が広がり、ところどころ小高い丘のようなものがみえた。
ナイロビを出発して約3週間後、ほぼ赤道直下のダダーブヘ到着。セスナから降りるとすでにUNHCRダダーブオフィスへ向かった。
オフィスはダダーブのほぼ中心地にあり、UNHCRはじめ他のNGOのオフィスも一定の区画に固まっていた。門のところには警備員がいて、チェックが厳しい。オフィスにたどり着くまでに何重もの扉があり、セキュリティには相当神経を遣っているようだ。
荷物をおいてひと休みする間もなく次から次へとまたUNHCRやそこで活動しているいろいろなNGOからの説明がビシバシ飛んでくる。英語がわからない私はもう必死だ。手渡された資料を頼りになんとか少しでも理解するように務めた。
その後、2日くらいかけて実際キャンプに出かけて病院や学校など、キャンプの様子を見学し、10月1日までの自分の興味・関心にそって各自の活動を開始した。
ダダーブ難民キャンプでは、UNHCRが全体の統括、調査、まとめなどをとりしきり、その下で分野別に各援助団体・NGOが活動しているような形だ。あわせて10くらいの団体がある。
私は、今までの経験を生かして教育関係か、あるいは栄養士の免許を持っているので栄養・公衆衛生関係の分野で活動しようとケニアに来る前から考えていて、それなりの準備もしてきた。その中で、現地の実情などをいろいろな条件を考慮した結果、教育関係の分野に絞ることにした。
具体的にはダダーブキャンプを形成している3ヵ所のキャンプ(イフォ、ハガデラ 、ダカハリ)に1ヶ所ずつセカンダリー・スクールがあるのだが、そのうちのひとつダカハリキャンプ内のダカハリ・セカンダリー・スクールの先生たちに(全て難民である)に、効果的な授業のやり方や進め方、やはりモノが十分いない中での実験の工夫などについて、できる限りアドヴァイスをしたりした。また、時間をみつけては教育に関係する資料を集めたり、セカンダリーの先生や生徒達(もちろん、みんな難民)とおしゃべりしたり、キャンプの中を歩いて難民たちの生活をみて回ったりした。
教育関係のプログラムを一手にひきうけているのは、ケアというNGOである。他に、食糧貯蔵や配給、水、衛生、難民たちの自立支援のための地域サービス(日本でいうと公民館のようなもの)もやっており、その活動範囲は多岐にわたっている。このケアは、ケア・インターナショナルというかなり大きい組織で、世界中に事務所をもっており、日本でも活動している。
キャンプで活動していたスタッフはケニア人が多かったが、中には難民のスタッフもいて(ちゃんと採用試験があるという)、そのNGOから給料をもらっている人もいた。しかし、そのように現金収入を得ている人は難民全体のごくひと握りである。
私は1ヵ月間、ケアの教育プログラムのスタッフにお世話になった。今だからいえるが、私は初めセカンダリーで直接生徒に教えることを希望していたのだが、ケアのスタッフから暗に私の英語力のなさを指摘され、妥協策として先生たちにアドヴァイスをする、という案が浮上した。もし、私にもう少し英語力があったなら――と今でも悔やまれる。トルコから来ていたジャーナリストの男性はセカンダリーの生徒に対して、1時間英語でジャーナリズムの話をしっかりしている。
ダカハリ・セカンダリー・スクールは、生徒数61人、教師数、14人(96・8・31現在)で、生徒の大半は男子。私がみた限りでは、女子生徒はたったひとりだった。教師は全て男性。なぜ女子がひとりしかいないのかと聞くと、「女の子は家事やら小さい妹、弟の世話などで忙しくて学校に来られないから」という。キャンプ内の生活が大変で苦しいのは皆同じはずなのに、やはり女の子の教育はあと回しにされてしまうのか。また、他の途上国と同じように女子の早婚、早期出産、あるいは強制結婚(家の長は男性-父親、祖父など-で、この命令には逆らえない)の問題があるようだ。これは、その国の宗教、それに密接にかかわっている文化・習慣などが多分に関係していると思われる。
ダダーブ難民キャンプ全体としてはソマリア難民が圧倒的に多いが、スーダン人やエチオピア人もおり、ここのキャンプごとにそれらの民族の役割が違う。ダカハリキャンプは9割以上がソマリア人、セカンダリーの生徒もソマリア人。先のセリフもソマリアの宗教、イスラム教という背景とは無縁ではないだろう。
セカンダリーの先生たちはソマリア人、エチオピア人、スーダン人とさまざまで、校長はソマリア人だった。以前、祖国で教職の経験がある人はほとんどいないので、毎週土曜日、ケアの主催で教師研修(ワークショップ)を開いている。
研修の最終回では、私も主に理科係の先生たちを対象に、”楽しい学校を作り出すために”というテーマで実験をまじえながら話をする機会を得た。反応はよく、そこそこ好評だったので研修をしめくくるにはまあよかったとホッと胸をなでおろしている。
ちなみに、教師たちは毎月ケアから給料をもらっているが、中には妻を3人もっていて(イスラム教では妻を4人までもっていいそうだ)、給料だけでは生活していけないのでキャンプ内で商売もしているというソマリア人教師もいた。
私がザンビアのセカンダリーで教えていた時と同じように、やはり子どもたちには十分なテキスト、教材がない。ノート、ボールペン等はまさに貴重品だ。紙1枚すらも。校舎は、木で骨格を作り、土でぬりかため屋根はトタンという非常にシンプルなもの。雨風がしのげるだけでいいというべきか。それでも、乾燥してほこりっぽいダダーブの地では強い風が吹くと教室の中まで砂ぼこりが舞い上がり、生徒も教師も大変である。
こんな学習環境としてはとても厳しい状況の中でも、生徒たちはよく教師の話を聞き、必死にノートをとっていた(これが結局彼らのテキストになる)。やはりここでも、モノにあふれた日本のやる気のない高校生と、同じ地球上でほぼ同じ年代の子どもたちの、両者のおかれている状況のギャップはいったい何なんだろうと考え込んでしまった。
たった1ヵ月間だけの、突然来た訪問者を、教師、生徒の皆は快く迎えてくれ、いろいろな話をしてくれた。どこから情報を手に入れるのかはわからないが、「国連の事務総長にオガタサダコはなったのか」とか、「もはや国連はアメリカの言いなりだ」などなど生徒から言われ、逆にこっちがしどろもどろになる場面もあった。
また、「早く祖国に帰りたい」と生徒たちは言うが、教師たちはそれぞれのようで、あるソマリア人教師は「自分の国に帰ったって仕事はないし、食糧も満足にない。ここ(難民キャンプ)なら、まあ食糧も配給されるし、子ども達も教育が受けられる。」と複雑な胸の内をのぞかせた。
研修期間中、9月23日に”Education Day”が開かれた。これは、日本でいう文化祭のようなもので、小学校からは特別教育の生徒たちが一堂に会し、歌や詩、劇などを披露するというもの。看板もきれいに色ぬりされ、手作りのイベントという感じのあたたかさが伝わってきた。他に、”Africa Refugee Day”というイベントもあり、難民たちの数少ない楽しみのひとつとなっているようだ。
主催者のケアのスタッフはよくやっていると思った。今回の研修で印象に残ったこと、特に私の関心を引いたことは次のような事柄だ。
まず、キャンプ・サダコショーでの出来事。
難民の子ども達に何かできないか、ということで今回参加したキャンプ・サダコショーを開くことになった。参加メンバーの国の紹介という簡単なイベントだったが、大人も子どももたくさん見に来てくれて、結果的にはまあまあだったのでは、と思う。ただ、ひとつ、全く予期せぬ出来事が起こった。
途中までなごやかにすすんでいた。イベントだったが、あるメンバーが自分の国の祭で使う手作りの十字架を持ち出したその瞬間、満員の会場から子ども達のほとんどが去っていってしまったのだ。場内は騒然。私も一瞬何が起きたのかわからなかった。このイベントに協力してくれたケアのスタッフは、大あわてでキャンプ・サダコショーの趣旨を説明。「このイベントは単に各国の紹介をするだけで、宗教を共生するものではない」必死に釈明。延々20分くらい続けた結果、子ども達は開場に戻ってきてショーは再開された。観客(大半はソマリア人)の宗教がイスラム教とわかっているところへ十字架をもち出すのは無神経、という意見もあるかもしれないが、改めて宗教の力の大きさ、影響力を感じずにいられなかった。
次に、女性(の人権)の問題である。 学校で生徒や教師の女性の数が圧倒的に少ないことに象徴されるように、女性の社会的地位(と私はみた)はまだまだ低い。ファイアーウッド(まき)を集めに行って女性がレイプされる例は枚挙にいとまがないし、家庭内暴力も後をたたない。だからこそ、”女子の人権”に関するワークショップがさかんに開かれているのだろう。しかし、これらのことを長い間の”伝統・文化”と片付けてしまうか、そうでない問題とみるか-難しいところだ。セカンダリーの教師が、「宗教は伝統であり文化・習慣だ」と言い切った光景が私の脳裏にあざやかに甦る。
わずか1ヵ月のプログラムではあったが、私にとっては非常に有益で、役に立ち、勉強になることがとても多かった。世界のいろいろな国の友達ができたこともとても良かったと思う。今後も何らかの形で交流を続けたいと考えている。
私の最大の反省点は語学力だった。もう少し語学ができたのならもっと自分の納得のいく活動ができたのに、と思う。他のメンバーの語学力には脱帽だ。と同時に、とにかくすごい人たちばかりだったと今さらながら思う。あの、日中の温度が40度になるのではないかと思えるほどのダダーブの暑さの中、精神的にフィールドへ出て自分のプロジェクトを進めていった。そのタフさと行動力は、特筆すべきものがある。
今回、ほとんど自分で出した参加費用は決して安いものではなかったが、それ以上に得るものがあり、自分自身は行ってよかったと思っている。
キャンプの様子も、以前見たザンビアの、ザンビア人もうらやむほどのとても落ち着いたアンゴラ人難民キャンプと違い、これが平均的日本人がイメージしている難民キャンプという状況(粗末な家に、ボロボロの服と裸足の子ども……)を自分の目で確かめることができた。難民キャンプ、といっても本当にさまざまな現状があるのだ。
毎日、UNHCRオフィスから銃を持ったポリスにエスコートされて、車で30分のダダハリキャンプに通うのも意外だった。改めて、正しい情報を得ることの大切さを痛感した。
最後に”キャンプ・サダコ”研修プログラムに参加した感想も含め、UNHCRに対しての提案になるかもしれないが意見を述べたい。
今回、このような貴重な経験、勉強の機会を与えていただいたUNHCRおよび関係の諸団体、スタッフの方々には大変感謝している。が、実際、現地に行って非常にとまどったのは、日本で考えていたプログラムのイメージと相当ギャップがあったということである。これはどういうことかというと、日本でキャンプ・サダコの事前研修を受けた時は、とにかく現地のキャンプに行って実際の様子をみてお勉強して、写真をたくさんとってきて、日本に帰ったら広報活動を一生懸命やってほしい、とまさしく”研修”で気楽に行ってくれればいい、くらいにしか考えなかった。前参加者のレポートをみてもそういう雰囲気だったし……。ただ、キャンプに行って毎日単にキャンプの様子をながめていても仕方がないと思っていたので、私は私なりに現地へ行ってできることを考え、用意をしていった。他の国の参加者も同じなのかな、と安易に考えていたら全然違った。語学をはじめとして錚々たる経験の持ち主だ。そして1ヵ月の研修の間に自分で問題点を見つけ、プロジェクトを作り、できる限りその間、問題解決のために活動するところまでUNHCRケニアオフィスは期待していたのである。その期待通りに他の参加者はそれをきちんとこなしていった。レポートもすばらしいものを次々と残している。私には最後まで語学のカベが厚く、苦労した。このプログラム参加の成果は語学力による部分が少なくないと言っても過言ではないとさえ感じた。そうした他の国と日本の事務所”キャンプ・サダコ”のとらえ方のギャップが気になった。もっと事前の研修の内容の工夫や情報の提供などについてUNHCRに再考願いたい。
最後の最後に。この1ヵ月の経験をひとことでいうなら、日本という国に生まれたことに対してやはり”ラッキー”と思わなければならないだろうという点である。
人は、自分の生まれる国は選べない。