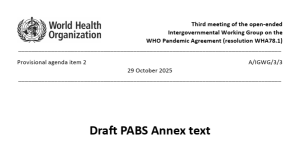Thinking about the bridge of area studies and development studies by tracing “Development and the State”
『アフリカNOW』91号(2011年5月31日発行)掲載
開発と国家 アフリカ政治経済論序説/高橋基樹著
勁草書房
2010年1月25日 初版第1刷発行
横組、本文448ページ
定価:4,200円+税
ISBN:978-4-326-54602-2
※ 出版社サイトに、正誤表・付表1修正版が置かれています。
高橋基樹
たかはし もとき:1959年生まれ。東京大学経済学部経済学科卒業。米国ジョンズ・ホプキンズ大学高等国際問題研究大学院修了(国際関係学修士:アフリカ研究)。日本郵船、国際開発センター、神戸大学大学院国際協力研究科助教授、タンザニア・ダルエスサラーム大学経済研究所客員研究員を経て、現在、神戸大学大学院国際協力研究科教授。本書以外の主著として『アフリカ経済論』(ミネルヴァ書房、2004、共著)、『国際開発とグローバリゼーション』(日本評論社、2006、共著)など。
※ 本稿は、2010年9月4日に実施した『開発と国家 アフリカ政治経済論序説』著者の高橋基樹さんへの公開インタビューから、質問を契機にして、この本の執筆の契機にもなった開発経済学と地域研究に関わる問題意識について語った高橋さんの発言を再構成したものです。高橋さんは、第三世界論への共感から出発した自らの思考の経緯にふれながら、アフリカ諸国に大きな影響力を及ぼした構造調整政策が抱えていた問題を指摘し、新古典派(新自由主義)経済学が前提にしている利己主義的な人間像を問い返すことを提起されました。
【質問1】 高橋さんの著書『開発と国家』(以下、本書)の序章で言及されているハンナ・アーレント(Hannah Arendt)についてお聞きします。高橋さんは本書だけでなく、大学の講義やゼミなどでもよくアーレントに言及されているようですが、開発経済学の本でなぜ著名な政治哲学者であるアーレントで取り上げたのか、開発経済学とアーレントにはどのような関係があるのかについて、まず話していただけませんか。
ハンナ・アーレントはドイツ生まれのユダヤ人女性で、マルティン・ハイデガー(Martin Heidegger)やカール・ヤスパース(Karl Theodor Jaspers)など、20世紀の歴史に大きな足跡を残した著名な哲学者と親しく、彼らの指導を受け、ナチスが政権をとる前は、政治哲学者として将来を嘱望されていました。ユダヤ人ですから、ナチスが政権をとると生死の危機に直面し、アメリカに亡命します。その後、ドイツ語と英語で多くの論文を発表し、現代文明そのものに対する根本的な批判をした人物として、第二次世界大戦後の政治哲学に大きな影響を与えるようになりました。彼女の主張の核心は、20世紀的あるいは近代的な人々の生き方を批判して、人々というのはお互いに対話をして合意を形成し、お互いの公共的な空間を作りあげていくことが重要で、単に生きるとか働くだけの状況から解放されていかなければならないということだと、私は理解しています。
彼女は、自分たちを死の淵に追いやったナチズムそしてスターリン主義といった全体主義がなぜ20世紀に出現したのか、西欧では1789年のフランス革命を始めとする市民革命において人権の理念が高く掲げられているにもかかわらず、百数十年も経ってなぜ突然にナチズムのような全体主義が西欧に現れたのかについて、その理由を真剣に問い返しました。そして彼女は、「ナチズムの源流はアフリカにある」と指摘するのです。アフリカに行ったドイツ人の入植者などがアフリカの人々に出会い、自分たちとは姿も違い、歴史的な背景とか文明とかを持っているようには見えないアフリカの人々に対して、自分たちとは違う人間だと思わざるをえなかった。人種主義は、彼らがアフリカの黒人世界に組み込まれたこと(ヨーロッパのアフリカ化)によって始まった、という趣旨のことをアーレントは述べています。
実はこの点について、東京大学教員の高橋哲哉さんが早くから問題にしておられます。岩波書店から発行されている高橋さんの著書『記憶のエチカ-戦争・哲学・アウシュヴィッツ』(1995)で、このことを指摘されています。残念ながらというか、高橋さんは現代哲学の研究者で、アフリカ学会の会員やアフリカ研究者ではない。私はその点がものすごく悔しい。というのも、私たちアフリカ研究者はたくさんのアフリカ人の友人がいますから、アフリカの人々が違う人間だなんてまったく思わない。このように思っている私たちがアーレントの思想の問題性に気付かずに、(他にもおられるかもしれませんが、少なくとも)高橋さんに先に指摘された。それがかなり悔しくて、私がアーレントにこだわっている理由のひとつにもなっています。
高橋さんも指摘されていますが、アーレントと同じようなアフリカ観を持っていた人が、すでに彼女と同じ国の大先輩にいました。それは哲学者のヘーゲル(George W. H. Hegel)です。ヘーゲルの『歴史哲学講義』というあまりにも有名な本の中に、アフリカについての見方が提示されていますが、そこで彼は「アフリカには歴史がない」と書いています。『歴史哲学講義』の中ではアフリカのことについてもいろいろ触れていますが、例えば、現在のベナンあたりにあったと言われているダホメ王国を、家族同士で殺し合って滅茶苦茶なことをする、非常に野蛮で残虐な国であると描いています。アーレントのアフリカに対する見方というのは、自分より100年以上も前に生きていたヘーゲルの見方をそのまま踏襲しているのです。「アフリカ人の野蛮さ」に出会ったヨーロッパ人、そしてその人たちのものの考え方がヨーロッパに入ってきて、それがナチズムのひとつの源流になったとアーレントは指摘しているのです。
アーレントは、社会主義の思想と体制全体に対して批判的であるだけでなく、1960?70年代に拡がっていた欧米の資本主義や植民地主義に対抗する多様な運動と思想(本書では「第三世界論」と呼んでいますが)にも文句をつけていました。当時の第三世界論の人たちが掲げた旗印は「AALA(アジア・アフリカ・ラテンアメリカ)の連帯」というものです。それに対して彼女は鼻で笑い、「AALAの連帯」なんていうのは単なるお題目に過ぎない、アジアとアフリカとラテンアメリカというまったく異なる3つの世界を一括りにしていること自体がすでに間違いであると述べています。どのように間違いかというと、それは単に「敵」によって連帯しているだけであって、同じ「敵」(第三世界論の文脈からすると南北問題の中の「北」の世界、特に軍事的な手段も使って「南」を抑圧する「帝国主義」)に対抗するという理由だけでアジア・アフリカ・ラテンアメリカを結びつけるという考え方はおおきな誤りだと、アーレントは主張したのです。
アジアやラテンアメリカとアフリカを一緒にしてはいけないということは、アフリカの特殊性とか固有性とかを捉えなければいけないと考える私たちアフリカ研究者からすると、ある意味では歓迎できることかもしれません。しかし、アーレントの本をよく読んでいくと、彼女は(ラテンアメリカはあまり問題にしていませんが)アジアとアフリカを一緒にすることの問題は、アジア人をアフリカ人と一緒にする(その逆ではなく)ことにある、と書いているのです。で、アフリカ人は何者かというと、世界の一番下の段階にある人たち、虐げられた人たちであり、彼らこそ帝国主義者に踏みつけられており、とても貧しいので、自分たちについて自己主張する権利はある。一方で、アジア人はもっと立派な人たちで、ヨーロッパと並び立つような文明を昔は持っており、彼らとアフリカ人を一緒にするのはとんでもない、と言っているのです。中国人に「あなたたちはバンツー族と一緒ですと言ったら目を丸くしますよ」という言葉が1970年代の彼女の本に出ている。アーレントはナチズムの起源を、ヨーロッパ人がアフリカへ出かけて行き、ものの考え方が変わったというところまでさかのぼって分析しました。そうした考えをひとつの柱として近代の本質の一面を見極めようとしたアーレントの著書『全体主義の起原』(”The Origins of Totalitarianism”)は1951年に英語圏で出版されましたが、そこでのアフリカの人々に対する問題ある見方が、20年後の1970年代にも維持されていたのです。
アーレントの発言は1970年代で終わっていますから、そんな人は相手にしなくてもいいじゃないか、と思われるかもしれません。しかし、アーレントのアフリカに対するものの見方が、現在の開発経済学・開発研究においても無縁であるとは言えません。本書では、現在のアフリカ政治研究を牽引している世界的権威の一人であるパトリック・シャバル(Patrick Chabal)を取り上げています。現在彼は、フランスとイギリスの学界で大きな発言力を持っていますが、そのシャバルがダロズ(Jean-Pascal Daloz)と共同で執筆した”Africa works”という本があります。私は「アフリカは作動している」と訳しましたが、この本では、アフリカの状況はどうしてこんなに反開発・反民主主義なのかという問題に対して、一言で言ってしまえば「それはアフリカだからだ」という「答え」が提示されています。援助する側がアフリカに人々に対して「もっと豊かになりなさい」「もっと自由で民主的な世の中を作りなさい」と一生懸命に誘いかけ、場合によっては「言うとおりにしないと援助しないよ」という脅しすらかけても、アフリカの人々は言うとおりにしてくれない。それはなぜなのかというと、民主化をせずに、人々が開発を選ばない方が都合がいいと思っているアフリカの政治エリート(政治研究におけるエリートという言葉は「権力者・支配者」のことを指します)がいるからだというのです。彼らはそういう論理によって動いている、とシャバルは主張しています。
しかし、その論理がどこからくるのかについては、シャバルは説明していないのです。そういう説明がないので、彼のこの「答え」は単なる「叙述」にすぎないと、私は本書で指摘しました。アフリカのエリートがもしそういう支配の仕方をしているのであれば、それはアフリカであるからだという議論ではなく(この議論では、アフリカがいまそういう状況にあると描いているにすぎないことになります)、アフリカが現在なぜそのようになってしまうのかということを分析しなければならない。シャバル的な見方、アフリカはアフリカだからわれわれとは違う、開発にも参加しないし、民主化も選択しない、最終的には人々を豊かにしない、そういう社会であるという見方は、実は近代の古い見方としてヘーゲルあたりから現れている。本書では、それを現代につないでいるのがアーレントだということを言いたかったのです。
先ほど紹介した第三世界論は、1960年代後半から1980年代にかけて世界的にかなりの影響力を持っていました。世界全体の人々の解放は、途上国や植民地の人々と先進国の人々が手を携えて進めていかなければいけないという考え方に、私自身も1970?80年代にかけて強い関心を抱いていました。それに対して、アーレントはそんなものは嘘っぱちであると言ったのですが、それはちょっと偏った見方ではないかと、私は考えています。
アメリカは1975年にベトナム戦争に敗北し(アメリカ人は負けたとは言いませんが)、アメリカの社会は非常に傷つきます。その一方で、アメリカ軍が勝手にベトナムに侵略して行った非人道的行為や戦争犯罪に対して先進国の人間も立ち上がりました。日本でも欧米でも、そしてアメリカ国内でもベトナム戦争に対する反対運動が広がっていったのです。さらに途上国の中でも、ベトナムに連帯しようという動きが広がりました。
同じようなことは実はアフリカにもありました。本書を読むと、私がこの時代に誰のファンだったのかがばれてしまうのですが、それはギニアビサウおよびカーボベルデの独立運動の指導者であったアミルカル・カブラル(Amilcar Cabral)という人です。アフリカ史に少しでも詳しい方はご存知のように、アフリカの植民地解放運動は暴力的な闘争をあまり伴いませんでした。しかし、いくつかの国々だけは例外的に武装闘争に訴えざるをえなかったのですが、その理由のひとつとして、世界最古の帝国ポルトガルが最後までアフリカの植民地を手放さなかったということがあげられます。カブラルは民族解放闘争そして武装闘争は注目すべきものであり、それは帝国主義に対するアンチテーゼとしての第三世界論なしには語ることができません。
戦争を賛美すること自体は良くないと思いますが、ジャングルに入ってポルトガルの支配と戦ったカブラルは、ギニアビザウではいまでもとても尊敬されています。武装闘争ですから、もちろんお互いに殺し合いをしますが、カブラルはポルトガル兵を捕虜にするととても丁重に扱ったと言われています(研究者としては事実を良く確かめる必要がありますが)。他方でポルトガル軍は、捕えたギニアビサウ人を残虐な方法で殺したり、見せしめのために拷問をしました。その当時のポルトガルの政権(アントニオ・サラザール政権とそれを引き継いだマルセロ・カエターノ政権)は、ナチズムのなれの果てのファシスト政権でした。第二次世界大戦後にもスペインとポルトガルにはファシスト政権が残存し、政権の正当化の根拠のひとつとして植民地支配を継続していました。
これらの政権は、植民地で多くの残虐行為を行いますが、それに対してカブラルは同じように報復するのではなくて、反対にポルトガル人を人道的に扱うということによって道徳的に勝利をしていくのです。さらにカブラルが率いた解放勢力は、ポルトガルと戦いながら同時に、ギニアビサウの人々に文字を教えていきます。さらに保健サービスも実施していく。それは、ポルトガルに支配されていた側にいたギニアビサウの人々にはとても享受できないサービスでした。しかも当時は、宗主国のポルトガルの田舎でもこのような人間開発政策が行われていない可能性がありました。そのころのポルトガルは識字率が低く、先進国であるとはとても言えなかったのです。
ポルトガル人にとっては「敵」になった肌の黒い人々が、植民地解放闘争を通じて否定しているのは何か。一番ショックを受けたのは、実はポルトガルの若い軍人でした。当時のファシスト政権のもとでは、一番のエリートは軍人です。ギニアビサウの解放闘争に触れた若い軍人は、ポルトガル自体を変えなければならないと思い始めたのです。こうして、ファシスト政権のもとでファシストの考え方を教え込まれて育ったはずのポルトガル人の青年将校が、1974年にポルトガルの首都リスボンで「リスボンの春」あるいは「カーネーション革命」と呼ばれるクーデター起こします。そしてファシスト政権を打倒して、次に彼らは、当時のポルトガルの植民地であったギニアビサウ、カーボベルデ、アンゴラ、モザンビークの植民地解放勢力と握手をして、独立を認めていくのです。そのことによってポルトガル自体も、植民地支配とファシズムという支配の病気から解放されていきます。このことは、カブラルの戦いが道徳的にもヨーロッパの側を変えるという化学反応を起こしたと言われていました。カブラル好きの私は、もちろん魂を深く揺さぶられた気がしましたし、いまでもその感動は心に残っています。
そしてこのことから考えても、第三世界論の果たした世界史的な役割を無視してしまうアーレントは、やはり帝国主義に踏みにじられた途上国の人々の歴史を軽く見ている。近代が作り出した途上国の人々への暴力性に対して関心が薄いと言わざるをえないのです。
【質問2】 次に、構造調整政策(SAP: Structural Adjustment Policies)についてお聞きします。本書の結章の第2節「開発援助とアフリカ」の冒頭において「援助供与側の、アフリカの国家の運命を左右するような関与と影響力が実際に問題になり始めたのは、(中略)構造調整政策の実施の時代からである」(p.357)と述べられています。高橋さんは、構造調整政策がどのような場面において、どのような問題をもたらしたと考えられますか。
まず、構造調整政策がどのようなものであるのかについてごく簡単に説明します。アダム・スミス(Adam Smith)の名を聞かれたことがあると思いますが、彼の思想は自由放任主義だという言い方をされています。誰もが経済活動を自由に行い、自分の利益のために、市場で欲しいものを買い、自分が売りたいものを売る。自分の利己主義的な利益を追い求め、みなが売り買いすることによって世の中全体がうまくいくというように、自由放任主義は「神の見えざる手」という言葉で説明されてきました。端的にいうと、こうした自由放任主義を1980年代以降に政策としてはっきりと打ち出し、世界中に広めていこうとしたのが新自由主義であり、この考え方に基づく政策が構造調整政策であると言えます。
新自由主義を進めていくうえで必然的に問題になるのは、市場の邪魔をしている、自由な取引の積み重ねを邪魔しているものを退場させるということですね。そのものは、政府のさまざまな役割だと言うこともできますが、新自由主義の考え方では政府の役割を究極的にしりぞけて、できるだけ「小さな政府」をつくらなければならないということになる。1980年代に登場したアメリカのレーガン大統領やイギリスのサッチャー首相は、自分たちのイデオロギーとして、こうした考え方に基づいた政策を強固に進めていきました。そしてこの政策が、国際通貨基金(IMF)や世界銀行を通じてアフリカにも及んでいったのです。アフリカだけでなく、アジアやラテンアメリカの国々にも少なからず影響を与えましたが、アフリカで進められた構造調整政策は常に大きなコストを伴い、大きな政治経済的な変動を起こし、アフリカ各国の指導者たちが追求しようと思っていた政策をできなくさせてしまったのです。構造調整政策を推進した世界銀行やIMFの権力がどこに根ざしているのか。これらの機関がアフリカのそれぞれの主権国家の運命を大きく変えてしまったことの根拠はどこにあるのか。彼らのかたくなさの根本はどこにあるのか。本書を執筆したのは、研究者としてこうした問いについて考えようとしたからであるとも言えます。
一例として、構造調整政策がタンザニアにもたらした問題について述べてみます。タンザニアの初代大統領であるジュリウス・カンバラゲ・ニエレレ(Julius Kambarage Nyerere)は、独立・建国・開発の父であり、現在のタンザニアでもとても尊敬されています。彼はウジャマー(ujamma)という理念を掲げて、その考え方の基で国家を社会主義的に導いて開発を進めようとしましたが、1985年にその志もあえなく辞任してしまいます。アフリカの大統領や首相では、自分の非を認めて辞めた最初の人物になりました。彼がどうして自らの非を認めざるをえなかったのかというと、そこには構造調整政策が大きく関係しています。ウジャマー政策に代表されるアフリカ社会主義は、『アフリカ現代史Ⅱ 東アフリカ』(吉田昌夫、初版=1978 /第3版=2000、 山川出版社)でも指摘されていますが、アフリカ諸国の独立後の約20年間は、輝ける国家建設の理念になっていました。それが1980年代になると、構造調整政策によって息の根を止められてしまいます。
当時のタンザニアは借金(債務)が積もりに積もって返済できなくなっていました。そうすると次に何が起こるかというと、輸入ができなくなる。飢えている人がいるのに食料が買えず、子どもの予防接種のためのワクチンが買えなくなるという状況に陥っていく。しかしニエレレの政府は、自分たちとは理念が違うという理由で、IMFや世界銀行から融資を受けようとはしませでした。一回でも融資を受けたならば、IMFや世界銀行は自分たちの言うとおりに政府がいろいろと経済に介入することをやめて、もっと国民が自由に市場でものを買い、自分の欲しい値段でものを売ることを認めなさい、と指示するに違いないからです。
しかし、そうやって3-4年も経つ内にどんどん債務が増え、結局は国の財政が破綻しそうになった。そこでニエレレは、「がんばったけれども、皆さんと約束したようには国を作れなかった」と言って、1985年に大統領を辞任します。そこで迫られたことは何かというと、先進国と同じように政府はほどほどに小さく、基本的には市場経済によって経済の原理が動いていくような社会を作りなさいという、IMFや世界銀行の融資の条件だったのです。実際、このようにして市場原理は世界そしてアフリカに権力的に広げられていきました。
それぞれ独立国であるはずのそれぞれのアフリカの国家の理念、いわば国是とでもいうものが、外からの力によってつぶされてしまう。こうしたことがなぜ起きたのでしょうか。IMFや世界銀行には間違いなく権力があります。アメリカという世界で最も力を持った国の財務省がその背後で支持をしているだけでなく、アメリカはIMFや世界銀行の大株主なので政策を左右する力もあります。アフリカ諸国は、1970-80年代にかけて、財政の資金繰りが非常に厳しくなっていき、融資をしてくれる側の意向に従わざるをえなくなったのです。
では、融資の条件の中身がなぜ自由放任の考え方なのでしょうか。もっと問題にしなくてはならないことは、次のことです。
私は、IMFや世界銀行にも何人か友人がいますが、彼らと個人的に話をしてしばしば感じるのは、とても正義感があるということです。自分たちが非常に厳しい融資の条件をアフリカ諸国に突きつけると、もしかしたら子どもが死んでしまったり、学校に行けなくなってしまうかもしれないということに対してひとりひとりはかなり自覚的で、自分の責任ということを重く考えています。それにもかかわらず彼らは、自分たちが考えた政策をやり抜くという、まあいってしまえば気迫を持っている。
しかし、それは転倒した考え方ではないかと、私は思います。その証拠に構造調整政策は、その後のアフリカを開発や貧困削減に導くことには成功しませんでした。IMFはともかく世界銀行は開発を進める機関ですから、貧困削減という結果をもたらすことができなかったならば、説明責任が問われることになります。説明責任を問われたことによって、彼らの言っていることは、1990年代に少なくとも表面的には大きく変わりますが、それは口先だけのことで、お題目を変えたに過ぎないように見えます。むしろ、1980年代の彼らのものの考え方のどこに問題があったかということを問わなくてはなりません。
新自由主義・新古典派経済学の考え方は、それ自体はとても分権的であるにもかかわらず、その考え方を世界に押し広めようとした構造調整政策は極めて権力的なものでした。この理念的な権力性はどこから生まれてくるのか。おそらくそれは、理論の一貫性に対するわれわれの信仰とでもいうものの中にあるのではないか。ある理論の体系を進めていこうという発想が常に自分の頭の中にあると、その体系から外れるものは見ようとしない。異物を取り入れようとしない。何か違うものがあった場合でも、自分と同じものとして常に解釈していこうとする。私の理解が正しければ、アーレントよりさら若い世代のドイツの哲学者のユルゲン・ハーバーマス(Jurgen Habermas)は、古いマルクス主義の特徴を批判する際に、こうした発想をモノローグと呼びました。モノローグはダイアローグ(対話)の反対語ですが、彼は、こうした発想は自己との対話でしかない、異物や他者を排除するではなく、常に異物と対話する必要があると述べています。
そのうえで重要なことは、私たちが世界の中で異物や他者と対話をするためには、実は異物や他者の側が発話をしてくれることが必要だということです。私たちがアフリカのことを知ろうとするならば、アフリカ自身が発話をしてくれなくてはならないのです。
世界銀行やIMFの人たちのものの考え方は、もっとも典型的なモノローグのひとつになります。彼らは、自分たちが教科書の中で学んだことと同じように、さまざまな経済現象が必ず起こるに違いないと信じ、大きな失敗をしでかします。彼らは、「悪い」政府を退場させると「良い」市場が自然に現れ、市場が物事を効率的に配分していくので、アフリカ諸国の病である財政赤字や国際収支の赤字、その帰結である対外債務などがすべてきれいになくなり、経済が成長し貧困が削減されていくという、首尾一貫した論理的な青写真を描いていました。だが実際には、そうしたことは起こらなかった。この現実をふまえて、彼らが持っている理論や理念の問題性に対して批判をしていこうと考えています。
【質問3】 最後に、人間像を問い返す意味についてお聞きします。高橋さんは本書で、開発経済学が前提にしている人間像を問い返すという問題提起をしています。開発経済学を考えることと人間像にこだわり人間について考えるということとは、どのように関連していると考えられますか。
人間像を問い直さなければならないということは、かなりの人に関心を共有してもらえることだと思います。一方で仲間の経済学者からは、本書で人間像を問い直すような余計なことはしなくていいのではないか、アフリカの話に関心を集中すればよいのではないか、こうやって人間像を問い直すという大風呂敷を広げたために全体を締めくくれていないのではないか、などと批判されています。人間像を問い直すということは、主流派の経済学(新古典派経済学と言ってもよいでしょう)の前提を疑うということにもなります。私自身は地域研究者で、経済学の大きな体系から言うと一番はずれの方にいます。地域の現場の中で、いつもあっちへ行ったりこっちへ行ったりして苦しんで、現実の事柄を経済学的にどう解釈したらいいのかと、いつも答えが出せず悩んでいる。そうした人間が、主流派経済学の前提に挑戦すべきだとぶち上げて、そして答えが出せていない。それは竜頭蛇尾ではないかとも言われています。
基本的な経済学の体系として、新古典派経済学はある意味で一番優れていると思います。前提がもっとも明確で、そこから数学的に解き起こしていくと、市場全体で一番効率のいい状態=パレート最適は何かということまですべて数学的に解けてしまう。パレート最適を導くための理論というのは、論理の一貫性という意味では優れている。しかし、ここからが肝心なことですが、仮定されている前提条件を一個一個覆していくと、どんどん論理体系が崩れていく。そのやり直しの作業を進めることが現在の経済学理論の最前線になっている。そして、こうした作業を行っている人たちに対して理論家でない私も、「皆さんのやっていることの方向性は正しい」と言いたいのです。
私がなぜそのように考えるのかというと、実は単純な事実に基づいています。皆さんひとりひとり、そしてアフリカ人のひとりひとりは、ミクロ経済学の教科書の最初の部分に書いてある人間像とはまったく違います。アダム・スミスの片面である、自分の利益しか追い求めない人間像とはまったく違う。われわれはやはり家族や仲間のことを心配しているし、ときどき倫理的に悪いことをしたりするとやはり後ろめたいと思い、しばしばそういうことで悩み苦しむ人間なのです。そういう多面的な人間像というのを研究の中にインプットしなければならない。
構造調整政策は、どちらかというと利己主義的な人間像だけを道具に、理論だけで目の前にある経済を分析した究極のかたちでしたが、それはうまく機能しなかった。その理由のひとつは、人びとが利己主義的に個人的な利益のみを追求して動いているわけでは決してないからです。さらに、市場経済に参加している人々が徹頭徹尾、利己主義的かと言うと、そうではない。一部の経済学者のからは強い反論を受けるかもしれませんが、本当に利己主義的であるならば、お金を払わず物を盗むことが、自分のコストはかからないので、経済学的には一番合理的な行動になります。ところが利己主義的なはずの市場は、実は誰もがきちんとルールを守ることで成り立っているのです。
実際には、市場全体の秩序が壊れると自分の利益にならないからルールを守ろうという考え方を日常的にしている人はほとんどいないでしょう。万引きや詐欺、ちょろまかしなどが道徳的に良くないと思うからこそ、そうしないのではないでしょうか。法の支配が確立しているところでは、それらの不正行為への罰や制裁を恐れるという要因ももちろんあるでしょう。しかし、その恐れだけで、日々の無数の市場取引が支えられているわけではないと考えています。
私が大学生のとき、世の中には共同体とその外しかない、ということを習いました。共同体の中というのは平和で、みながお互いのことを心配しているから、全体の生産量が十分であれば食いはぐれることはない。しかしその外に出たら、それは狼の世界で、みなが利己主義的で、自分の仲間ではないから人間どうしが食い合う世界であると。
ところが現在、世界中で進行していることは何かというと、見たことも聞いたこともない、仲間でも何でもないと思っている人たちがインターネット上でクリックするだけでお互いに物事をやりとりして、しかも正直に代金を払っている。そういう仲間でも何でもない人たちの中で市場経済が成り立つのは、相互にルールを守るという暗黙の了解があるからなのです。このルールは、歴史の中で形成されてきましたが、利己主義的な人間だけ集まっていたら決してできることではない。ルールは誰かが作らなくてはならない。
こうした市場外のことをあまりにも無視してきたのが、新自由主義あるいは新古典派の考え方なのです。新古典派的な、先ほど述べたように利己主義的な人間像から始まりパレート最適まで至る社会は、契約のルールを守るという前提がなければ成り立ちません。しかしその契約のルールは、自分の利益をはかるための場である市場の外で作られている。外からの社会の働きがないままでは、市場そのものが成立しないし、機能しないのです。
さて、人間のあり方に関わる抽象的な話をなぜしたのかというと、そこまでさかのぼらないと、アフリカの開発を語ることはできないということが私の問題意識になっているからです。アフリカには正直な友人がたくさんいますし、アフリカの人々は私たちよりはるかに親切である一方で、初めて会った人には私自身もよくだまされますし、泥棒の被害にも会いました。アフリカの経済が発展してゆくためには、そういうものをなくしていかなくてはなりません。もちろん日本にも不正行為を行う人はいますが、私たちの日常を覆いつくしている日本の市場経済の動きのほとんどは、見知らぬ他者への信用によって動いている。その一方でアフリカの社会の多くが、見たことも聞いたこともない人々の間での信用というものを確立できていないために、いかに苦しんでいるかということが問題なのです。銀行のシステムなどは、信用がなくては動きません。多くの貧困国では、銀行システムさえ簡単には発達しません。では、政府が規制すれば物事が解決するのかといえば、そういう問題でもない。このようなことが言いたくて、人間像までさかのぼって考えてみたのです。
アフリカの複雑な現実にアプローチするためには、私たちが日常的に当然のように前提としていることや、主流派経済学が長い間当然の前提としていることを疑ってかかる知的な腕力や耐久力が必要でしょう。特に、純粋な市場経済の枠から抜け出て、政治と経済の関連や市場を外から規定しているものを見ようとする場合、単純な人間像を疑い、複眼的なものの見方をしなければならない。本書の目的のひとつは、この点について問題提起をすることにあります。
また、新古典派経済学があまりにもみごとに体系的に完成されたために、世界の文化・学術の中心になってきたアメリカで、その経済学の手法を別の分野にもどんどん拡大していこうという知的傾向が起こりました。そのひとつは、明らかに政治学です。国家のあり方を研究する分野で、新古典派経済学の手法を用いて国家や政治の動きを分析しようという動きが、20世紀の末ころまでに強まってきた。新古典派的な方法による政治分析は非常に鋭利で、首尾一貫した論理的な知見を私たちに教えてくれたと同時に、鋭利すぎていろいろなことを見落してしまった部分があります。その典型例のひとつはアフリカ国家論であると言えるでしょう。
経済以上に政治の世界でも、人間は明らかに利己主義的な原理だけで動いていない。日本の政治家やその他の政治的アクターも、彼らなりに日本の国について考えていますし、自分なりのイデオロギーや理念がある。支配の論理に基づいて、決して単純な個人的な利益のためではなく、他人におせっかいしたいと考えたり、あるいは仲間内の義理人情によって動かされています。
こうした事情を多面的に捉えないと政治の分析はできないはずですが、新古典派的な政治解釈は物事を非常に単純化させてしまいます。そして、そうした解釈をある程度は支えにしながら、構造調整政策も動いてきた。私たちの思考方法も(経済学の最先端における改変の努力はありますが)単純化の傾向を持っているのではないでしょうか。そして、こうした政治の理解は、市場がはらんでいるモラルを希薄化し、あるいは壊してゆく傾向に対抗しようとするときには、助けにならないのではないでしょうか。本書では人間像を正面から問いかけ、こうした状況を変え、人間が共同性を持っていることを正面から捉えて、状況を変えるような議論を始めようよと呼びかけました。
ただし、共同性も市場と同様に複数の面があり、ポジティブな意味だけを持っているわけではありません。本書では、仲間との共同性ということを私たちの考察に持ち込むことも繰り返し論じています。その議論の対象は農村の人々の間の相互扶助だけでなく、より前向きの生産的な共同性であったり、ある国全体の共同性であったりしますが、同時に人々の個性や個人的な努力を阻害する共同性であるかもしれません。
国家論の関係で言うと、アフリカでは残念ながら、民族集団という単位でまとまることがある国全体の共同性・公共性を妨げるという現象が見られます。そうした部分的な共同性、本書の言葉では「部族」主義がなぜ生じるのか。民族や「部族」は過去から変わらずに存在しているものではなく、近現代の歴史のなかで変わってゆくものです。その流動性をふまえて、本書の後半部分ではケニアを事例として、アフリカの国家を民族問題の観点から論じました。民族問題はカブラルでさえ悩まされ、彼が目指したギニアビサウとカーボベルデの合邦はついに成りませんでした。民族・言語の著しい多様性を特徴とするアフリカが「部族」主義を乗り越えてゆく過程から、人類社会が現在の相違や格差を越えてゆく営為の先駆けとなる可能性を見出すことができるかもしれない。この点はアフリカの現状をご存知のかた、あるいはご興味をお持ちのかたにもそれなりにおもしろい問題意識になると自負していますので、ぜひ本書をお読みいただき、ご批判をしていただければ幸いです。