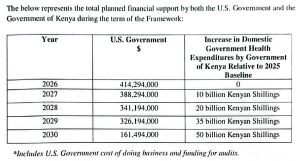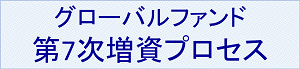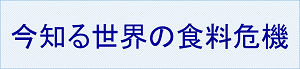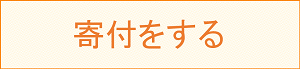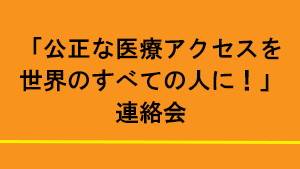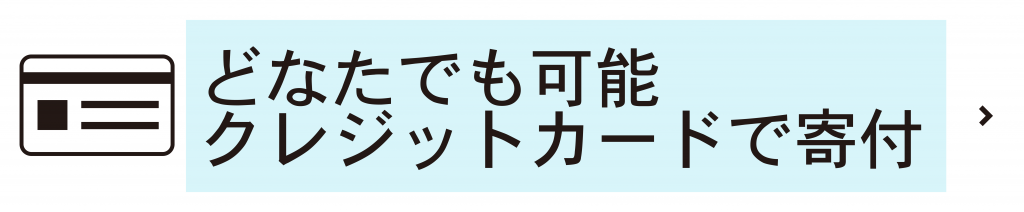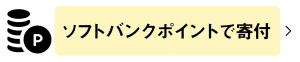閉じたコミュニティを作らない
―「アデイアベバ・エチオピア協会」の挑戦 ―
2025年5月24日葛飾区四つ木地区センターで第二回アフリカ玉手箱 「日本に暮らすエチオピア人と私たち〜地域社会とつながり助け合う〜」が開催されました。登壇者は、NPO法人アデイアベバ・エチオピア協会の代表、アベベ・サレシラシェ・アマレさん。
日本に住むエチオピア人は637人(2024年6月時点)。中でも葛飾区は在住者が多く、彼らの生活支援を行うべく立ち上がったのが「アデイアベバ・エチオピア協会」です。その背景には、母国での政治不安や、難民として来日した人々の生活苦がありました。日本語が話せない、制度が分からない、住居が借りられない ーそんな困難に直面する同胞たちを支えたい想いから、NPO法人化に至ったといいます。

アベベさんが強くこだわるのは、「閉じたコミュニティを作らない」ということ。「私たちは“エチオピア人だけの世界”にとどまらず、地域社会と交わることを選びます。そうでなければ、水と油のように交じり合わない孤立した存在になってしまう。それは私たちも、日本社会にとっても不幸です。」欧州では、移民が現地社会から分断され、相互不信や社会的摩擦を引き起こしている事例もあります。「そうならないために、つながる努力を惜しまない」―アベベさんたちの活動は、この覚悟のもとに成り立ちます。
活動の中心にエチオピアと日本の文化を結びつける数々の取り組みがありました。
• エチオピアのパン「ダボ」やコーヒーセレモニーを振る舞う食事外交
• 和菓子・茶道体験、浴衣での夏祭り参加など、日本文化との接点を大切にした交流イベント
• 年3回の文化交流会で、エチオピアと日本の新年などを共に祝う体験
「一緒に食べたり経験を共有することで、言葉を超えてつながれる」という姿勢です。たしかにセミナー終了後のエチオピアレストランでの食事会では、みんなで大皿を囲みインジェラで料理を包み食べながら歓談するというエチオピアならではの楽しさに溢れていたように思います。
今では当協会の活動参加者の6割が日本人。ボランティアや役員にも日本人が加わり、「支援する/される」関係を超えて、共にコミュニティを築く存在へと変化しています。区役所や学校との連携も深まり、葛飾という街に根を張った存在になりつつあります。「葛飾は、今や私たちの“ふるさと”。」そう語るアベベさんの言葉から、日本という地で着実に育まれてきた信頼の重みを感じました。
会場で思わず頷きが広がったのは、日本とエチオピアの文化的共通点に関する話題です。
• 年長者を敬う言葉文化(敬語があり、目上の人との話し方が異なる)
• 建前を大切にするコミュニケーション(本音と使い分ける柔らかな表現)
• 独自の食文化(刺身や納豆 vs エチオピアの生肉料理)
「だからこそ、日本社会になじめる素地が私たちにはあると思っています」と語るアベベさん。
移民や難民を“受け入れる”だけでなく、“地域の仲間として迎える”社会へ。そのためには、相互理解と交わりの場づくりが不可欠です。「水と油にならないために、混ざろうと努力する」アデイアベバ・エチオピア協会の実践は、多文化共生社会を目指す私たちに大切な何かを伝えようとしています。

<講師プロフィール>
アベベ・サレシラシェ・アマレ(Abebe Sahlesilassie Amare):1996年に留学生として来日。その後、日本人と結婚し、2009年には「アデイアベバ・エチオピア協会」を設立し理事に就任。日本に住むエチオピア出身の人々が、日本社会によりよくなじみ、日本人とともに安心して暮らせるよう、生活や仕事の支援を行う。日本とエチオピアの交流を深める活動や、エチオピアの貧困層を支援する取り組みも展開。2023年に理事長に選任された。足立区在住。