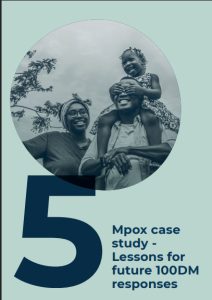Distorted “Democratization” and crisis in Libya
『アフリカNOW』No.94(2012年3月発行)
執筆:高林敏之/TAKABAYASHI Toshiyuki
たかばやし としゆき:1967年生まれ。青山学院大学大学院文学研究科博士後期課程(史学専攻)単位取得満期退学。社団法人アフリカ協会職員、四国学院大学教員を歴任。現在、日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会常任理事、西サハラ問題研究室主宰、早稲田大学理工学術院非常勤講師。アフリカ国際関係史・西サハラ問題を研究。
はじめに
2011年初めにチュニジアとエジプトの長期独裁政権を相次いで崩壊させた「北アフリカ革命」は、アフリカ最長の独裁者ムアンマル・アル=カッザーフィー(カダフィとも表記される。Muammaral-Qaddafi)大佐がおよそ42年にわたり君臨してきたリビアにも波及、北大西洋条約機構(NATO)諸国やアラブ君主制諸国の大規模な軍事介入を伴う内戦に発展した。同年10月のカッザーフィー殺害により体制は崩壊したものの、リビアの混乱に収束の兆しは見えない。
チュニジアとエジプトにおける非暴力的な変革とは対照的にリビアが大きな混乱に陥ったのは、同国の特異な歩みに起因する、国家としても市民としても極度に未成熟な状況ゆえであったと考えられる。反カッザーフィー勢力を支援する諸外国の軍事介入は、「民主化支援」とは別の動機によってなされたもので、リビアの混乱をさらに増幅するものでしかなかった。本稿では以上の点を、アフリカ国際政治の文脈や「アラブの春」に関する議論と関連づけながら、具体的に考察したい。
脆弱な「国家」の枠組みと地域間対立
アラブ・イスラーム世界、アフリカ世界、地中海世界の十字路に位置し、マシュリク(東アラブ)とマグレブ(北アフリカ西部)との中間地帯にもあたるリビアに初めて今日の国境線を画したのは、1911-12年の戦争でオスマン帝国からこの地を奪取したイタリアである。しかし、19世紀に東部キレナイカ(Cirenaica /Cyrenaica)地方で勃興したイスラーム復興主義勢力サヌーシー教団を中心とする激しい反イタリア抵抗闘争が続き、イタリアのリビア支配がようやく確立されたのは、ムッソリーニ時代の1931年であった。この間、イタリア軍による苛烈な弾圧と強制収容策により8万人もの人々が犠牲になったとされる。
イタリア支配は短命に終わり、第2次大戦後にリビアは戦勝国イギリス(東部キレナイカ、北西部トリポリタニア[Tripolitania])とフランス(南西部フェザーン[Fezzan])により分割占領された。3地域の間には将来をめぐる意見の対立があり、とりわけキレナイカには単独独立をめざす動きさえあったが、結果的には1949年の国連総会決議に基づき、1951年に「リビア連合王国」として独立したのである(1)。新生リビアの国王には、サヌーシー教団の長ムハンマド・イドリース・アル=サヌーシー(Muhammad Idris bin Muhammad al-Mahdi al-Senussi)が推戴された。
独立当初のリビアは連邦制をとり、トリポリタニアの中心地トリポリと、キレナイカの中心地ベンガジの双方を首都と定めた。しかし1963年の連邦制廃止後は国王とサヌーシー教団の地盤であり、油田も集中するキレナイカが偏重されるようになる。行政の中心地として定められたバイダや王宮の所在するトブルクなどキレナイカに国家の主要機能が集中していき、唯一の大学もベンガジに開設された。
イドリース王制は1969年、アラブ民族主義とアラブ統一の理想を掲げる統一主義自由将校団のクーデターにより打倒され、当時27歳の青年将校カッザーフィー大尉(のち大佐に昇進)を議長とする軍事政権、革命司令評議会(RCC)が成立した。以後約42年にわたり続くカッザーフィー体制のもとで、旧王政の地盤であったキレナイカはその優位性を失い、エジプトのイスラーム復興主義運動の影響を受けやすいこともあって、繰り返し粛清・弾圧にさらされた。このことは、2011年の反カッザーフィー蜂起がなぜキレナイカを中心に展開されたのかを理解するうえで重要である。
このように、現在のリビアという枠組みが成立してから歴史が浅く、統一的な権力による統治もカッザーフィーの登場まで徹底しなかった。かかる状況下で地域対立が温存され、「国家」としての一体性が脆弱なリビアにおいて、「国民意識」の形成は容易ではなかった。加えて、サハラの遊牧民の子であり、アラブ民族主義の代表格である故ガマール・アブドゥル=ナーセル(Jamal ‘Abd al-Nasir)エジプト大統領の影響を強く受けたカッザーフィーには、植民地列強により画された国境を揚棄しようという志向がきわめて強く、権力獲得当初からアラブ統一をめざして近隣アラブ諸国との合邦を繰り返し模索した。一方でサハラ・サヘル地域をはじめとするサハラ以南アフリカの情勢にも積極的に関与・干渉し、1990年代にアラブ諸国の内部分裂やパレスチナ問題での後退に失望を深め、アラブ統一の展望に見切りをつけると、急激にアフリカ統一論へと傾斜した。そのような彼に「リビア人意識」を積極的に育もうという意識は薄かったのである。
「市民社会」の育成を阻んだ独立リビアの歴史
このような「国家」の枠組みの脆弱性をさらに助長したのは、いかなる形であれ立憲共和制度を一度も経験しなかったという、きわめて特異な歴史である。
独立当初のリビアは立憲君主制を採用したが、権力は国王に集中され、政党活動も禁止されていた。1969年のクーデタ後に国名は「リビア・アラブ共和国」と改称されたが、あくまでも軍政であって共和制の実態はなく、軍政の翼賛団体として設立されたアラブ社会主義者同盟(ASU)以外の政治結社は禁止された。
やがてカッザーフィーは極めて特異な政治思想を掲げるようになる。彼は著書『緑の書』の中で、代議制民主主義、政党政治、階級独裁のすべてを特定の「代表」や集団による独裁であるとして否定、多数決原理すらも「少数者に対する独裁の強要」としてしりぞけた。そして最底辺の基礎人民会議から全国人民会議に至る人民会議を組織し、全人民が基礎人民会議に参加して合議・合意により政治的意思決定を行う「人民直接民主制」によってのみ、真の民主主義が実現されると主張したのである(2)。人民会議の設立は1977年の「人民権力確立宣言」以降本格化され、RCCやASUは解散、国名も「社会主義人民リビア・アラブ・ジャマーヒーリーヤ」に改称された。「ジャマーヒーリーヤ」とは「大衆の共同体」を意味するカッザーフィーの造語である。1979年にはカッザーフィーがすべての公職を辞任、リビアは彼の観念によれば、「国家元首も首相、政府も存在しない」世界でただ一つ真の民主主義が実現された理想社会となったのである。
しかし、「ジャマーヒーリーヤ」の非現実性は自明であり、表向きには「偉大なる9月1日革命の指導者」という称号のみ有する「一市民」となったはずのカッザーフィーが、公的地位にないがゆえに任期・権限など一切の法的制約を受けることなく、『緑の書』にのっとり全人民の意思を「革命的」な方向にまとめる絶対的権威者として君臨することになった。たとえるなら、それは「第一市民」アウグストゥスが事実上の「皇帝」として支配した前期ローマ帝政(元首政)に類するものであった。政党や政治結社が否定され、「反革命的」な言動がカッザーフィーに直属する「革命委員会」によって厳しく統制されているという実情の中では、人民会議に真の意味での民主的議論は存在しえなかった。リビア人は市民としての自発的な行動・思考・組織化の機会を奪われ、法治主義にも無縁な「群衆」として長い年月を送ることになったのである。
結果としてリビアは、カッザーフィー個人の想念に支配される「私物」の様相を呈していった。人民会議の中では石油収入、対外援助、軍事などの議題は扱われず、カッザーフィーと一握りの取り巻きが直轄していたとされる(3)。発足当初のRCCメンバー12人の過半数は亡命または粛清され、「ジャマーヒーリーヤ」樹立の段階で実質的な「革命指導部」を構成していたのは5名のみであったが、1990年代に入ってナンバー2と目されていた元首相アブデッサラーム・ジャルード(Abdessalam Jalloud)少佐(内戦勃発後に国外脱出し反カッザーフィーの立場を宣言)が失脚すると、次男のカッザーフィー国際慈善基金総裁セイフ・アル=イスラーム(Saif al-‘Islam al-Qaddafi)、五男とされるムアタシム(Al-Mu’tasim Billah al-Qaddafi)国家安全保障顧問、義兄弟のアブドゥッラー・アル=サヌーシー(Abd ullah al-Senussi)軍諜報部長ら、カッザーフィーの一族が体制の中枢を握るようになった。カッザーフィーと最後まで行動を共にし殺害された旧RCCメンバーが国防書記(国防相)のユーニス・ジャービル(Abu-Bakr Yunis Jabr)少将ただ一人であった事実こそ、「個人王国」化した「ジャマーヒーリーヤ」の実態を象徴するものであった。このように、王政、軍政、そして「ジャマーヒーリーヤ」と続いた独立リビアの歴史は、「市民社会」の育成とはまったく無縁のものだったのである。
「石油の富」の功罪
王制リビアは、イドリース国王が独立前からイギリスと結んでいたこともあって、米英両国に大規模な軍事基地を提供し、1960年代から本格的に開発された原油も欧米企業により採掘されるなど、強度の従属的状況下に置かれた。カッザーフィー政権はかかる従属の打破を掲げ、発足早々に米英の軍事基地を撤収させ、1970年代初頭には石油産業の国有化と原油価格の大幅値上げを実現するなど、欧米列強からの自立と「資源主権」の回復をはかる「第三世界」の旗手として脚光を浴びた。
彼はその後、石油の富を活用して、教育や社会保障の整備、砂漠地帯の地下水をパイプラインで輸送し農業開発に活用する「大人工河川」プロジェクトに代表されるインフラ整備などを積極的に推進した。この結果、王政時代に世界最貧国のひとつであったリビアは、一人当たり国内総生産が1万ドルを超え、アフリカ最高の人間開発指数(HDI)を誇る豊かな国へと発展した。例えば大学レベルの教育機関は2,000カ所を超えるまでに激増し、高等教育まで無償化されたばかりか、学生に一定の給与まで支給される制度によって、リビア人の大学進学率は70%を超えるという、世界有数のレベルに達した(4)。
その意味で、リビア人はエジプトやチュニジアのような極端な貧富の格差に苦しんでいるわけではない。むしろ彼らはホワイトカラー志向が強く、150-250万人ともいわれるサハラ以南アフリカ諸国など外国人の出稼ぎ労働力に肉体労働や非熟練労働を委ねてきた。リビア人の経済活動人口はすでに1970年代末期の段階で20%と極端に低くなっており、その「失業率」も実態は「未就業率」であるとの指摘さえ見られるほどである(5)。かかる状況はリビア人の「市民」としての成熟をさらに阻んだばかりか、40年を超える啓蒙主義的な革命体制がもたらした「自由なき豊かさ」の中で将来の展望を描けない閉塞感を、アフリカ人移民に対する日常的な差別へと転嫁する悪弊を生み出した(6)。
カッザーフィーの支配下でリビアが大きく発展したことは事実である。しかし、発展も「ジャマーヒーリーヤ」も啓蒙的革命指導者による「恩恵」として大衆にあてがうという独善的姿勢は、総人口の85%がカッザーフィー時代以前のリビアを知らない40歳未満になったいま(7)、完全に民衆から遊離していた。そのことを理解できないカッザーフィーは、(独立リビア史上カッザーフィー時代を否定する唯一のシンボルである)王政時代の国旗を掲げ決起した民衆を、自らが実現した「豊かで自立した人民主権の理想郷」の破壊を企む「反革命」勢力と見なし、熾烈な暴力で応じたのである。かたや市民として未成熟なリビア人は簡単に外国軍の空爆を頼んだばかりか、アフリカ人移民へのゼノフォビアを高め、無関係な者にまで「傭兵」の嫌疑をかけ虐待・虐殺したのであった(8)。
欧米諸国によるリビア軍事介入の意味するもの
以上のような背景のもとに勃発したリビア内戦に、NATOとアラブ君主制諸国(カタール、ヨルダン、アラブ首長国連邦)の同盟軍は空爆、特殊部隊派遣、物資補給などの軍事介入を実行した。それは、リビア情勢に関して2011年3月17日に採択された「国連安全保障理事会決議1973」が規定した「市民保護」の域を踏み越え、明らかに体制打倒を目的としていた。また、同盟軍参加国の中に、旧宗主国イタリア、第二次大戦後の占領国である仏英両国、軍事基地を保有した米国がすべて含まれているという事実は、この軍事介入がもつ支配主義的な本質を示している。
なかでもフランスは、2011年3月に反体制派の暫定国民評議会を世界で初めて正統政府として承認するなど、カッザーフィー体制打倒に最も前のめりの姿勢を見せた。むろん、その理由が「人権と民主主義の擁護に積極的であるから」ではないことを、フランスのアフリカ関与の歴史を知るアフリカニストなら、ただちに理解できるだろう。同じ北アフリカのモロッコ王国による、1975年以来35年以上にわたる西サハラ占領支配を最も積極的に後援し続けているのもフランスであるという事実は、強調に値する。
サハラの遊牧民出身であるカッザーフィーは1970~80年代にかけ、サハラ・サヘル地域における「革新的」「イスラーム的」政権や「革命運動」(反政府勢力)を精力的に支援し、西側諸国やアフリカの親欧米政権との激しい対立を引き起こした。チャド北部の「アラブ系」民族集団を基盤とするチャド国民解放戦線(FROLINAT)を1970年代から支援し、1980年代に大規模な軍事介入を実行したことはその代表例である。同地域に限らず、植民地解放運動からリベリア国民愛国戦線(NPFL)のような悪質な勢力に至るまでアフリカ各地の武装勢力を支援し、国内の軍事キャンプで訓練したことが知られている(9)。今回の内戦時にも、スーダン・ダールフール地方の正義平等運動(JEM)や、マリなどのトゥアレグ人武装勢力がリビアを脱出した(10)。このような事実が、「アフリカ人傭兵」問題を指摘される遠因となったことは確かである。
しかし、米国による1986年の空爆、1990年代の国連安保理決議による経済制裁など厳しい圧力に直面すると、カッザーフィー政権はオイルマネーによる経済援助や投資という「ソフト・パワー」によってアフリカへの影響力を拡大する方針に転じた。その結果、かつてアフリカの多くの政府から敵視され、1982年にはトリポリでのアフリカ統一機構(OAU)首脳会議を多数の国のボイコットにより流会させられる憂き目さえ見たカッザーフィーが、2009年にはアフリカ連合(AU)の議長に就任するに至ったのである(11)。
そうした外交的成果を象徴するのが、カッザーフィー自身の提唱により1998年に創設されたサヘル・サハラ諸国共同体(CEN-SAD)である。リビアの首都トリポリに本部を置くこの機関は、サヘル・サハラ投資商業銀行による投資や加盟国民のリビア入国ビザ免除などをテコとして、創立当初の6ヵ国から、アフリカ大陸の北半分をほぼ包摂する28カ国にまで拡大した(12)。サハラ・サヘル地域の大部分は旧フランス植民地・信託統治領であり、「フランス語圏」の中心である。CEN-SAD加盟国の過半数は「フランス語圏」の国なのである。同じころからフランスの影響力は、駐留仏軍の約8,000人から5,000人への大幅削減、およびフランスのユーロ加入にともなう「フラン圏」の先行き不透明感の強まりにより低下傾向にあった。CEN-SADの拡大は、フランスの覇権がカッザーフィーにより崩されつつあることの象徴だったのである。
フランスのリビア内戦への積極的介入の動機が、その覇権を脅かすカッザーフィー体制を打倒するとともに、暫定国民評議会に恩を売り、「カッザーフィー後」のリビアの石油利権に対する優先的アクセスを確保することであるのは明らかであった。
アラブとアフリカの対比の倒錯
一方、アラブ君主制諸国がリビアの反カッザーフィー勢力を積極的に支援した理由としては、君主制諸国に極めて批判的だったカッザーフィーに対する積年の嫌悪感もさることながら、リビア内戦と同時期に発生していたバーレーン民主化運動への弾圧から世界の目をそらし、民衆主体の民主化の流れを体制側からコントロールしようとする意図があったと考えられる。これら諸国の主導のもと、アラブ連盟は2011年3月12日、リビア上空に飛行禁止空域を設定するよう国連安保理に求める決議を採択し、3月17日の「安保理決議1973」採択への道筋を敷いたのである。AUが3月10 日の平和・安全保障理事会で外国の軍事介入を批判し、首脳級の特別高級委員会を設置して調停工作に乗り出そうとした矢先の決議であった。ちなみに、アラビア半島の君主制諸国から構成される湾岸協力評議会(GCC)の合同軍が、多数派シーア派信徒を中心とする民主化運動を粉砕するためバーレーンに軍事介入したのは3月14日である。カタール首長家の強い影響下にあるアル=ジャズィーラなどの報道や安保理協議を通じてリビアの悲惨な戦闘に世界の耳目を引き付けることにより、専制君主たちはバーレーンでの弾圧を覆い隠し、あたかも「民主化運動の味方」であるかのように振る舞ったのである。
他方、「アフリカ人傭兵」説、あるいはアフリカが「独裁者カッザーフィーに好意的」であるとの言説によって、AUの調停の信頼性はおとしめられた。しかし無視してはならないのは、1990年代以降のアフリカで民主化が(少なくとも外形的には)紆余曲折を経つつも着実な前進を遂げ、専制君主国をはじめとする独裁的体制に覆いつくされた西アジアのアラブ諸国よりはるかに先行していたという事実である(13)。「北アフリカ革命」は、アフリカからアラブへ民主化の波をつなぐ動きと評価することもできるのである。AUにとって、アフリカ諸国移民が直面する苦境や、リビアがAU予算の15%を分担する5大国のひとつであることを考慮すれば、一方の当事者への支持を明確にすることなく平和的な紛争解決をめざす以外に選択の余地はなかった。
つまり、アラブ連盟がAUより民主化に前向きであるかのように描く言説・報道は明らかに倒錯しており、「民主化」を振りかざして軍事介入したアラブ君主制諸国の真の意図から世界の眼をそらすことに寄与するものでしかなかったのである。
暫定国民評議会にリビア代表権を認めた2011年9月の国連総会での投票において、多数のアフリカ諸国が反対(12カ国)・棄権(5カ国)・欠席(17カ国)したのは、AUの調停努力を無視した欧米およびアラブ諸国の姿勢、および暫定国民評議会側の民兵による激しいアフリカ人移民迫害に対する、アフリカの強い不快感を表すものであった(14)。
むすびに代えて
これまでに論じてきたように、リビアは特有の歴史的・政治的・経済的背景から、国家としても市民としても未成熟なままに置かれていた。それがNATOやアラブ君主制諸国による軍事介入を呼び込み、性急な体制打倒によって無秩序へと転化しつつある。元法務書記(法相)のムスタファー・アブドゥルジャリール(Mustafa Abd al-Jalil)議長のような体制離脱者から、人権活動家、政治囚、イスラーム主義者に至るさまざまな勢力の寄せ集めである暫定国民評議会は各地の武装勢力を統制できず、イドリース元国王の親族アフメッド・アル=サヌーシー(Ahmed Al-Zubair al-Senussi)率いるキレナイカの勢力が2012年3月に自治を求める宣言を発するなど(15)、リビアは「破綻国家」化の危機に直面している。さらに同月には、過去20年間民主的な体制を続けてきたマリで、リビアを脱出したトゥアレグ人武装勢力を吸収し蜂起したアザワド解放国民運動(MNLA)への対応に対する不満を原因とする軍部のクーデタが発生した。リビアの混乱はサハラ・サヘル地域全体の不安定要因となりつつある。
「北アフリカ革命」はもちろん、アフリカの民主化の営み全般にも影を落とす。リビアに対する支配主義的な軍事介入の本質と意味を見極めることができなかった先進諸国の知識人や市民社会の責任は大きいと、結論せざるをえない。
(1)宮治一雄『アフリカ現代史Ⅴ 北アフリカ』山川出版社、1978年、pp.136-139。1949年3月にはイドリースを首長とする「キレナイカ首長国」が宣言されている。
(2)『緑の書』の邦訳版(アラブ現代史研究者の藤田進による訳)が1980年に第三書館から出版されているので、参照されたい。
(3)『ジャマヒリア?革命の国リビアの実像』中東調査会、1981年、pp.124-125。本書は「ジャマーヒーリーヤ」の理念と実際に関する包括的な分析として極めて有用である。
(4)塩尻和子『リビアを知るための60章』明石書店、2006年、pp.247-248。『ジャマヒリア』、p.227。
(5)『ジャマヒリア』、pp.229-235。塩尻[2006]、第38章。
(6)リビアにおけるアフリカ人移民労働者の状況の一端を紹介するものとして、塩尻[2006]、第39-41章を参照。
(7)2005年の推計。塩尻[2006]、p.204。
(8)2011年9月にアムネスティ・インターナショナルが発表したレポートThe Battle for Libya: Killings, Disappearances, and Tortureは、反体制勢力によるアフリカ人労働者虐殺・虐待について多数の証言を収めている。カッザーフィー側による虐待にも言及しているが、いわゆる「アフリカ人傭兵」説には「根拠がない」と明記している。
(9)リビアのアフリカに対する関与・介入については国外で多数の文献が発表されている。特に以下の文献はやや古いが、包括的で有用性が高い。Rene Lemarchand (ed.) The Green and The Black: Qadhafi’s Policies in Africa, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1988.
(10) “Darfur rebel leader Khalil Ibrahim flees Libya”, BBC news, 12 September 2011【http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14881745】;
Andrew Harding, “Sand and fury: Mali’s Tuareg rebels”, BBC News, 13 March 2012
【http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17357122】
(11)ただし、この事実を過大評価することは禁物である。彼の議長就任は下位地域間での輪番原則と、北アフリカの他の元首がすでにOAUの議長を務めていたことによるところが大きい。在任中、彼が唱導したAU機関強化の構想などに実質的な進展は見られなかった。
(12)CEN-SADの概要や活動については、同機構のウェブサイトに詳しい【www.cen-sad.org】。ただし内戦勃発後、同サイトはほぼアクセス不能となっている。
(13)詳しくは、拙稿「北アフリカ革命―その歴史的意義と試練」『前衛』879号、2012年2月、pp.111-123を参照のこと。付け加えるなら、GCCのバーレーン軍事介入およびモロッコの西サハラ軍事占領をともに容認するアラブ連盟と、西サハラの亡命政府サハラ・アラブ民主共和国を国家として認めるAUのどちらが人民の民主的権利に前向きだと言えるだろうか。GCCは現在モロッコの加盟申請の検討を進めている。
(14)国連プレスリリースGA/11137,16 September 2011
https://www.un.org/press/en/2011/ga11137.doc.htm
(15)“Libya: Semi-autonomy declared by leaders in east”, BBC News, 6 March 2012【http://www.bbc.co.uk/news/world-afrtica-17271431】