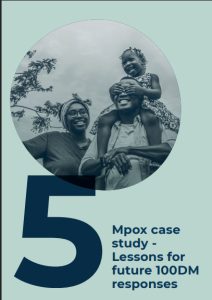Meet and talk with people with disabilities in Tanzania
アフリカNOW No.93(2012年1月31日発行)掲載
執筆:桑原知広
くわばら ともひろ:1985年生。鳥取大学卒業後、九州大学大学院農業資源経済学部門修了。2009年国際協力機構(JICA)入構。現在、人間開発部社会保障課にて障がい者支援分野の技術協力プロジェクトの実施モニタリングや評価などを担当。東日本大震災後、友人と「みちのく応援隊」を結成。南相馬市への物資供給など、現地のニーズに合わせた活動を展開している。
2011年9月12日、乾いた大地にまぶしいほどの陽光がさんさんと照りつける中、一台のバスがタンザニアの玄関、ダルエスサラーム(Dar es Salaam)空港を飛び出した。「利光徹とアフリカを歩きたい!」ツアーグループの珍道中の始まりである。乗車しているのは老若男女計12人と折りたたまれた車いす1台。日本人の集団は珍しいのか、沿道の歩行者や並走する車の窓から好奇の目とさわやかな笑顔が飛んでくる。このレポートでは、利光徹さん(55)(以下、徹さん)と彼に吸い寄せられるようにして集まった11人の愉快な仲間たちの、笑いあり、出会いあり、涙あり(?)の11日間にわたるタンザニアの旅を報告する。この旅は、ツアーのタイトルにも名前が入っている徹さんが10年間夢描いた末に実現したものであるので、報告の前段として、主人公である徹さんの紹介から始めたい。
徹さんと行動すると新しい発見がたくさん
私の場合、福岡で大学院生をしていたころ利光さん一家に出会った。徹さんと一緒に行動すると新たな発見があっておもしろい。実は車いすで簡単にエスカレーターに乗れてしまう事実とか、「手伝っていただけませんか」と見知らぬ人に車いすを持ち上げることをお願いすると結構な確率で手伝ってくれることとか、家で一緒に風呂に入ったときは満面の笑みで「あー幸せ!」なんて不意にこぼされ、当たり前のように送っている日常のありがたさに気づかされたりとか、人の意識の根底にある差別意識に遭遇する瞬間だったり。
二人で鹿児島を旅行したときのこと。「次の車両はノンステップですので、そちらに乗ってください」と路面電車の運転手。僕らはこの電車に乗らないと福岡行の高速バスに乗り遅れてしまうという状況なのに、車いすに乗っているというだけでなぜ当然のように乗車を見送るよう言われるのか。理不尽だ。事情を説明し、手を貸してもらうようお願いしたところ、その運転手は表情や態度に不快感を露わにしながら、片手で車いすを持ちあげた。車いすは宙でバランスを崩し、落下するかもしれない危険な乗車だった。こういう態度は本当にいい加減にしてほしいが、社会に潜む闇がかいま見えるようでやっぱりおもしろい。
介助者=友だち
徹さんは口で生きているような人である。食事、入浴、移動、トイレと生活のあらゆる場面で介助を必要とする。生後間もなく、高熱により脳性マヒ者となった。20代のころ親元を離れ、現在は福岡市東区の公営住宅で妻、息子と3人で生活している。公的な介助サービスは極力利用しないようにして、介助は友人に頼むというのが長年彼の貫いてきたスタイルだ。そのスタイルは、彼が所属しているグループの先人たちが開拓し、実践してきた自立生活運動の原点でもある。電話を駆使して友人に連絡を取り、1ヵ月先の介助のスケジューリングをする毎日。来る日も来る日も24時間友人が介助に入ってくれるわけではないから、3食満足に食事をとれる日は少ないし、お風呂だって、夏場でも1週間入れないようなこともある。
この部分を話すとだいたい「なんでそこまでして…。私はそんな生活はいや」という反応が返ってくるし、自分自身が仮に徹さんのような障がいをもったとして、同じような生活スタイルをとるかどうかはちょっと考えてしまうが(というか能力的に多分できないが)、友人としての立場からいえることは、こういう関係は心地いい。徹さんは常に介助者の目を見て話をするし、頼みごとは介助者を気遣いながらする。その日にどうしてもシャワーを浴びたくても、もし介助に入っている友人の体調が悪そうだったり、帰らなければならない用事があったりすれば、そちらを優先して家に帰す。家で火を使っても、徹さんを一人家に残して買い物に出ても、酒を飲んでも、誰にもとがめられることはなく自由だ。
少し話がそれてしまったが、おそらくその生活スタイルを軸にした生き方や考え方が広い交友関係と信頼関係を形成し、周囲の共感を得て今回の旅の実現へとつながったのではないかと思う。みな私と同じように、頼まれたから行くのではなく、「行きたい」という自らの意思をもった人が集まっている。むろん旅費はおのおの自腹である。同行者が一人や二人であれば少人数に介助の負担がのしかかるため、修行のような厳しい旅になるが(それもまたおもしろいか)、今回は10人も集まったからまったく心配なしだ。さあ、タンザニアへ行こう。
タンザニアの障がい者と出会う旅へ
タンザニアを旅するといっても、ただ観光するのではおもしろくないだろうということで、これは徹さんの強い希望でもあったが、「障がい者に出会う」ことを一つの共通テーマとして旅程を組んだ。旅のコーディネートを引き受けてくださったのは、『タンザニアに生きる-内側から照らす国家と民衆の記録』(昭和堂、2011年)の著者で、インド洋史学徒の根本利通さんと、『星降る夜は緑の匂い-タンザニアで暮らす』(ゲンタデザイン、2005年)の著者の金山麻美さん(ご夫婦で「ジャタツアーズ」という旅行会社を経営されている)。お二人を紹介してくれたのは、お二人と一緒に日本で反アパルトヘイト運動にかかわってこられた楠原彰さん(國學院大学名誉教授、教育学)。楠原さんには全日程同行していただいたので、タンザニアを歩くにはこれ以上ない最高の布陣である。
さてダルエスサラームに到着したバスはその翌日、内陸部の西へ向かって走行した。彼方に見えるバオバブの木に興奮したりしながら、サバンナの景色を数時間眺めていると、広大なサイザル麻のプランテーションが眼前に広がった。目的地は近いようだ。ここはダルエスサラームから約170km離れたキンゴルウィラ(Kingolwira)村。人口約1万人、戸数約3,000戸の大きな村である。ジャタツアーズのタンザニア人スタッフの一人であるグビ(Ngubi)さんが生まれ育った場所で、もう20年以上前から日本人旅行者を案内しているそうだ。ここで3日間ほどお世話になることになった。
人懐っこい村の子どもたち
到着するとさっそく村の子どもたちが集まってきた。「イェーッサイェッサイェッサ、イェーッサ!」という掛け声に合わせて、手をつないで作った円を回しながら飛んだり跳ねたりしているメンバー(キンゴルウィラ村の遊びらしい)、「だーるまさんが…ころんだ!」と日本の遊びを教え込むメンバー、牛飼いの少年について行ってしまうメンバーと、みな子どもたちと思い思いの時間を過ごしている。
子どもたちは、車いすのおじさんには最初は警戒した様子だったが、おじさんが得意のウィリー(前輪を上げて走るとかなりスピードが出る)で追いかけてみると「ギャー!」と喜んで、みなおもしろがって車いすのハンドルを我先にと握っていた。この村の子どもたちは無邪気で人懐っこくて本当にかわいい。
手こぎ車いすの靴職人に出会う
村に障がい者がいるということで、グビさんの弟さんの紹介で、隣の集落で靴の修理の仕事をしているという人に会いにバスを走らせた。迎えてくれたのはボニ(Boni)さん(55)。さびついた手こぎ車いすにさっと乗り込み、テーブルとイスが並ぶ野外レストランへ車いすで先導する。地上とレストランには30cmくらいの段差があり、ボニさんはそれを自力ではい上がるのだが、その様子を静観している村の人の態度が少し気になった。こうしてなんでもできることは自分でやっているのだろうか。
みなが席に着くと、金山さんがスワヒリ語の通訳をかって出てくださり、徹さんとBONIさんの対談が始まった。私たちの一行から徹さんが代表して、タンザニアで障がい者がどういった生活をしているのかを学びにきたという訪問目的を説明する。それを受け、ボニさんがご自身の生活を語り始めた。
生後間もなくポリオになり、足に力が入らなくなった。両親はなぜかわからずケンカ。おじさんが彼を病院に連れて行った。母親は亡くなり、いまは父親と二人で暮らしている。靴の修理をしているが、ときどき材料を買うお金がなくなり、物乞いみたいにしてお金を得ることもある。村の行政機関は、公的には「障がい者を大事にしよう」と言っているが、実際に役所に行ってみると、そんなことは知らないという態度をとられるのだという。
一変した空気
ボニさんの口から語られる現実は厳しいものだが、お互い質問に応え合っていたから、それなりになごやかな雰囲気で対話が進んでいた。しかし、彼が「もし自分が日本で勉強したいと思ったら、みなさんが私を連れて行ってくれますか」などと、こちらに援助を要求し始めたから、その場の空気は一変。苦しい、困っていると説明された上で援助を要求されると、押し黙っている自分が何だか悪いことをしているような気分になってくる。
ボニさんの要求は徹さんだけではなく、私たち全員に対してのものだったが、回答はみな徹さんにまかせっきりで、自分を含め若手メンバーは傍観者と化していた。「今ここで連れていけるということは、僕は正直言いきれません。連れて行きたいという願望は持っていますが、申し訳ないです」。徹さんの苦しい回答が続く。
そんな私たちの無責任な態度を見かねてか、楠原さんと徹さん以外のメンバーの間では年長の山岡信幸さん(予備校カリスマ地理講師兼進学塾講師。ツアーグループのキャプテン)が鋭く指摘する。「みんなはどう考えているのか」。山岡さんの言葉にハッとさせられ、自分の考えを急いで整理してみる。
私が出した結論は、「初対面でボニさんのことをよく知らない今の段階で援助はできない」。10万シリング(約7,000円)という額を要求されていたが、じゃあ仮に同金額を渡したとして、ボニさんにとってそのお金がどういう意味を持つのかわからない。みなで出し合えば高い金額ではないが、要求されているお金は出すべきではないと考えた。
若手メンバーの回答は、およそ似たようなところに落ち着いたので、要求されている額は渡さないことになった。ただし、貴重な時間をいただいてお話を聞かせていただいたから、お礼の気持ちとしてメンバーがそれぞれおもいおもいに志をだしあい、後日それを集めて謝礼として、グビさんの弟さんを通してお渡しすることにした。
さて徹さんがボニさんに伝えようとされていたのは、「障がい者同士が手を取り合って、団体で行政に掛け合うこと」だった。行政に働きかけて何かを変えていくには、長い長い道のりになるだろうが、恒常的な生活水準の向上のためには、私たちのような外部者に依存しようとするのではなく、まずはキンゴルウィラ村という地域で障がい者同士手を取り合うことが必要ではないかと感じた。徹さんが福岡という地域で実践してきたように。
ダルエスサラーム路上での偶然の出会い
旅の後半、徹さんの提案でダルエスサラーム市内をしばらく歩いてみることにした。その間の距離約6キロ。空が赤く染まりつつある中、中心街へ伸びる幹線道路には、市外に向かう車が長い列を作っている。赤信号に足を止めると、すぐ隣で車いすの人が静かに車の列へ視線を送っているのに気が付いた。周りに目をやると、交差点に障がい者のものとおぼしき複数の手こぎ車いすが視界に入る。指がない歩行者も一人。グループで物乞いをしているのだろうか。興味があったので道を尋ねてみた。
彼の名前はジュマ(Juma)、37歳。ケニア国境にほど近い北部の港湾都市タンガ(Tanga)出身。5歳の時にポリオになった。流ちょうな英語を話すので、どこで勉強したのかを尋ねてみると、小学校で7年間勉強し路上での会話経験を積むことで上達したのだという。徹さんの存在が気になっている様子で、周りの車いすも集まってきた。ジュマさんはこちらの質問に答えつつ、逆に質問を返してくる。
「日本では政府による支援がありますか。医療費の支援はありますか」。「僕たちみたいに仕事ができない障がい者に対しては、最低限の生活を保障するためのお金が毎月支給されます。日本には健康保険があり、病院費用の3割を個人が負担します。ただし、障がい者の場合は、そのほとんどは自治体で払うため、自分で払うのは1割程度です」。「タンザニアには何の保障もありません」。通訳にも熱が入る。
物乞いという仕事
政府から何の保障を受けていない状態で、いったいどうやって暮らしているのかというと、こうして路上で現金や衣類、食料などを道行く人に求めることで生計を立てているということになるだろう。いわゆる物乞いであるが、彼らから卑しさはみじんも感じられなくて、むしろ堂々としており、「物乞いが仕事です」と言わんばかりにどこか開き直っている。明るささえ感じられる。
日本ではちょっと考えられない姿だが、乗っている手こぎ車いすは実際、路上で出会った人から寄付されたものであるというし、現にこうして生活ができているわけだから、タンザニアには物乞いを援助することは特別なことではない雰囲気とか、障がい者にはものを受け取る権利がある! というような権利意識があるのかもしれない。
グループの関係を尋ねたところ、やはりみなで協力して物乞いをしているのだそうだ。時間帯によって場所を変えていて、夕暮れ時はここにきているというから、車の交通量や他グループの縄張りなど勘案し、戦略的に配置スケジュールを組んでいるということか。メンバーは仕事だけでなく生活も共にしていて、そこから約1時間の場所にある部屋を2万シリング(約1,400円)で借りて共同生活をしている。住所を登録するお金もないのだという。経済的に苦しい生活を強いられていることはまず間違いなさそうだが、ときどきみなでサッカー観戦に行ったりもしているということで(サッカー場への入場は無料だそうだ)、苦しい生活の中にも楽しみはあるようだ。
そして議論は人と人との関係性へ
「あなたたちはどういう関係ですか」とジュマさん。「友人です。私が学生のころ知り合いました」と答えると、「それはいいですね。タンザニアには、障がい者と親しい関係を作ろうとしない人がいます。それは家族も同じです」と、何だかうらやましそう。「それは日本も同じです。どこでも同じだと思います」とすかさず徹さん。すると「なぜ日本では障がい者と友だちになろうとしない人が多いのですか」と今度はダルビッシュの剛速球みたいなのが飛んできた。これには徹さんもさすがに困った様子で苦笑しながら、「なんでしょうね?」とひとしきり考えた末、「日本の場合、子どものころから分かれた生活をしているから、障がい者に接する機会がまったくない人が多いのです」と静かに打ち返した。
このとき徹さんは自分の話をされなかったが、徹さん自身、小学校すら満足に6年間通っていない。普通学校に行きたくても行かせてもらえなかったという経験を知っていたから、このことを伝えると、「タンザニアの小学校では障がい者も一緒に勉強しています。そこは障がい者も健常者も同じなんですよ。タンガにいる小学校時代の友人とは今もつながりがあって、帰るときには会ったりするし、今もときどき電話したりします」と少し誇らしげだ。徹さんのような重度障がい者もJUMAさんらと同じように小学校で一緒に勉強しているとは思えなかったが、今度は徹さんの方が、どこかうらやましそうだった。
お金や物を要求することはなかったJUMAさん。それどころか、「日本のことが少しわかった。タンザニアのことも知ってくださってありがとう」とお礼を言われてしまった。ひょっとすると商売の客ではなく、友人として接してくれたのかもしれない。お互いにタンザニアと日本のことを分かち合うことができたことが確認できる、うれしい一言だった。JUMAさんには貴重な営業時間をさいてもらったし、こちらからの質問に真摯に答えていただいた。グループのみなさんでおいしいものでも食べていただきたいと思い、お礼にいくらか渡してその場を後にした。
読者の皆さんには、この旅や徹さんという人がどのよう写ったでしょうか。もし少しでも魅力を感じていただけたのなら、筆者にとってこれ以上の喜びはない。徹さんと歩くと、「あなたは奉仕の心を持っている」とか言われることがある。そうじゃなくて、自分の中にあるのはいつも、新たな世界・人との出会いと興奮であり、人生を豊かにしてくれる何かがそこにある。5年後は中南米へ? おもしろそうだから、お供しましょう。