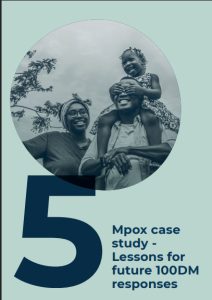教育開発:今日の現状と挑戦ー山田肖子著『国際協力と学校』をめぐる討論
Education development: Current situation and challenges
Discussions about “International Cooperation and Schooling” authored by YAMADA Shoko
『アフリカNOW』90号(2011年1月31日発行)掲載
発言:山田 肖子/質問:李 ハオ
やまだ しょうこ:名古屋大学大学院国際開発研究科准教授。専門は比較国際教育学、アフリカ研究。早稲田大学法学部卒業後、コーネル大学修士課程、インディアナ大学博士課程修了(Ph.D)。民間財団、国際開発コンサルタント、広島大学、政策研究大学院大学を経て、現在に至る。著書に『国際教育開発論―理論と実践』(共著、有斐閣、2005年)、『アフリカのいまを知ろう』(編著、岩波ジュニア新書、2008年)、『国際協力と学校-アフリカにおけるまなびの現場』(創成社新書、2009年)、など。
リ ハオ:中国河北省生まれ、1998年、小学校6年生のときに大阪の市立小学校へ転入。大阪の府立高校在学時に米国ワシントン州の高校に留学、その後、カナダの高校に転入し卒業。トロント大学卒業後、スイス・ジュネーブの国際関係・開発学院入学。2010年9月より早稲田大学・大学院アジア太平洋研究科で交換留学中(2011年2月まで)。現在は就職活動やインターンをしながら毎日、卒業論文に取り組んでいる。
国際協力と学校-アフリカにおけるまなびの現場
創成社 新書
2009年11月20日 初版発行
縦組、本文230ページ
定価:800円+税
ISBN:978-4-7944-5040-1
2009年11月に出版された山田肖子著『国際協力と学校-アフリカにおけるまなびの現場』は、発展途上国の「教育開発」を就学に関わる既成の処方せんを当てはめるだけの単純な問題と捉えるのでなく、学校に限られないまなびの場・機会に注目することを呼び掛けている。また、自分からかけ離れたアフリカの問題と思わず、日本国内で起きているさまざまな教育実践や議論に関心を払うことで、アフリカの教育についても洞察が深まると示唆している。
本号では、中国・日本・米国・カナダで学んだ経験があり、現在、早稲田大学アジア太平洋研究科でアフリカに注目しながら教育開発について学んでいる李ハオさん(国際関係・開発学院 [Graduate Institute of International and Development Studies] 学生)が、この本を読んで投げかけた質問・質問趣旨と、それに対して著者の山田肖子さんが答えた討論を掲載する。/ 『アフリカNOW』編集部
山田:私が、『国際協力と学校-アフリカにおけるまなびの現場』を執筆したのは、発展途上国の教育開発専門家として、また研究者として、アフリカ社会における学校や教育の意味を、思考錯誤しながら考察してきた思考の途中経過を報告する目的からだった。
多くのサブサハラ・アフリカの国では、いわゆる近代学校教育が制度化され始めてから150年程度しか経っていない。しかし、1990年代以降、教育(つまり就学)はすべての人に与えられるべき権利であり、それを提供するのは国家や親の義務だと説明され、急激に初等教育の就学率が拡大した。そのように急激に学校教育が拡大したアフリカ社会において、学校に行くということは何を意味するのか。家族の仕事を手伝ったり、遊びながら身につけていたことは、学校で学ぶことに劣るのだろうか。近代学校教育制度の有無にかかわらず、社会で生きていくための知識や技術を身につけ、世代間で社会集団の記憶を伝達していくという意味での教育は、さまざまな形で行われているはずである。しかし、学校に行くことを教育の前提とする開発言説の中で、そうした社会に根差したまなびの意味や形は軽視され、子どもが就学しないことは、後進性の現れであるかのようにすら言われる。
私は、以前は開発コンサルタントとして働いていたこともあり、現在も、ときには教育開発を行うプロジェクトなどに自ら関わる。そうした中で、国際的に望ましいと言われる教育開発のアプローチや手法は、時代とともに変遷しつつも、援助依存度の高いアフリカ諸国の教育政策に多大な影響を及ぼすことを目の当たりにしてきた。そのため、私の研究者としての始点は、開発言説や教育行政、プロジェクトでとらえきれない多様な教育のすがたや、それを取り巻く人間関係や社会の諸相、言説のレトリックと現実のギャップを学問分析として提示しようとすることにあったと思う。植民地時代の教育言説分析に始まり、現代の教育政策形成プロセス、教育行財政、学校と周辺コミュニティの関係、学校を含む多様なまなびの場のつながりなど、あちこちつまみ食いをしてきて、まだ研究途上にある。しかし、不完全を承知で、研究書ではなく新書という一般向けの書物に著したのは、開発の中でも特に教育をテーマに研究しようとする若者が少なくない中、「途上国の教育開発=学校教育の普及」という固定概念を打ち破る必要を訴えたかったからでもある。
教育における批判的思考の育成
李:本書の序章において、日本の学生が教科書に書かれたことを正解と見なす傾向があると書いてありますが、どうしてそのような傾向が生じているとお考えでしょうか? 日本の教育は欧米と比べ、生徒に批判的な考え方ではなく、潮流あるいは権威に従うように教えていると思いますか?
私は日本の高校を卒業せずにカナダの高校に転入しました。そこで驚いたことは、高校3年生が長いプレゼンテーションをすることや論文を書くように要求されていたことです。もちろん日本の教育を受けてきた私にとって大きな挑戦でした。文系の授業ばかり選択した私は、すべての科目において2、3篇の小論文を書きました。そのプロセスのなかで自分の意見を論理的に表現すること、主観分析の手法、そして異なる見解を客観的に比較することを習いました。日本の教育システムを大きく変える必要はないと思いますが、学生に発表の場を与えることで、批判的に考えられる人材の育成ができるのではないかと思います。
山田: まず、上記のコメントをした本書の箇所を少し引用したい。
最近は、(筆者が教鞭を取る名古屋大学国際開発研究科のような)大学院に進学してくる学生も、EFA (Education for All = 万人のための教育国際開発目標:筆者注)や援助の動向など、いろいろなことをすでに知っている。(中略)情報が豊富になった分、悩んだり求めたりする前に、教科書的な答えが与えられ、教育開発の正解はこれで、それに対する理由付けはこう、とパターン化して覚えてしまう傾向があるような気がするのである。今、主流とされている教育開発のモデルは、90年代から流行しているもので、普遍的正義とは限らない。(中略)国の事情や特定の状況によってトレンドがあてはまらないこともある。(pp.11-12)
ODA(政府開発援助)が年々、縮小傾向にあるにもかかわらず、教育開発を勉強したいという若者は引きを切らない。大学院の入試にもよく準備してくる。しかし、優秀で吸収力が高いことは、言われたことはとてもよく覚えるが、自分で批判的に考えるということは苦手ということをしばしば意味してしまう。それが、日本の教育制度の問題かという問いに対して安易に答えることは差し控えるが(留学生にも似た傾向はあるので)、人間は、一度思考がパターン化すると、そのパターンを形成している枠組み自体を問い直すことが難しいということと、入試制度がそういう人間を選抜しているということは言えるだろう。
人間は、物事を何かの基準に基づいて類型化することで世の中を系統的に理解しようとするもので、たとえば、血液型や誕生日の星座などで他人の人格や嗜好を想像するというのも、そうすると納得がいく感じがするからだ。教育開発の勉強もそれと似たところがあり、受験勉強で、「EFAを達成し、すべての子どもが教育を受ける権利を達成することが貧困削減の重要な要件である」と学ぶと、EFAをどのぐらい達成したかを基準にして国や社会を類型化し、まだ達成していないところは早く達成できるために介入する必要があると考える。どういう介入が有効かも教科書に例示されているので、何が足りないから何をすればいい、というのは、○×式に答えが出てくるような気がしてくる。
こういう思考を持った、処理能力の高い人は、決められたことを忠実に実行する業務にはとても向いている。留学生も、文部科学省やJICA(国際協力機構)の奨学金を受けて日本に来る人たちは、政府やNGOなどで、開発の実務に携わっていたというケースが多いので、開発の方程式には結構詳しく、実務能力は高い。しかし、研究者は、「なぜEFAなのか、どういう視点からみた貧困削減なのか」という本質もたまには疑ってみる必要がある。ということで、入試に強く、パターン認識力にたけた学生を疑り深い研究者に仕立て上げるのも、大学院の一つの仕事だと思っている。
教育と人的資本
李:人的資本は国の発展にとってとても重要ですが、不適切な教育内容は効率のよい発展の手助けにならない場合があります。若者の失業率の高さは、途上国や先進国も直面している課題です。教育者はいかに労働市場を分析し、適切なカリキュラムを作ることができるでしょうか?
ニュースで見たところ今年の日本の新卒就職率は60%前後しかなく、大きな社会問題なっています。学生の就職活動の時期も年々早くなり、ある大学教授はカラカラの教室を見つめ「企業の説明会に出席するために授業を欠席する生徒たちを責められない」と述べていました。私の故郷である中国も今は似たような状況にあり、子どもの大学教育に投資することをためらう人々が増える一方です。先生がおっしゃったように、労働市場に必要な人材を育成するための教育制度の見直しが本当に不可欠だと思います。
山田:人的資本とは、学校教育や職業訓練などによって高められる労働者の能力を指す経済学の用語で、金融資本や物的資本などとともに、蓄積されることによって利潤を拡大できる資源と考えられている。途上国の教育開発の議論は、UNESCO(ユネスコ)などが提唱する人権としての教育普及の発想と、世界銀行などが中心になって行う経済学的理由付けが強い影響力を持つ傾向にあるが、人的資本論は、学校教育への公共支出や保護者の負担を経済発展や所得向上のための投資とみなし、その妥当性を裏付ける理論としてしばしば用いられてきた。
ただし、人的資本論は、人的資本が形成される教育プロセスはあまり見ていないため、実際に意図したような人材が養成されるかどうかは別の視点から考えなければならない。カリキュラムが学校外で求められる知識や技術に合っていなければ、学校を卒業しても、知識の中身は社会的妥当性(レレバンス)が低く、活用されないことになる。人的資本論は、就学によって獲得した卒業証書の教育段階(中学、高校、大学など)や教育課程(普通科、職業科など)、教育年数などによって資本の価値を測定するが、それは、能力そのものよりも、学歴によって、労働市場で人の価値が外的に判断され、それによって社会のさまざまな場所に振り分けられるという学校教育の振り分け作用を測定してしまうことになりかねない。
また、学校教育のレレバンスという観点から、近年、特に深刻になってきているのは、中卒者の進路の問題である。初等教育(小学校)、前期中等教育(中学校)は無償義務教育とされ、総就学率100%の目標を達成した途上国も多い。しかし、中学校までの教育の普及に政府や援助機関の資金や注目が集中した半面、後期中等教育にあまり重点を置かれなかったため、中学校を卒業した後の進学機会が非常に限られている。同時に、進学しない中卒者を吸収できる雇用も不足しており、若年失業率が増加している国が少なくない。失業者全体に占める若年失業者の割合は、ウガンダで83%、ジンバブエで68%、ブルキナファソで56%となっている [African Development Indicators 2009: World Bank]。つまり、初等教育に就学するだけでは、雇用につながらず、生計の手段を得られなければ、貧困から脱することができないのである。そこで、ここ2-3年は、初等教育の質的向上、中等教育の拡充とともに、雇用可能な技能形成、特に職業技術教育の必要性が注目されるようになっている。
労働市場の人材需要にあった教育をする必要があるという認識から、近年は、成果主義 [Outcome-based]、あるいは、職能に基づく[Competency-based] 教育と言われる資格認定枠組みを導入する国が増えている。カリキュラム内容を順を追って教え、それを生徒がどのぐらい習得したかをテストし、合格すれば卒業証書を与えるというやり方ではなく、どのような教育プロセスを経て学んだかに関わりなく、どのレベルの技能や知識が身についたかを審査し、資格を付与するという発想である。しかし、こうしたやり方は、カリキュラム開発者だけでなく、学校で実際に教える教師にも、従来慣れ親しんだ教育の考え方を転換し、学校と社会、知識と生活の関係を、個々の学校や学習者の状況に合わせて柔軟に把握し、対応することを求めることになり、教材作成や教師教育など、資金・人材の不足や制度的な負担など、多くの困難を抱えている。
教育開発と貧困削減
李:すべての人に教育を受けさせる必要はあるでしょうか? 貧困削減は教育以外の方法では達成できないでしょうか? 学校をつくることや学校に行かせることが多くの教育開発事業の核心であり、そしてこのような教育を達成すれば経済発展につながり、貧困が削減されるという理論が主流になっています。しかし、もし貧困削減が教育開発の主な目的のひとつであれば、貧困とは何でしょうか? それを考えていない教育開発者や学生が多いという気がします。
私が幼いときに住んだ家にはガスも水もなく、トイレは歩いて5分のところにあり、家電製品もあまりありませんでした。でも食べ物は十分ありましたし、寒さに凍えることもありませんでした。そんな私と私の家族は貧困というカテゴリーに当てはまりますか? 社会が進歩することとは何か、そもそも何のために開発を行うのかを一番初めに議論すべきではないでしょうか。
山田:教育がすべての人の権利だというのは、世界人権宣言にもうたわれている。そして、年長者が年少者に教え、年少者が社会で生きていくための知恵や技術を身につけるというのは、人間社会の最も基本的な活動の一つだろう。しかし、教育を「受けさせる」という表現には、学習者自身でなく、外部者によって「いい教育とは何か」についての答えが用意されていて、それを与えるというトップダウンの発想がかいま見える。国際協力や援助のレトリックに潜むそうした「教化」の姿勢には、注意が必要なのではないか。
「教育=学校に行くこと」と限定するのは、近代学校教育の枠組みに縛られた考え方であるように思う。また、教育を個人の権利とみなす立場は、個人主義を前提とした平等観に基づいている。すべての人が形式的に同じものを同じように与えられなければいけないというのは、家族の中で、適性や性別、生まれ順などによって、学校を経てキャリア形成する子どもと、それ以外の道を経る子どもを作らないということを意味する。この考え方に立つと、学校に行くことは、大人と違う子どもの役割であって、就学させずに仕事をさせるのは、子どもの権利を侵害する「児童労働」として排除されなければならないとも言われる。
しかし、多くのアフリカ社会において、就学と労働は相互排他的な活動ではない。急激に拡大した学校は、午前と午後の二部制で稼働しなければ就学年齢人口をすべて収容しきれないし、学校に行く資金を自力で稼ぐために、学校に行っていない半日は働いている子どもも少なくない。「児童労働」は社会の悪弊で、学校が普及するとそれが廃絶できるといった発想は一面的であり、そのような視点での就学促進は、皆に与えられた権利である就学を行使しないのは、親が教育の意義を理解できず、近代化に乗り遅れているからだとか、学校に行かない子どもは落後者だ、といったコミュニティ・レベルでの非就学者の排除につながるので、注意が必要であろう。
私は、学校に調査に行くと、就学年齢より年上の生徒が、「ずっと学校に行きたかったが、学校に行けなかった。最近、村に学校が出来たのでやっと通えるようになった」と言っていたり、家族の反対や通学途中の誘拐の危険も顧みず、女の子が「学校を続けたい」と必死で通ってきている姿に出会う。そのような学校への強い期待と人々の就学にかける努力を目の当たりにすると、学校教育を提供するために私たちのような外部者でもできることがあるのなら、何とかしたいと思うのである。その一方で、就学によって、自分は親の世代と同じように村に残りたくはない、都会でいい暮らしがしたい、と思う若者が増えることも事実だ。近年、学校に行く若者が急速に増えたことが、都市への人口移動を加速化させ、若年失業率が増える原因になっているとも言えるのである。学校を作ることが、伝統的な家族の在り方や社会構造を変える結果を生んでいる可能性に、教育の専門家はもっと注意を払う必要があるように思う。
学校を作ること、教師を養成すること、カリキュラムを作り、教科書を配布し、学校を運営すること、それらは教育開発の重大な仕事だ。そのために、さまざまな専門知識が必要である。しかし、それは、学校という制度を動かすための専門性であって、学習者が生きていくための知識や技能を身につけるということとは必ずしも一致しない。
「貧困削減は教育以外の方法では達成できないのか」という質問に対しては、そもそも、教育(学校)は、MDGs(ミレニアム開発目標)で、貧困削減のために達成すべき8つの目標のひとつに過ぎず、教育だけでは物質的な意味での貧困削減には直結しないことを指摘しておきたい。アマーティア・センの「ケイパビリティ・アプローチ」に従えば、貧困は財や収入の多寡によってのみ測れるものではなく、人々が自分の置かれた状況を認識し、考え、選択する自由と尊厳を持つことによって克服できるものである。人々が自らを解放し、高めるきっかけとして、読み書きや広い知識を得ることによって自分自身を客観視できる教育の機会は、非常に大きな意味を持つ。学校がそのような「ケイパビリティ」を身につける場になっているかどうかをわれわれは常に検証していく必要があるだろう。
教育の正当性とは
李:教育を受けるのは人権の一環だとUNICEF(ユニセフ)や他の国際機関が掲げています。しかし人権という西洋の思想とは何かを理解しづらい国の人々にとって、教育の正当性は他の方法で立証するほうがよいのではありませんか? それとも、人権として考えるべきでしょうか?
人権についての議論が繰り返し続く中で、それをあたかも当り前のように教育に結びつけることは少し難しいのではないでしょうか。私は、人的資本論のほうが教育の正当性を提唱しやすのではないかと思います。
山田:「教育は人権である」という発想は、西欧の個人主義と国民国家が形成された歴史的背景を共有しない国ではなかなか理解しづらい。人権というのは、それを保証するための行政サービスと、その権利が侵害されたときに介入する法制度や警察権力があって成り立つわけだが、「教育」をそのようなものと位置付けられる国は多くはないかもしれない。アフリカ諸国に「就学=人権」という前提を持ち込むのは難しいことは先に述べた通りである。では、そのようなアフリカ諸国において「教育の正当性を他の方法で立証する」ことができるだろうか。
何かの「正当性」を主張するためには、それが何の目的に照らして正当であるかを設定しなければならない。国家の経済発展のために、教育に投資をすることが正当であり、効果的・効率的な手段である、という考え方が「人的資本論」である。親にとっては、子どもを学校に行かせるために多少費用がかかっても、将来、学校のおかげで高い収入を得られるならば、投資効果は高いことになるし、国にとっては、GDP(国内総生産)の成長率が人的資本蓄積の効果のバロメーターになる。ただし、教育を経済的利益のための投資とだけ見なす「人的資本論」は、まなぶことが持つ多面的な意義を軽視することにもつながり、注意が必要である。もし、ある社会で、教育を行う目的が「貧困削減」であれば、カリキュラム内容に、生活に根差した知識や、簡単な栄養、保健知識を盛り込むなどのカリキュラム改革も必要であろう。また、前述のように、卒業後に仕事につながるような技能の習得が教育の貧困削減効果を増大させるとも考えられる。
教育の効果は、何のために教育を行うかによって評価の方法もまったく違ってくるので、目標設定にあたって、いかに広く人々の意見を集約して、合意を形成するかが重要になるだろう。
教育言語と多文化共生
李:私は日本に来た当初、日本語教室で勉強したことがあります。その当時はありませんでしたが、今では母国語教室というものができて、月に数回、自分の国の言葉で勉強する教室も設けられています。途上国の少数民族の教育は、どちらかというと多数派に同化させるようにデザインしてあります。多文化共生についてどうお考えですか? 貧困削減のためなら文化の単一化を図っても正当化されるのでしょうか?
一つの教育システムが世界共通になることはそれなりのメリットがあると思います。でもそのデメリットとして多様性が失われる恐れもあります。「学ぶこととは何か」を外から押しつけられるよりも、ひとつひとつの文化の中で、その意味や意義を見つめ直す必要があるのではないかと思います。
山田:アフリカで、教育言語の議論は、多くの課題を内包している。植民地支配に対する独立闘争やその後のナショナリズム言説の中では、支配者の言語であるヨーロッパの言語で教育を行うのをやめ、アフリカの言語で学ぶ必要が叫ばれた。ギクユ[Kikuyu, Gikuyu]語で文学を発表したングギ・ワ・ジオンゴ[Ngugi wa Thiong’o]をはじめ、アフリカの言語で表現することを選んだ文学者や活動家にとって、支配者の言葉での教育は、心の支配をも意味したのである。
その一方で、多民族で構成されるアフリカ諸国にとって、国家教育制度を通じて共通の国民意識を醸成し、国家統合を果たすことは、重要な課題であったが、異なる言語を話す国民を統合できる言語は、ヨーロッパ言語以外にはないという場合が少なくなかった。ヨーロッパ言語以外の公用語で教育を行っても、その言語が母語でない人々にとっては、言語を通じた支配や排除を別の形で受けることになってしまう。また、言語学者や教育学者等によって、学習の基盤が形成される初期の頃に母語で学ぶと、その後の学習効果が高いと言われたこともあり、初等教育段階、少なくとも低学年では母語で教育するというのが、アフリカの多くの学校教育に共通する政策である。
しかし、言語が非常にたくさんある国家で、すべての言語の教科書や教材を開発し、それに沿って教員を訓練することは困難であるため、多くの場合は、主要な言語5-10程度に絞って「母語教育」を行っている。つまり、「母語教育」を母語以外で受けている生徒が必ずいる。このような状況では、「母語教育」の議論は、政治的なメッセージとして、アイデンティティ形成や多文化共生、学習効果についての象徴的な意味は持つが、実際の教育現場ではそれほど明確に行われていない可能性が高い。また、苦労して子どもを学校に行かせる親は、家でも使っている言語よりは、就業や商売に有利な公用語や英仏語を学んでほしいと思っている場合も少なくない。
「母語教育」が差別を助長している可能性や、学校教育の親にとっての投資価値を下げている可能性を考慮するならば、教育言語自体が学校という場を通じた多文化共生に貢献しているとは必ずしも言えないことがわかる。むしろ、学校教育を通じて多文化共生を図るのであれば、そのような教育目的に見合ったカリキュラムを組み、生徒のみならず親や地域の人々を学校の諸活動に巻き込んで、学校が民族や言語、社会経済条件の違う人々が共に活動する場になっていく必要があるだろう。