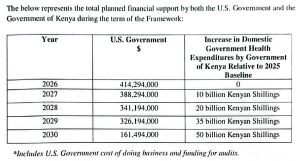~映画『私たちが誇るもの~アフリカ・レディーズ歌劇団』を観て
How are someone’s experiences seen?
– A film “The Baulkham Hills African Ladies Troupe”
『アフリカNOW』109号(2017年12月31日発行)掲載
執筆:茂住 衛
もずみ まもる:AJF理事。『アフリカNOW』編集メンバー。アフリカへの関心の出発点は音楽・映画やイスラームなど。アフリカに長期滞在したことはないが、東西南北の各地域に行ったことがあり、チュニジアのこれからに注目している。
「体験」を「言語化=共有化」する
数ヵ月前に早稲田大学の教員をしているIさんから、全学部の学生を対象とした「体験の言語化」という科目のファシリテーターを担っていると聞いた。この科目の概要について、私はたまたま会話のなかで簡単に聞いただけでしかない。だが翻って考えてみるならば、自らの「体験」を他者にも「共有」してもらおうとすることは、「言語」だけに限らないさまざま方法によって、大学教育のみならず社会のさまざまな場において試みられていることだ。そこでは、自らの「体験」を、言語などの他者にも理解できる方法によって表すだけでなく、自己に個別に起きた出来事の記憶としての「体験」を、その記憶を〈共有〉できない他者とどのように「共有」することができる/できないのかが、まずは問われることになる。
複数の人がある時ある場で同じ出来事に出会ったとしても、それに伴う「体験」は、まずはそれぞれに個別的に立ち上がってくる。しかもその「体験」は、自らの時間のなかで編集され、変化していく。一方で、自己の内部にある記憶としての「体験」を他者に語るという行為は、その語り手がたとえ自らの「体験」が「共有」不能であることを強調したとしても、聞き手の側に何かしら「共有」可能な接点を見いだしたいと思わせるものでもある。自らの「体験」を他者に語ることと他者の「体験」に接することはいずれも、「体験」とその「共有」の間にある緊張関係に気づく契機になる。
映画『私たちが誇るもの~アフリカ・レディーズ歌劇団』
Iさんからの話を聞いた後で私は、その数日前に国連UNHCR難民映画祭2017で観たドキュメンタリー映画『私たちが誇るもの~アフリカ・レディーズ歌劇団』(原題; The Baulkham Hills African Ladies Troupe)(1)を思い出した。この映画が演劇による「体験」の語りとその経過を映像化したものであり、それゆえに、この映画を観た観客に「体験の言語化=共有化」の意味を問いかけるものにもなっていると、改めて気づいたのだ。
この映画は、ギニア、シエラレオネ、エリトリア、ケニアからオーストラリアに難民あるいは移民として移住し、現在はオーストラリアで暮らしている4人の女性、出身国順にヤリー(Yarrie)、アミナータ(Aminata)、ヨルダノス(Yordanos)、ローズマリー(Rosemary)が、オーストラリアで演劇グループに参加したことが契機になっている。この演劇グループの演出家で、映画の監督でもあるロス・ホーリン(Ros Horin)の手引きによって、この4人の女性は、それぞれが出身国での紛争によって、あるいは家族・コミュニティから受けた暴力と性暴力の「体験」を自らが舞台で演じることになった。4人の女性や演出家へのインタビュー、劇作品をつくりだしていく過程、いくつもの劇場での上演の映像、舞台を観た観客の反応などで、このドキュメンタリー映画は構成されている。彼女たちの舞台は、オーストラリア国内で注目され、観客数がより多い劇場での上演を重ねていき、ロンドンの大きな劇場でも上演されるまでになる。
この映画で特に印象に残ることは、自らが出演を了承したにしても、舞台で演じるために自らが被った暴力と性暴力の「体験」の記憶を無理矢理にも思い起こさざるをえない、自らのトラウマ(心的外傷)への葛藤(かっとう)がストレートに描かれていることであろう。実際に、エリトリア出身のヨルダノスは、「自分は何をやっているのだろう」という思いが募り、何度か自分は上演される劇に出演できないと、他の出演者や演出家などに伝える。だが、その後に思い直して、再び出演を了承するという場面も描かれている。
「体験」をツールとしての演劇で表現する
この映画を観ただけでは、劇づくりの過程と上演された作品の内容は、断片的にうかがい知ることしかできない。それでも、出演しているアフリカ出身の4人の女性が、自ら「体験」や出来事を演劇というツールによって社会的に表現していることは明らかだ。
こうした表現の一環として、演劇ワークショップを取り上げることができる。私も経験したことがあるが、演劇ワークショップでは大きな枠組みとして、その手法を通じて、参加者のそれぞれが自らの生活や闘い、出来事などを媒介として、他の参加者との関係を意識し、自ら表現することによるエンパワーメントがめざされていた。そしてこの枠組みが「共有」されることによって、演劇ワークショップの手法は、さまざまな現場で社会化されていったとも言えるだろう。
ツールとしての演劇を活用して、自らの「体験」や出来事、他者との関係などを改めて意識する演劇ワークショップの出発点からすると、その過程を「共有」することこそが重要になる。演劇ワークショップの参加者が相互に学び合うために、他の参加者・グループの演劇表現を観ることは必要になるが、多様な立場の観客を想定した作品としての劇の上演は必ずしも目標とされていない。
だが、演劇ワークショップが固有の「体験」や出来事を出発点として、他の参加者との関係や自己表現の過程を重視したものであっても、その過程を積み重ねていくなかで、自らの作品としての劇をつくり、多様な立場の観客の前で上演したいという欲求は、参加者に当然にも生まれてくる。さらに、ファシリテーターや演出家は、洗練された作品としての劇に仕上げたいと期待する。そして、演劇ワークショップの成果として、多様な観客の前で劇が上演されることも少なくない。固有の「体験」や出来事が出発点となった演劇ワークショップの過程から作品としての劇がつくりだされ上演されたときに、観客の側は、自らの「体験」と出来事を語る出演者との間にどのような位置関係を意識しているのだろうか。
観客という位置を問い返す
この映画の原点には、暴力と性暴力の被害の当事者の「体験」があり、その周りに当事者の劇と映画を演出・制作した関係者がいて、さらには当事者の舞台を観る観客が存在し、その周囲にこの映画を観る観客がいる。
最も外部の観客でしかない私は、まずは、出演者の固有の「体験」を「共有」することの不可能性を自覚せざるをえない。それでもなお、この「体験」を自分の内部にも根拠を持ったものとして「位置づける」ことによって、なんとか「共有」可能な接点を見出そうと摸索する。そのことには、どのような意味があるのだろうか。
アフリカ出身の4人の女性が出演した劇づくりの過程で彼女たちは、自らが被った暴力と性暴力の「体験」の記憶を思い起すことによって、自らがトラウマに直面せざるをえなかったのではないか。彼女たちの事情をよく知らずに、自らの主観で彼女たちの心情を安易に推測することはもちろん避けるべきだ。だが観客は、特に意識しなくても映画や演劇から「体験」や出来事を想像しようする。この映画や劇作品の観客の想像力が「アフリカ」や「女性」という抽象的なフレームのなかに一方的に位置づけられるだけであるならば、ありきたりの感動や共感が語られることにしかならない。この状況は端的に、出演者の「体験」や出来事がいかに語られたとしても、それが観客には「共有」されないことを示しているのではないか。
私は、この映画が上映されることの意義を納得しながらも、映画で描かれた世界に内在する「危うさ」も感じてしまう。それは、当事者ではない演出家が、出演者がトラウマに直面することを自覚していながら、(映画のなかでロス・ホーリンは、前述したヨルダノスの出演辞退に対して、「恐れていたことが起きた」と述べている)「あなたの暴力と性暴力の『体験』を世界の広範な人々にアピールすべきだ」と意図することの「危うさ」であり、その意図を受け取って安易に感動し共感する自分に満足してしまう観客の「危うさ」でもある。この「危うさ」が自覚されないと、出演者それぞれの固有の「体験」と出来事は、観客が自らの感覚や価値観のなかで構成された世界でのみ〈共有〉可能な「現象」にすり替えられてしまう。
この映画が上映された国連UNHCR難民映画祭2017のキャッチコピーは、「観なかったことにできない映画祭」というものだ。映画を観ることによって知った出来事は、どのような記憶として刻まれるのか。「観なかったことにできない」という自覚は、観客としての自らの位置やあり方をどのように問い返すことによって生じてくるのだろうか。冒頭の「体験の言語化=共有化」という視点に立ち戻って考えてみるならば、自らの「体験」を「言語化=共有化」する側の表現能力だけが問われているのではない。むしろ、観客という位置にいる側が、語られた「体験」をどのように受け止めるのかということこそが問い返されているのだ。
(1) この映画の詳細は次のウェブサイト(英語版)を参考。http://africanladiestroupe.com