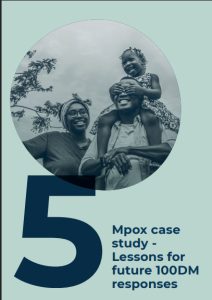On the view of the self in the post-Cold War discourse on development and security
『アフリカNOW』103号(2015年9月30日発行)掲載
執筆:榎本珠良
えのもと たまら:東京大学教養学部総合社会科学科国際関係論卒業、リーズ大学大学院政治・国際関係学科開発学修士課程修了、同大学同学科紛争・開発・安全保障修士課程修了、東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻「人間の安全保障」プログラム博士課程修了。2003年9月から2015年8月まで国際NGO 勤務(勤務時は組織の規則によりペンネームを使用)。2015年9月より明治大学勤務。
はじめに
1980年代以降の国際関係論においては、ネオリアリズムやネオリベラリズムといった「主流」の理論について、国家中心主義や実証主義を前提としていると批判し、「より人間中心」で「全人類的」な国際関係論を目指そうとする動きがみられた。こうした動きのなかで、1990年代には、安全保障研究の分野においても、批判的安全保障研究と呼ばれる研究が盛んになった。そして、初期の批判的安全保障研究の論者は、概して「人間」(ないし個人あるいは人々)の「解放」(emancipation)を安全保障の中心に据えて、国家だけでなくコミュニティや個人も安全保障の対象と見なすべきであると論じ、パワーや秩序ではなく「解放」こそが「真の安全保障」をもたらすのだと主張して、軍事だけでなく経済、環境、社会等の領域にまで安全保障のテーマを拡大することを支持した。また、初期の研究者には、自身の研究における批判を通じて「解放」に向けた変容を導くことを重視するなかで、政策論議に関与しようとする傾向もみられた。
このような研究者および「北」の政府、国際機関、NGO などの政策論議においては、主権国家によって構成されるシステムのなかで国家がいかにして自国の安全を保障するかに焦点を当てる従来の安全保障概念ではなく、人間の「解放」に対する様々な制約を取り払うことを中心に据えた概念としての「人間の安全保障」(human security)が形成されていった。そして、「人間の安全保障」をめぐる政策論議においては、「人間の解放」として再定義された安全保障をめぐる政策論議が、開発に関する論議と相互に接近し、融合した。そうしたなかで、いわゆる平時と紛争時および紛争後に必要とされる取り組みの境界線も曖昧化し、開発や平和構築の全ての段階において、「南」の個人の心・価値観・態度・行動や社会的関係を変化させ、「南」の政府に「適切」な政策を実施する意思や能力を形成させる必要性が謳われた。また、そうした論議のなかでは、「北」の政府、国際機関、NGO などが「南」に介入することが概して正当化され、介入にあたっては内外諸アクターの有機的連携と調整が必要であると論じられた。
このような初期の批判的安全保障研究や、その影響の下に形成された開発と安全保障を融合させた言説(以下、「開発・安全保障言説」)については、その後、批判的安全保障研究の内部において、懐疑ないし批判する論者が登場した。そのような後期の研究のなかには、例えば、1990年代以降の開発・安全保障言説は近代の理性中心主義的な人間像と啓蒙の思考に依拠して近代化と自由化を「トップ・ダウン」の形で国家中心主義的に推し進めることを正当化していると批判したり、「南」において統治の主体を創出しようとする覇権的な秩序の興隆を意味するものであると指摘したり、19世紀末の植民地主義的な「白人の責務」の再来を意味していると論じたりする傾向がみられる。
しかし、このような批判は、この言説の「介入の論理」の表層を額面通りに捉え過ぎいないだろうか。むしろ、着目し説明を試みるべきなのは、一見して遠大な「介入の論理」と、国際合意の文言や個々の施策の実践との間に見うけられる乖離なのではないか。
こんな問題意識に基づいて、批判的安全保障研究のなかに位置付ける形で、博士論文『冷戦終結後の開発・安全保障言説における人間像―小型武器規制・通常兵器移転規制の事例から―』(2014年11月提出・2015年2月学位授与)を執筆した。そして、この論文では、1990年代以降の開発と安全保障をめぐる広範な政策領域のなかでも、小型武器規制・通常兵器移転規制に焦点を当てた。
本稿では、この論文の論旨や構成を詳細に述べるというよりも、筆者がアフリカ政治研究に出会い、北部ウガンダ・アチョリ地域で調査を行い、19世紀末のアフリカ植民地化の時期について考察し、国際NGOでの仕事をめぐって自問した過程のなかで、なぜこのような論文を書くに至ったのかを振り返ることにしたい。
ウガンダ政治から北部ウガンダ・アチョリ地域へ
筆者のアフリカ研究との出会いは、大学卒業が近づいた1990年代末のことだった。遠藤貢先生のアフリカ政治の授業に夢中になり、ウガンダの政治について卒業論文を書き、2つの修士論文も、ウガンダの政治・経済に関連するテーマを選んだ。そして、博士課程の入学試験を受けていた頃、国際刑事裁判所(ICC)がウガンダの事態に関与を開始し、北部ウガンダ紛争下での罪――とりわけ反政府集団「神の抵抗軍」(LRA)の元兵士による罪――に対してICC の「応報的正義」を適用すべきか、アチョリ(北部ウガンダ紛争の被害が集中していた地域の人々)の修復的な「伝統的正義」のメカニズムないし和解と赦しの儀礼を適用すべきか、という論争が沸き起こった。筆者は、このような議論の状況に関心を持ったものの、当時、アチョリの儀礼等の詳細についてインターネットで入手できる情報はわずかだったため、アチョリ地域で調査を行うことにした。
「われわれにはトラウマなどなかった。それは、チェン(cen)なのだ」
筆者は張り切ってアチョリ地域での調査を開始したものの、1ヵ月と経たないうちに、自身の認識枠組みに対して限界を感じることになった。
当時の国際的な政策論議においては、LRA の元メンバー(多くがLRA によって誘拐され兵士や「妻」にされたアチョリの若年層の人々)は「トラウマ」を抱えており、「トラウマ」に起因する問題行動を起こす可能性が高いと考えられていた。さらに、LRA の元メンバー以外のアチョリの人々も、長引く紛争下で自身や家族が被害を受けて「トラウマ」を抱えているために、暴力の連鎖を生み出しかねないと見なされていた。そして、「アチョリの伝統的正義」を支持した外部アクターには、元LRA メンバーや周囲の人々の心理的問題に対処し、元LRA メンバーに対する周囲の人々の受容を促し、社会的関係を再構築し、和解と赦しを促進するものとして「伝統的正義」を捉える傾向があった。
ところが、外部アクターとともに「伝統的正義」を推進する立場にあったアチョリのNGO 職員は、筆者と会って間もない頃は、「伝統的」儀礼を「アチョリの人々の伝統に根差した正義と和解の手法であり、アチョリの人々に受容されるトラウマ・ケアなのだ」と説明していたが、そのうち、「われわれにはトラウマなどなかった。それは、チェン(cen:本人あるいは家族やクランのメンバーが行った禁忌行為ゆえに取り憑いた霊)なのだ」と論じ始めた。同じく外部アクターと協力関係にあったアチョリのNGO 職員も、「伝統的正義のプロセスにおいては、加害者側クランが多くの賠償を行う課程で辛い目にあって苦労するのを目の当たりにするから、被害者側クランの人々はスッキリする」と言い出した。
こうした語りにおいて、「伝統的」儀礼は、「トラウマ」や心理的問題への対処、和解や赦しといった認識枠組みのなかに位置付けられているとは言い難かった。言い換えれば、外部アクターと協力関係にあったアチョリの人々は、必ずしもこれらの認識枠組みを共有した上で「伝統的正義」を推進していたわけではなかった。そこで、筆者は、文献調査を行い、長老・首長、NGO職員、元反政府集団のメンバーをはじめさまざまなアチョリの人々にインタビューをして、国際NGO や欧米メディアなどが「トラウマ」や心理的問題への対処、和解や赦しといった視点から捉える現象や儀礼を、アチョリの様々なアクターがどのような視点から捉えているのかについて、考察を試みた。
それと同時に、国際NGO や欧米メディア、国際機関の関係者らが、アチョリの儀礼や概念を移行期正義等の枠組みで捉えるようになったこと自体についても、検討が必要だと考えた。同様の儀礼や概念を、1970年代前後の国際機関や医療の専門家らは「伝統医療」とくくっていたようだし、植民地期の宣教師は「アチョリの宗教」としてくくっていたのに、なぜ最近になって、国際NGO や欧米メディア、国際機関の関係者らは、移行期正義等に資するものとして認識するようになったのか? そして、そもそも1990年代以降の開発・安全保障言説においては、人々の心や関係性への介入がなぜこんなにも重視され必要だと捉えられているのか?
こうした疑問に直面した時に、筆者の頭に浮かんだのは、後期の批判的安全保障研究の代表的論者であり、2 つめの修士課程で指導頂いたマーク・ダフィールド(Mark Duffield)先生による、1990年代以降の国際的な政策論議における「開発と安全保障の融合」(開発と安全保障の政策論議・領域の融合)に関する分析や、先生がゼミで紹介したヴァネッサ・プパヴァック(Vanessa Pupavac)の論文で論じられていた「グローバルなセラピー統治」概念であった。
そこで、筆者は、こうした先行研究を手掛かりに、1990年代以降に開発と安全保障をめぐる政策論議が融合し、人々の心や関係性への介入が必要視されるようになった背景を、主に欧米の社会における人間像の変容という視点から検証しようとした。そして、20世紀後半の「北」の社会で生じた、環境を変化させ自らを解放し歴史を進歩させる理性的な人間像への懐疑や、近代性や物質主義に対する批判が、「南」の開発をめぐる政策論議に影響を及ぼすようになり、人間中心主義に対する懐疑に伴って形成された「脆弱な人間」像――自らの利益が何であるかを必ずしも十全に認識することができず、「傷」を受けることにより機能不全となる可能性を常にはらむ人間像――が次第に「南」に投影されるようになったからこそ、「開発と安全保障の融合」が生じたのであり、国際NGO や欧米メディアなどがこの「脆弱な人間」像をアチョリの人々に投影し、この人間像を基に形成された知識に拠りながらアチョリの土着の実践を読み解こうとしたからこそ、アチョリの儀礼や概念を移行期正義や和解、赦し、トラウマの癒しに資するものとして捉えるようになったのではないかと考えた(1)。
正義や和解と通常兵器移転規制
他方で筆者は、博士課程入学と前後して、小型武器規制や通常兵器移転規制(以下、「通常兵器移転等の規制」と総称する)の仕事に関与するようになっていた。先述のダフィールド先生は、1980年代後半に某国際NGO のスーダン事務所の代表だった。そして、2つめの修士課程が終わりに近づいた頃に、その国際NGO が日本で事務所を立ち上げたことを知り、インターンに応募した。勤務を始めて間もなく、当時の職員が、通常兵器規制(とりわけ武器貿易条約(ATT)の締結)を求める「コントロール・アームズ」国際キャンペーンを日本で展開すべきと論じ、他のNGO に働きかけて、日本キャンペーンを立ち上げた。しかし、誰もキャンペーンの政策を担わなかったため、当時インターンであった筆者が担当することになり、次第に勤務時間が増えて有給職員になった。そして、先述のウガンダでの調査は、この仕事を通じてお世話になっていた日本やウガンダのNGO 関係者の協力により、可能になった。1990年代以降の通常兵器移転等の規制をめぐる国際的な政策論議は、兵器の貿易管理や刻印といった課題だけでなく、元兵士の社会復帰やコミュニティの和解、心の癒しなどの課題までを包摂するものになっていたため、ウガンダで関連のプロジェクトを展開していたNGO も、上記のキャンペーンに関与していたのである。
このような政策論議に触れるうちに、筆者は、1990年代以降の通常兵器移転等の規制をめぐる政策論議で取り扱われる施策の幅がこんなにも広がり、国連等の場で多くの国際合意が形成されるようになったこと自体を、どのように解釈できるのだろうと疑問を抱いた。そして、1990年代以降の国連を中心にした政策論議の経緯を確認するうちに、それが先述の「開発と安全保障の融合」の過程と密接に連動していることに気付いた。また、1980年代以前の通常兵器移転等の規制をめぐる国際的な政策論議の歴史をたどり、国際会議の記録を検証する作業を行った結果として、この分野の政策論議で扱われる施策の幅が広がり、なおかつ多くの主権国家の参加の下で合意が形成された時代が、過去にもう1つだけあったことを知った。その時代とは、19世紀末にヨーロッパ諸国がアフリカ大陸に進出した時代であった(2)。
「アフリカ分割」の時代と1990年代以降
1890年に列強諸国によって合意された「ブリュッセル協定」は、アフリカの大部分の地域に対する銃器や弾薬の移転を原則禁止するものであった。そして、この協定の合意にあたっては、列強がアフリカの人々を保護し、アフリカの人々の道徳的・肉体的堕落や内部紛争を防ぎ、奴隷貿易を撲滅し、アフリカにおける商業活動等を促進することを通じて、アフリカ大陸に文明をもたらすことが謳われ、その旨が協定にも盛り込まれた。アフリカへの武器移転の禁止は、アフリカの個人と集団に介入して文明をもたらす手段の1 つとして位置付けられていたのである。その後、20世紀に入ると、国際連盟や国連などの場で武器移転規制の合意を形成する試みはことごとく失敗に終わっていたし、移転規制と人々の内的問題への介入を同時に扱うようなアプローチは、国際的な政策論議の主流にならなかった。つまり、主権国家システムの形成期以来、19世紀末と1990年代以降にだけ、通常兵器の移転規制と人々の内的問題への介入が結び付けられ、同じ合意のなかに盛り込まれるという現象が生じていたのである。また、通常兵器移転等の規制に関する1990年代以降の国連における合意形成プロセスの開始や進展は、それを決定した国連総会決議の採択時に、数が多いアフリカ諸国が賛成したからこそ可能になった。
そこで、筆者は、この2つの時代にのみ合意の形成が可能になり、なおかつ移転規制と人々の内的問題への介入がパッケージとして認識されて合意に盛り込まれたことをいかに説明し、この2つの時代に通常兵器移転等の規制を正当化した言説をどのように比較しうるのかと、問うようになった。そして、考察を進めるにつれて、この2つの時代に規制言説の主流化と合意形成を可能にするとともに、双方の時代の言説の相違を生み出した背景にある要素の1つとして、それぞれの言説の基底を流れる人間像を指摘できるのではないかと考えた。
「脆弱な彼ら」と「脆弱なわれわれ」
19世紀末のブリュッセル協定の成立を支えたものは、いわば当為命題としての「自律した理性的な人間」像に依拠して、「文明国」と「自律した理性的な人間ではなく、国家を運営することができず、野蛮なアフリカの人々」とを区別する論理であったと言える。他方で、1990 年代以降の開発・安全保障言説と、それに連動して形作られた通常兵器移転等の規制をめぐる主流の言説の基底に流れるのが、20世紀後半に「われわれ」の側の社会において浸透した「脆弱な人間」像であるならば、この人間像に依拠した「われわれ」と「彼ら」をめぐる論理は、19世紀末の論理といかなる相違があるのだろうか?
そこで筆者が想起したのは、国際機関やNGO などによる、アフリカ等の「南」の人々の描写をめぐるルールであった。「南」の人々をいかに描くかについては、1970〜80年代頃から、国際機関やNGO 等のなかで常に問題になり、「彼ら」を悲惨な状態にある野蛮で力なき人々として描いてはならない旨を盛り込んだ行動指針が形成されてきた。筆者が勤務してきた国際NGOにも、「彼ら」の描写の仕方(とりわけ写真などのイメージの使用)に関する詳細なルールがある。そして、そうしたイメージは、主に「われわれ」の側の人々をターゲットにした広報ないし情報発信において挿入されるものであり、国際NGO が自身について確立しようとしている「ブランド」を表現しつつ、「われわれ」の側の人々に訴えかけ、彼らの「倫理」や行動に働きかけるべく使用される(3)。アフリカなどの「南」の人々を自律した理性的な人間ではない野蛮な存在として描くべきではないと論じ、「われわれ」と「彼ら」を区別するような表象を忌避し、「彼ら」に関する「より適切」で「倫理的」なイメージをもって「われわれ」の側の人々の「倫理」や行動に影響を与えようとする国際機関やNGO は、自身を「理性的で自律した人間」と見なしていると言えるのだろうか(4)? 1990年代以降の開発・安全保障言説が、「われわれ」と「彼ら」との区別を否定したうえに成り立っているのであれば、この言説においては、「南」の人々の利益や幸福を十全に知ることができ、「南」において実現すべき社会の在り方に関する「解」を提供できる「人間」の存在は、果たして「北」のなかに想定されているのだろうか?
遠大な介入の論理と実践との乖離
こうした考察を進めるにつれて、開発・安全保障言説に対する既存の研究についても、少し疑問を感じるようになった。ダフィールド先生をはじめ、批判的安全保障研究の比較的後期の研究として位置付けられる論者は、国際的な政策論議の場において開発・安全保障言説が主流化したことをもって、この言説で正当化される介入が実践され、諸制度やアクターが有機的に結びつき統一体として作動するグローバルなネットワークの総体による「南」の「生の促進」が現実のものになるかのように論じる傾向がみられる。しかし、通常兵器移転等の規制に関する国際的な政策論議において、移転規制から人々の心や関係性への介入までを含む様々な施策の必要性を訴える言説が主流化したとはいえ、実際に国連等で採択された合意文書の内容は概して抜け道だらけの「ザル」状態であり、グローバルな覇権的統治を可能にするような合意内容とは言い難い。
例えば、先述のATT は、長い交渉の末に2013年4月に採択されたものの、規制対象にならない兵器も多く、規制を実施するか否かを各締約国の裁量に委ねる文言が多く盛り込まれている。アチョリ地域の「移行期正義」をめぐる論議や支援活動を通じても、外部アクターの活動は、戦略的に制度や政策を配置してアチョリの人々の生に関与するような状況とは程遠いように思われた。
したがって、筆者にとっては、開発・安全保障言説において繰り返される壮大で抽象的なスローガンや介入の論理と個々の実践との間に生じる乖離こそが、説明を要する重要な点であるように思われた。そして、遠藤先生をはじめとする博士論文審査員の先生方により、この乖離と、この言説が依拠している(と筆者が論じる)人間像との関係を明確に論じるべきとのご指摘をいただき、提出に向けて原稿を再構成した。
おわりに
以上のように、アフリカ研究を起点にして試行錯誤し、離れているようにも見えるさまざまな「点」を結び付けられそうな「線」を素描しては消してまた引き直しながら、博士論文を執筆した。論文終盤の第七章は、北部ウガンダ・アチョリ地域の事例にあてた。アフリカ政治研究にひかれ、ウガンダでの調査を通じて自身の思考枠組みに疑問を抱き、通常兵器移転等の規制をめぐるアフリカ植民地化の時期と1990年代以降の「国際的」な政策論議・合意の類似点や相違点を論理的に説明しようとし、国際NGO 等のアクターがアフリカなどの「南」の人々および「われわれ」の側の人々に対して差し向ける眼差しを解釈しようと試みた過程を、論文に活かすことができていればと思う。
こうして、どうにか論文の形にはなったものの、多くの課題を感じており、アフリカに関わられている方々にご指摘をいただくことができれば大変ありがたい。最後に、遠藤先生をはじめ、これまでご指導いただいた多くの方々に、この場を借りて改めて感謝の意を表したい。
(1)榎本珠良(2007)「 「アチョリの伝統的正義」をめぐる語り」『アフリカレポート』44、pp.10-15
Tamara Enomoto(2011) Revival of tradition in the era of global therapeutic governance: The case of ICC intervention in the situation in northern Uganda. African Study Monographs, 32-3, pp.111-134
(2)榎本珠良(2012)「 通常兵器の移転に関する国際規制の歴史と現状:冷戦終結後の進展とその限界」『軍事史学』48-2、pp.4-21
(3) 榎本珠良(2006)「 ライブ・エイドからライブ 8 へ:20 年後のアフリカ・イメージ」『アフリカレポート』42、pp.33-39
(4)Tamara Enomoto (2014) Governing the vulnerable self at home and abroad: Peace and justice in northern Uganda and “KONY 2012”. African Study Monographs, Suppl.50,pp.25–41