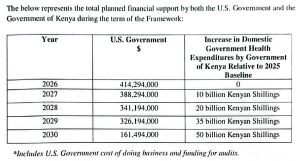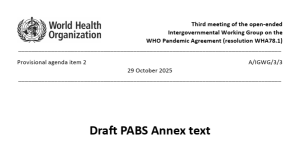25年目の検証-飢え・援助・エイズ
Ethiopia: verification of hunger, aid and AIDS in the 25th year
『アフリカNOW』88号(2010年7月31日発行)掲載
筆者:林 達雄
はやし たつお:2002年から現在までAJF代表。1954年生まれ。愛媛大学医学部を卒業後、国立横浜病院外科勤務を経て、1983年よりNGOの職員としてアフリカ(特にエチオピア)、アジアで海外協力活動に従事。日本国際ボランティアセンター(JVC)元代表。ほっとけない世界の貧しさ前代表。2000年よりアフリカのエイズ問題に取り組む。著書『エイズとの闘い-世界を変えた人々の声』(岩波ブックレット)。
はじめに
エチオピアでは干ばつが来るたびに、実に多くの人が命を失った。私自身も1984-85年の飢饉に立ち会った。「どっから来たのか」とたずねると、弱りはてた被災者たちは「コレブ(Koreb)からだ」と答える。「何時間かけて歩いてきたのか」。「1週間」。欧米の団体の多くは、自分たちが活動しやすい幹線道路沿いで救援活動を行っていたが、被災地からは歩いて1週間かかった。それでは遠すぎると考えたわれわれは、被災者にとって少しでも近い地点、車両が入れるぎりぎりの地点を選んで活動をはじめたが、それでも被災者たちは3日3晩かけて歩かねばならなかった。体力の残った者しかたどり着けなかっただろう。私たちの仮設病院だけでも500人以上が亡くなり、共同墓地に葬られた。
あれから25年、何回もの干ばつがエチオピアを襲った。エイズ・マラリア・結核という感染症が追い打ちをかけるように辺境を襲った。アフリカの政府の多くは、周辺地域の面倒をあまり見ない。都市での栄養失調や感染症には対応しても、周辺の地方は置き去りにされやすい。今回、実際にこの地に来るまで、コレブは干ばつと感染症の2つの災厄の被害を受けているに違いないと内心、覚悟を決めていた。ところが幸運なことに、私の心配は裏切られた。
私がコレブを訪れた12月1日は世界エイズデイなので、コレブでも催しがあった。その催しの後、私たちについてきた少女がいた。保健センターの看護師によると、彼女はHIV陽性者である。両親をエイズで失い、いまは親戚の家で養われている。彼女は毎日薬を飲むことができ、その結果、彼女は生きながらえている。私は、このような辺境の地でエイズ治療が可能になっているとは思っていなかった。いくつもの奇跡がつらなって、1年半前に治療が可能になり、彼女は今日ここに生きている。
その奇跡は第一に、エチオピアという国家の努力、特に地方分権の努力である。アフリカの普通の国では国外への頭脳流出もあり、医療従事者、特に医者が不足している。医者がいなければ治療ができない。特に地方に医者が足りないために、地方での治療は困難である。ところがエチオピア政府はアフリカの普通の国とは異なっていた。「医者が足りないなら育てればよい」「地方にいなければ地方に配置すればよい」と考え、それを実行に移した。郡のヘルスセンターには医師に準じるヘルスオフィサーを配置した。県にはエイズ発症の目安になるCD4細胞数を検査する機械が設置され、ヘルスオフィサーは検査の結果にしたがって治療を開始するかどうかを決定できる。世界でもっとも貧しい辺境の地のひとつに人材を投入したのだ。
第二の奇跡は、世界基金(世界エイズ・結核・マラリア対策基金:GFATM)の存在である。エイズ・結核・マラリアという3大感染症に対してしっかりとしたプロポーザルを出す政府やNGOに資金を出す仕組みが国際的に存在している。エチオピア政府にいくらやる気があっても、資金がなければ適切な感染症対策を講じることはできない。世界基金は、必要なところに必要な資金が配分される仕組みをつくり、HIV陽性者やNGOにも理事の席を与えている、ユニークで民主的な機関である。
第三の奇跡は、AJFを含めてエイズ関係のアドボカシーを行う人びとやグループの存在である。2000年代の初頭、私は「世界の誰にもエイズ治療薬を」という運動に加わり、一定の役割を果たした。その後はAJFとともに世界基金などに関するアドボカシーを行った。民主的な基金が存在しても、そこに資金が集まらないと、子どもたちの命を助けることはできない。AJFは、日本政府が世界基金に対する拠出を滞りなく行なうように働きかけた。コレブで出会った少女がいまここに生きているという奇跡の一端は、彼女のような弱い立場にある人を断固として助けようという意思表明がこの世界に存在し、その一角にAJFという日本の団体の存在があったからである。アドボカシーというと、回りくどい行動のように受け取られるかもしれないが、条件が整えば、遠いアフリカの生命をも助けうる、やりがいのある仕事なのだ。
私がなぜ20数年間、NGOで活動しているかというと、25年前の大飢饉に遭遇したからだ。1984年10月、BBC(英国放送協会)は、エチオピアの大飢饉を伝える衝撃的な映像を放映し、世界を震撼させた。そして2009年10月にBBCは再び、一週間続けてアフリカの干ばつを報道した。かつての死にゆく人びとの写真を持ち出し、最悪の事態を予感させた。「放置すれば1984-85年の事態の再来になること」をにおわせた。またオクスファム・オーストラリアは「エチオピアの今回の干ばつは1984年ほどは悪くない。しかし、極度に憂慮される事態である」と警告した。WFP(国連世界食糧計画)は「東アフリカ地域全体で2,300万人が干ばつの被害に直面している」というアピールを出した。NGOや国連の警告に比べると、エチオピア政府のアピールは控えめだ。BBCの干ばつ報道をエチオピア政府は無視している。本当のところはどうなのだろうか。
少なくとも1984-85年の飢饉と比較するのは間違っている。これがAJFの友人たちの共通の意見だった。なぜなら、政府が食料不足を放置していない。ひどい干ばつが来ても、「飢饉」にまでいたらせない対策を、つまり人を殺させない対策をエチオピア政府は講じている。しかし、この目で見るまでは納得ができない。エチオピアまで実際に見に行くことにした。
アディスアベバにて
1. 生産的セイフティネットプログラム(PSNP)
11月18日にドバイ経由でエチオピアの首都アディスアベバ(Addis Abeba)に到着。この街は、確かにビルは増えたが、25年前とそれほど変わっていない。ビルの下には昔ながらのトタン屋根の家が並んでいる。立体交差が見られたと思うと、裏道はデコボコで土ぼこりがひどい。修理のために2mも掘り返している。近くには炭を売る店があり、わがドライバー氏も買って帰る。壮大な教会や市庁舎や警察所があり、コーヒー屋や菓子屋が繁盛している表通りを一歩出ると、そこには昔ながらの生活がある。旅の疲れのためか、2,600mという標高のせいか、頭がかすれた。かすれた頭で、到着早々にJICA(国際協力機構)の中村貴弘さんから言われた「この国は一握りの人たちの『農業に対する強い決意』でなりたっている」という言葉をかみしめていた。
エチオピアでは、800万もの人口が慢性的な食料不足に陥っている。この800万の人びとは、農民なのに食料が自給できず、森林を失って土が流されたり、干ばつが来ればすぐに飢えに直面する。25年前の大干ばつのときも、こうして100万人以上が命を失った。私自身もかつてJVC(日本国際ボランティアセンター)の一員として緊急救援活動を行い、墓掘り人夫をやとい、多くの人たちをみとった。その後、10年ほど復興支援活動を試みたが、エチオピア政府との関係がうまくいかず、活動を継続することが困難になった。
「農業に対する強い決意」をもった人たちは、この800万人を決して見捨てないことを決意して、生産的セイフティネットプログラム(PSNP: Productive Safety Net Programme)を実施している。この800万人に、土と水が流れるのを防止する段々畑のようなテラスや道をつくるなどの土木事業をしてもらい、その代償として現金あるいは食料を配っている。このプロジェクトの開始から2010年で5年目になるが、栄養失調は見られても死までにいたることはかなり少なくなったようだ。土壌保全を行ってもそう簡単に生産性があがるわけではないといった批判にさらされながらも、断固としてこのプログラムを続けている。さらに、6万人の農業普及員の育成も行い、5年かかっても10年かかっても人を育て、育てた人を農村に派遣している。これも信念がなければできないことだ。
エチオピアの飢えを考えるときにベースとなるのがこの800万の人口であり、それに加えて毎年の政府アピールで発表される食料不足の人口が加わる。今年の政府アピールでは620万人の食料が不足していると発表されたが、食料不足に直面している総人口は1,420万人であると推計できる。干ばつが来ても、それがひどい栄養失調や死に結びつかなければ、「よし」とされる。だが現政権は、大干ばつの最中の1984年に「革命10周年記念」の式典をおこなっていた当時の政権とは異なり、少なくとも無策ではない。一方で、エチオピアにとって最大のドナーのひとつであるWFPのことを「食料援助屋」(Food Aid Industry)と呼び、決して媚を売らない。NGOにとっても手ごわい交渉相手である。
近年では、食料の国際価格の高騰というもうひとつの問題もおき、もともとあるインフレに加算される形で食料価格が上昇している。一時期はWFPの食料在庫も不足したといわれる。「飢え」を話題にするとき、誰しもが「世界的な食料危機」(Global Food Crisis)の問題を語っている。
2. 「飢え」との接近、しかし1984年とは異なる
11月24日に、オクスファム英国のエチオピア人スタッフで、人道プログラムを担当しているカベデ・モラさんを訪ねた。彼によれば、ひどい栄養失調はすでにエチオピア各地で発生している。そして干ばつの程度は、1984年の大干ばつのときに匹敵しうると言う。エチオピアでは人口が増え、一人あたりが使える土地は1/3ぐらいまでに減っている。
エチオピアには、2-4月の小雨期と7-9月の大雨期の2回の雨期がある。政府の発表した食料を必要としている人口620万人は、小雨期作の農産物の収穫の結果を反映した数字であり、大雨期作の収穫の結果をふまえていない。大雨期作の収穫の結果をふまえた数字は毎年12月末に発表される。しかし、それでは遅すぎるかもしれない。1984年の大干ばつのときも、政府発表が遅すぎたから、あのような惨事になったのだ。
セイブ・ザ・チルドレン(SCF)英国がエチオピアの各地で、栄養失調児に対する補助給食を行っている。そしてその活動地域のひとつは、私が訪問を予定している地域と重なっている。私は飢えつつある地域に行くことになるのだ。その地名はアジバール(Adibar)。この地で私たちは1985年に緊急医療活動を行い、500人以上の人びとの死をみとり、埋葬した。
エチオピア全土の農産物の85%の収穫を可能にするはずの大雨期が今年は遅く、また早く終わってしまった。十分な収穫が見込めないことは確かであろう。子どもの栄養失調は、ウォロ(Wello。1995年までの行政区分による州名だが、現在も地名として使用されている)、ソマリ(Somali)州、アファール(Afar)州などでの各地で報告されている。特にソマリとアファールではコレラ患者が見られるようだ(「コレラ」と言うと人びとがパニックに陥ることも少なくないので「急性水様性下痢」と言っているのだが)。
今年の食料不足と栄養失調がひどいことは確かだ。しかし、1984年とは次の点で異なっている。
- 早期警報システムが働いている。25年前の大干ばつの後、早期警報システムの必要性は多くの人や機関により語られ、当時、人道問題研究会の代表であった緒方貞子さんもその重要性を訴えていた。
- 政府の対応がまったく異なる。早期警報システムだけではなく、慢性的な飢えに対して現実的な対応を行なっている。
- 国連が協力している。
- 道路が格段によくなり、被災地へのアクセスが可能になった。
予想の段階で実際に何が起こるのかはわからない。しかし、アマルティア・センは『貧困と飢饉』で次のようなことを指摘している。メディアや野党は飢饉を未然に防ぐセーフティネットとして機能する。現在ではNGOもこうした役割を担うだろう。この点において、エチオピア政府は過敏すぎる。信念をもって飢えを防ごうとしている政府であるなら、野党やメディア、NGOの言葉にも聞く耳を持ちつつ、確固たる姿勢を貫いてほしい。
首都のアディスアベバにいると干ばつや飢えはほとんど実感できない。25年前の大干ばつのときも首都の住民は、農村で一体何が起きているのかまったく知らなかった。紫色の花が咲き誇る美しい街だった。同じときに農村では飢饉がおきていた。今回はどうなのだろうか。私自身も含めて多くの関係者が麻痺しているのか。カベデ・モラさんは、かつてのウォロ州マクレダ郡でJVCが救援活動を行っていたことを知っていた。まずは行って見てこい。そう言われているようだ。
フィールドトリップ
1.インジェラのかおり
窓を開けるとどこからともなく、主食のインジェラに添えられるワットというシチューの匂いがしてくる。ケベというバターとバルバレという調味料、肉や野菜からなる独特の匂い。お札や人やすべてのものにしみ込んだエチオピアの匂いだ。エチオピアを離れると懐かしくたまらない匂いである。一方、アディスアベバから地方に向かうとインジェラ漬けとなる。むろん、まずくはないが、毎日毎食となると耐えがたいところもある。
アディスアベバから北上すると、工事中の道路が続く。中国からの援助を受けたこの国は、国中が道路工事の真っ最中である。アラハム州の州都デシ(Dessie)まで飛ばせば6時間で行くが、今回は10時間もかかってしまった。デシでは土曜日だというのに、エイズ治療を行う病院の関係者が待ってくれていた。施設は暗く、入院したいとは思えない。しかし治療体制は充実し、活気にみちている。HIV陽性者に対して治療を開始するか否かの基準になるCD4細胞数の検査機が設置されている。ここは地方の基幹病院なのである。
2. アジバール
11月29日早朝にデシを出発して、アジバールに向かった。途中の標高は高く、富士山の頂上を超えている。かつての道は急峻で、両側の絶壁にトラックが落ちていた。アジバールでは、1985年の1年間、JVCとSHARE(国際保健協力市民の会)が共同して緊急医療活動を行った。今回同行してくれたかつてのスタッフ、イエットバラクさんとともにゼロから人を育て、ゼロから施設を作った。必要なモノのすべてを他団体から借り、必要な知識のすべてを他団体から習った。
アジバールにはいまだに当時の共同墓地が残されている。長い干ばつの終わりに雹(氷雨)が降ったのだ。遅すぎた雨は人を生かすどころか人を殺す。その翌日には遺体がトラック一杯積まれていた。
その墓地のとなりはいま、郡のヘルスセンターとなり、かつてのスタッフが看護師になっていた。ワールドビジョン米国がここを拠点に、子供に対する食料配給を行っていた。定期的に食料を配るだけであって、余病を併発していないかぎり入院はさせない。入院は急性水様性下痢(コレラ)などの流行の危険があるため、入院はなるべくさせない。飢えはいまのところ地域全体を襲っているわけではない。栄養失調の子どもの姿が散発的に見え隠れする。
1984-85年のときと現在との違いは、以前は政府が飢えに対応しようとしなかったのに対して,今回の飢えに対しては、政府が予防措置をとってきたことだ。それどころか飢えを「迎え撃とう」としている。政府だけでなくNGOもまた「迎え撃とう」としているのだ。以前のNGOは、問題が起きてから現場に来たのだが、いまはどっしりと腰をすえ、問題に対して先まわりしてプロジェクトを始めている。このアジバール周辺だけでも3つのNGOが活動している。
3. マーシャ
1985年にJVCとSHAREがアジバールで緊急医療救援活動を1年間行った後も、私たちはエチオピアから撤退しなかった。アジバールからコレブに向けて道をつくりながら、前進した。その中ほどにあるウォロ州マクレダ郡マーシ(Masha)を最前線にして、「餓えない」ムラづくりを始めた。
森林面積が2%になった大地は地表を覆うものがない。そこに降る雨は容赦なく表土を押し流す。私たちはこの大地からこれ以上表土が流れ去らないために、土留めを作り、木の苗を植えた。作業をしてもらう代償として食料を配った(フード・フォア・ワーク:Food for Work)。また、料理教室や寸劇を通して、女性の生活を改善した。私たちは住民たちに新しい選択肢を示し、緑の大地を取り戻すことを促した。しかし、農民たちの意欲を高めたのだろうか。農民たちにとってみれば、単なる土木事業にすぎなかったのではないだろうか。
エチオピアのNGOの協議体で、現在350のNGOが加盟しているCRDA (Christian Relief and Development Association)という団体がある。25年前にはJVCもCRDAに加盟していた。当時、エチオピアに殺到するドナーからお金や物資を受け取りながら、実際に活動するNGOをひき合わせる役割をになっていた。当時のCRDAの課題は、圧倒的に「フード・フォア・ワーク」であった。現在、政府が慢性的食料不全に対する対策と、土壌流出への対応として行っている事業は、すでにCRDAに属する数多くのNGOによって、当時から行なわれていたのだ。
4. 若き指導者たち
マーシャでは週に一度、市がたつ。マクレダ郡内のみならず周辺地域でもっとも大きな市である。主食のテフの値段は上昇していない。家畜の値段も下がっていない。つまり、私が訪れていたときの市の様子を見るかぎりでは、飢えの兆候は見られない(正確に判断するためには、定期的に調査する必要があるが)。
11月30日にマクレダ郡の長官と会った。左右にそれぞれ保健省と農業省の責任者を従えている。いずれも30歳前後の若さである。保健省はエイズに対してさまざまな試みを行っている。数年前まで人々を脅かしていたというエイズは、いまでは笑顔で語れる話題になっている。驚くべきことに、この地でもエイズ治療が行われているのだ。この町のヘルスセンターから120km離れた病院まで毎週、血液検体が運ばれ、その結果次第で治療が始まる。このヘルスセンターにはヘルスオフィサーという医者に準じる医療従事者がいて、治療が可能なのだ。
コーヒーセレモニーを利用してカウンセリングを行っているのがエチオピアらしい。HIV陽性者を抱える家族への支援や、孤児に対する仕事の提供も行っている。陽性者たちがガソリンや清涼飲料水を売っている。エチオピアは暗い土地柄だと思っていたが、そんなことはなく、陽性者も差別やスティグマにさらされることなく普通に生きている。それどころか、陽性者自身が証言者となり自分の経験を皆に語ることにより、感染予防の役割を果たしている。問題はむしろ周辺にある。マクレダ郡の中心地ではなく、コレブなどの辺境の地にこそ問題が存在しているのだ。
農業省によるPSNPの支援を受けている人口はマクレダ郡全体の1/3、約5万人に上る。誰が支援の対象になるかは村人自身が選ぶ。その中で6,000人が「卒業」したという。「卒業」とは何かと聞くと、土壌流出からの「卒業」だという。しかし、土壌流出という悪夢からの「卒業」は容易ではない。かつての経験からそう感じた。
5. 辺境の中の辺境
マーシャを過ぎると突然、道が悪くなる。車が滑り落ちそうになり、恐怖が走る。辺境の地コレブへの道である。斜面に農地があるため土壌流出がひどい。それに加えて、病虫害がいる。家畜の病気もはやっている。マラリアや結核をはじめとする人間の病気も流行している。人びとのエイズに対する理解も足りない。スーダンからの移民がいる一方で、出稼ぎに出る人も多い。コレブの6つの村にも健康普及員が2人ずつ派遣され、エイズをはじめとするさまざまな病気と格闘している。
第三世界と先進国の境は、実は第三世界の都市と農村の間にあると感じてきた。この地域に当てはめてみると、マーシャとコレブの間に境がある。農業と環境、医療の問題への対応において、まさに露骨に格差がある。しかし前述した、コレブで出会ったHIV陽性者の少女のことを思い出して欲しい。現状は「変わりうる」のだ。たとえば、マーシャにおけるエイズの問題は数年で劇的に変化した。
農業・環境・気候変動の問題も人と知恵が結集すれば「卒業」しうる。それに加えてNGOには経験とネットワークがある。この両者が緊張関係を持ちながら協力することができれば、辺境の地での問題も解決の可能性が見えてくる。
25年前には、政府の役人がやって来るとコレブの住民たちは、どこかに逃げていた。役人は税金を取りにくるか、兵役のために若者を連れてゆくか、どちらかの目的でしか来なかったからだ。しかし、いまは違う。政府は地域の生存のためにやって来るのだ。健康普及員や農業普及員がよい例だ。彼らは辺境の地に思い出したように来るのではない。辺境の民とともに生きているのだ。
6. 5つの飢えとエチオピア
エチオピアはいま5種類の飢えにさらされている。
- 土壌侵食による慢性的な食料不足:これに対してはPSNPなどによって表土の流出を防ぐ活動を促進し、その代償として現金または食料を配っている。これは干ばつがきても飢えを未然に防ぐ行為であり、エコ・セイフティネットとでも呼ぶべき行為である。800万人を対象にしたエチオピアの国家的事業であり、2010年で最初の5年のプログラムが終了する。
- 天候不順・気候変動による飢え: 政府関係者は口をそろえて天候不順のことを「気候変動」と呼ぶ。エチオピアに首相のメレス氏がアフリカの代表として出席する国連気候変動コペンハーゲン会議(COP15。2009年12月に開催)を意識しているのだろう。頻度を増す干ばつのことをストレートに「気候変動」と呼ぶのだ。かつては干ばつが起きるのは数年に一度だったが、最近では干ばつのない年が数年に一度になっている。
今年は、小雨期(2-4月)に雨がふらず、政府は620万人分の食料が足りないことを国際社会にアピールした。しかしオクスファムなどのNGOは、それは控えめな数字であると批判した。そして、その批判がほぼ正しいことは、今回のフィールドトリップでもあきらかになった。
政府は、11-12月に収穫を迎える大雨期(7-9月)の雨量不足を考慮していない。実際に2009年の大雨期は始まりが遅く、終わりが早かった。病虫害、家畜の病気なども起きている。そうすると約1,000万人が食料不足に陥ることになる。とくに子どもに対する食料配給の需要が日ごとに増えている。 - 世界的な食料危機: 2007-2008年におきた国際的な食料および燃料価格の高騰の影響を、エチオピアも真っ向から受けた。都市を中心に大きな打撃を受け、今なおその余波が残っている。インフレも加わり、食料価格が30-50%高騰したと人びとは語っている。
- 家庭内での子どもの飢え・慢性的な栄養失調: 食料が足りないから必ずしも栄養失調になるわけではない。2歳までの間に何を食べさせるかによって、その後の成長が変わる。エチオピアの多くの家庭では大人が食事の8割を食べ、残ったものを子どもが食べている。食料不足で一回の食事の量が減ったとき、大人から順に食べ物を減らすように習慣を変えることが大切だ。食料が最初に大人ではなく子どもに与えられれば、栄養失調は確実に減る。
- 人口増加による飢え: CRDAの関係者によると、人口増加の主な原因として、女性の教育の問題、早婚の風習、乳児死亡率の高さ、などがあげられる。
7. 1984-85年に匹敵する飢饉が再来するのか
CRDAは、(1)政府から人びとに分配されている土地が一人あたりわずか0.5haしかない(エチオピアでは、土地はすべて国有地とされている)、(2)人口が増加している、(3)干ばつの頻度が増している、(4)現実に栄養失調の頻度は高まりつつある、(5)政府の非常事態宣言が遅れている、などの理由により、1984-85年に匹敵する飢饉が再来する可能性があると警告している。
この警告はもっともだが、1984-85年のときと決定的に違うのは、飢饉にたいする予防措置である。食料不足に陥りやすい800万人の人びとには、すでに食料あるいは現金を配っている。国民の飢えに対してまったく顧みなかった1984年当時の政府と、飢えへの対策を国家事業としてやっている現在の政府とでは、結果がまったく違ってくる。その一方で、今年の干ばつは、干ばつが常時起きる地域ではなく、南部諸州を中心で起きているため、予防措置がゆきわたっていない。その意味である程度の「飢え」はおこりうる。しかし、「飢え」があるとしても、100万人が死んだ25年前の状況とは比較にならない。かつての大飢饉が再来する可能性は「ノー」である。
エイズ 10年目の検証
「世界の誰にもエイズ治療薬を」。10年前に世界の各地で始まった運動がいま実りつつある。25年前に飢饉にあったコレブに住む母子感染の少女が薬をもらい、元気に生き延びていた。コレブは、最貧国のひとつとされるエチオピアの中でももっとも貧しい地域である。エチオピアでのエイズ対策は劇的な進展があると国連は報告していた。しかし、世界で最も貧しいムラにおいても、まさかエイズ治療薬が配られているとは思ってもみなかった。
地域の努力は目をみはるほどである。特に地方で活動する医療従事者の育成、人材をつくるところに力をいれたことは特筆すべきことだ。しかし、「世界の誰にもエイズ治療薬を」という10年前からの世界規模の運動が実らなければ、少女はいま生きていない。その運動は南アフリアのザッキー・アハマットさんや国境なき医師団が中心となって行った活動であり、アフリカのHIV陽性者のNGO、たとえばケニアのアスンタ・ワグラさんたちも参加した運動だ。そして日本の私たちも、感染症対策沖縄国際会議(2000年12月)に参加してエイズ治療の必要性を訴えた。
それらの総体としての行動がなければ、「エイズ治療」という革命はおこらなかった。それだけではない。その後の国際機関の活発な動きがなければ、この少女は生きていない。いくつもの運動と努力が連なって、10年後の微笑みがある。世界基金に対するアドボカシーもその一つだ。私たちが何もしなければ、少なくとも日本が拠出すべき額のお金は入らなかったかもしれないない。そうした意味で、小さいながらもスクラムを組んでやってきた日本の国際エイズ運動、とくにAJFに誇りを感ずる。
10年たち、全世界のエイズによる年間死亡者の数は、300万人から200万人にまで下がった。この変化は驚くべきことである。しかし、スラムを含む都市部では治療が始まっても、農村部では難しいと思っていた。世界の中でももっとも貧しいこの地域では不可能であると、あきらめてきた。しかし、その思い込みは、自分勝手なものにすぎなかった。中央および地方の努力、人材の育成、世界基金、アクティビストなどの一貫したラインができるとき、奇跡がおきる。この少女が生き延びるということは、地方分権のおこした奇跡であり、同時にアドボカシーのおこした奇跡である。アドボカシーとは、生身の一人の人間を生かすものなのだ。