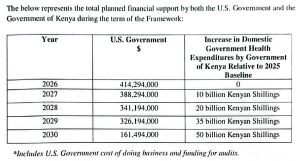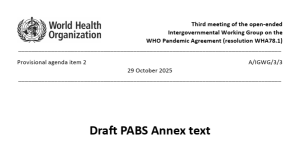Issues people living in African tropical forest are faced with
アフリカNOW No.93(2012年1月31日発行)掲載
西原智昭
にしはら ともあき:1989年から20年以上にわたり、コンゴ共和国やガボンなどアフリカ中央部熱帯林地域にて野生生物の研究・調査、国立公園管理、生物多様性保全の仕事に従事。現在の所属先と役職はWCS(Wildlife Conservation Society)コンゴ支部、コンゴ共和国北部Ndokiランドスケープ・自然環境保全技術顧問。
※本稿は、AJF主催で開催したセミナー「アフリカ熱帯林地域での自然環境と野生生物」(2011年3月29日)における講演・質疑応答と「アフリカ熱帯林地域での開発業と先住民・地域住民」(4月6日)における講演を元に編集しました。
日本の多くの人々が持つアフリカのイメージは、乾燥地帯やサバンナ、草原が広がり、そこにキリンやライオン、ゾウなどがいるというものであろう。そしてそこに住む人々は飢餓に直面し、貧困に苦しんでいるという印象を持つ人も多いに違いない。アフリカ中央部の熱帯林地域は、そうしたアフリカのイメージとはまったく違う世界である。しかし、日本にはアフリカの熱帯林に関する情報がほとんどない。本もなければ、写真集も出ていない。テレビ番組で放映されたことはあるが、一過性のものにすぎない。今回はその熱帯林に住む人々が直面している課題について紹介したい。
近年、開発が進み、アフリカ熱帯林にもいろんな人が暮らすようになった。大昔からそこに住んでいる先住民、もう少し大きな町や都市に住んでいる地域住民、また、熱帯林を研究・調査している人たちや環境保全に取り組む人たち、ツーリスト、いろんな開発業に関わっている人たちなどがいる。2000年以降の10年ほどの間に、コンゴ共和国(以下、コンゴ)では、熱帯林を伐採して熱帯材を供給する仕事が国家経済にとってどうしても必要ということで、開発が進んできた。
このように、いろんな人が関わっている現場で、野生や自然環境、野生生物を守りましょう、あの動物はかわいいから守るべきだという話だけでは通用しない。アフリカ熱帯林にいるいろんな人たちと話をしながら、どういう状況にあるのか、これからどういう方向へ行くかを見極めていかないと、自然保護をやりますと言うだけではまったくお話にならない。まずは、自然保護を進めるための前提となる、アフリカ熱帯林とそこに住む人々の現状を報告する。
アフリカ熱帯林はどこにあるのか
アフリカの地図を見ると赤道直下に緑の濃い部分がある。これが熱帯林だ。かつてはかなりの広さだったのだが、伐採で消えてしまったところが多く、熱帯林が残っているのは中央部のやや西寄りのところだけになっている(p.2の地図を参照)。熱帯林が広がる地域で日本でもよく知られているのは、昔はザイールと呼ばれていたコンゴ民主共和国である。内戦や大統領選挙が日本でもニュースになっている。私自身が20数年かかかわってきたのは、その隣のコンゴと大西洋に面しているガボンだ。現在、コンゴ北部にあるンドキ国立公園とその周囲で主に仕事をしているが、数年前、ガボンのロアンゴ国立公園でも貴重な経験をしたので、そのことは別稿で紹介する。
最初に開発業で一番大きい熱帯樹の伐採業の現状と、自然環境やそこに住む野生生物への影響について紹介する。次いで、開発や野生生物に問題があったとき、そこに何千年も住んできた先住民たちが昔から持っている伝統的な生活の仕方や生業、あるいは文化がどうなっているのかについて報告し、関連してエコツーリズムについて考えていることについて述べる。
熱帯林と伐採業
コンゴもガボンも、人口がそんなに多くなく人口密度が低いことから、人々が長年住んでいる土地では、その土地で代々続く村長が持っている土地があり、また村人それぞれの土地もあるが、国土の大部分は国が直接に管理している。その国土を、国はいくつものブロックに分割して把握しており、その一部を分譲住宅販売のような形態で売り出している。
国際NGOが調査して、ここには動物がたくさんいて環境保全にとって重要なので、国立公園にするのが望ましいと提言したので、コンゴでもガボンでも、政府はいろんな状況をかんがみて法を制定して、国立公園を設置した。その他の土地では、伐採会社が伐採したいと希望すると、切った分の木材の量に応じて税金をかけることを条件に伐採許可を出している。その木材にかけた税金が重要な国家収入になっているのだ。
コンゴ人やガボン人による伐採会社といったものはそれぞれの国に数%しかなく、ほとんどが外資系である。コンゴもガボンも旧フランス領なので、一番多いのはフランス系の伐採会社で、近年では中東系の人とかがやっている会社も増えている。さらに最近になって、中国をはじめとするアジア系の会社が登場しているが、日本の伐採会社はない。
自然林である熱帯林では、たくさんの樹木がある中で有用材として出荷が可能な直径2?3mの大木をチェーンソーで切っている。そんな大木を1本切り倒すと周囲の木もなぎ倒されて、空間が開けることになる。かつては熱帯林には木がたくさんあり、草も生えていて歩くことしかできず、車を乗りいれることはできなかった。しかし、切った木を運び出さないと商売にならないので、伐採を行っているところまで、ブルドーザーなどを使い、何万本、何十万本の木を切って道を作っている。しかも、切り開いたままだと、雨が降ると大型トラックは通れない状態になるので、ラテライトを入れて整地している。そうやって作った道路は路面が固まって、時速80kmぐらいで飛ばしてもまったく問題がない。そのような道を作り、何十台もの大型木材搬出用のトラックを入れ、伐採地で切り分けた木材を何百kmも離れた積出港まで運び出す。それが熱帯林の伐採業の仕組みだ。
ンドキ国立公園の周囲に広がる伐採地
コンゴ北部のンドキ国立公園は1993年に設置された。この国立公園はおよそ4,000km2、東京都の約2倍、山梨県と同じぐらいの面積がある。1993年時点で伐採会社があったのは、ンドキ国立公園の南側の地域だけであった。東側はごく小さな村がいくつかあるだけの完全な熱帯林で、人がまったく入れないような場所だった。2000年ごろまでは、ンドキ国立公園の南側で小規模に行われていた伐採が、この10年で東側と北側でも始まり、ンドキ国立公園の周辺がすべて伐採区になってしまった(西側は中央アフリカ共和国との国境)。伐採区を全部あわせると、ンドキ国立公園の約3倍の面積になる。それだけの広さの熱帯林が、分譲住宅の売り出しではないが、すべて売却されたような形になってしまっている。
南側と東側ではヨーロッパ系の伐採会社が操業している。他の地区では、中国系、中東系の会社が、また別のところでフランス系の会社がと、いろんな国籍の伐採会社が入っている。かつては、大きな沼地があって車で通ることができなかったところにも、伐採会社が協力して、大きい丸太を何十本、何百本と置いて、その上に土を固めて大きい道を作った。またそれぞれの伐採区内の道路をつなげている。伐採会社が道をつなげたことを契機として、コンゴ政府も首都ブラザビルから北部に向かう約900kmの道路を改良して国道として整備した。首都から国道を丸1日かけて走り、伐採会社の道路を通って隣の中央アフリカ共和国まで行くことができるルートが整備されたのだ。
野生動物や象牙を運び出すことも簡単に
道ができて木材が運び出され、人間の移動が楽になったというだけでなく、狩猟した野生生物をトラックに積んであっという間に運び出すこともできるようになった。そういう大きな変化がここ10年くらいで起きている。その結果、伐採区では6年前と比較して軒並みゾウの密度が減っている。伐採区ができたことで、人が入って来るだけでなく、ゾウを打ち殺す銃も容易に手に入って来るのだ。また象牙を運び出すことも簡単になった。こうして象牙の違法取引が容易になる中で、生存の場所を失ったゾウが国立公園に入ってきているので、国立公園内のゾウの密度は上がっている。
野生生物への直接の影響を考えると、この木材搬出道がいちばんの問題となる。2010年の6ヵ月間で地元のパトロール隊が摘発した銃、発見したゾウの死体やゾウの肉、あるいは逮捕した密猟者の数は、以前と比べ圧倒的に増えている。東京都の6倍くらいの面積の伐採区を、たかだか数十人のパトロール隊でカバーできるはずがないので、摘発されるのはごく氷山の一角にすぎない。
地元の人たちが食べている野生動物の肉のことをブッシュミートと言う。地元の人が野生動物をとって食べることは、コンゴの国内法で認められており、また合法的な範囲内であれば、野生生物への影響もそれほどない。だが道路ができたことにより、大量に野生動物を獲ってその肉を町へ運んで売るという動きが始まっている。伐採道路によってブッシュミートの交易が楽になり、ビジネス化してしまったのだ。このようにして密猟や密輸などの違法行為が増加している。
携帯電話と違法行為
携帯電話の普及も影響を及ぼしている。あちこちにアンテナが立てられ、森の中でも電話ができるようになった。そうすると、「何日か前に獲ったゾウの象牙があるから、取りに来い」というような連絡を簡単にすることができ、象牙取引が容易になってくる。携帯電話だと連絡が簡単なだけでなく、他人に情報も漏れない。以前は、携帯電話どころか手紙だって簡単に出せなかった。20年前に私が最初に森の中でキャンプを張って調査・研究をしたときは、重要な連絡がある場合は、雇っていた現地のアシスタントに手紙を持たせ、30km離れた最寄りの村に歩いて届けてもらった。村長か誰かへの依頼状を書いて、少しお金も入れて、渡してもらったのだった。その村長が何かの機会に町へ行ったときに、郵便局に持って行ってくれるという仕組みだった。そのため、私が帰国した後に手紙が着いたということもあった。
いまでは森にいても携帯電話がかかってくるだけでなく、インターネットも使えるようになった。その分、仕事も増えている。それは同時に、熱帯林へのアクセスが簡単になったことで、ゾウの密猟も増えていることを意味している。
マルミミゾウの密猟と象牙の密輸
熱帯林に住むマルミミゾウが、密猟の対象になっている。象牙は、歯から進化したものなので、ゾウが倒れたからといってヒョイと引っこ抜けるものではない。そのため、密猟者はゾウを殺した後、首を切って頭を持って行く。あるいは、象牙の根っ子のところまで切り裂いて、象牙を抜く。それだけの作業が必要なので、ゾウが死んでいなければ象牙を取ることはできない。うかつに象牙を抜こうとしてゾウが暴れだしたら手に負えない。密猟者はそのことを知っているので、まずゾウを殺すのだ。麻酔銃を使って象牙だけ取ればと思う人もいるかもしれないが、麻酔銃を買うだけのお金があったら、密猟などしないだろう。武器が簡単にしかも安い値段で手に入る、伐採用の道路ができたおかげで簡単に運べる、といった変化が密猟の増加につながっている。
ゾウを撃ち殺すのに使われている自動小銃、それもカラシニコフが出回っている原因は、内戦の後始末がきちんとなされていないことにある。1990年以降コンゴでは2度ほど内戦が起きた。隣のコンゴ民主共和国では、いまだに内戦が続いている。しかも、武器売買ビジネスもあって、武器が安く入手できるようになっているし、道路のアクセスがよくなったので、大量の銃弾も安価かつ簡単に入ってきている。
先に紹介したように、パトロール隊がパトロールを行っていて、運が良ければ密取引される前に象牙を摘発して没収することができるが、それは氷山の一角にすぎない。また、パトロール隊は伐採道路に何ケ所か検問所を置いていて、そこを通る車を全部チェックしており、象牙など持ちだすことが違法な物を発見すれば、直ちに逮捕している。24時間体制でチェックしており、車の通行を止めるための遮断機も設置してあり、パトロール隊員も車の音がすれば起き出してくるので、夜でも車は簡単に通過できない。そうしたことを知っている人たちの中には、自転車を使う人もいる。夜、検問所の遮断機の横を自転車で突っ切るのだ。自転車だとたいして音もせず、また簡単にすり抜けることができるからだ。ただし、自転車で大きな象牙は運ぶのはたいへんなので、用意した糸のこぎりで象牙を切って運んでいる。大きい象牙には飾りものとしての価値があり高く売れるのだろうが、一本の象牙をいくつかに切り分けたカットピースでもいい値段で売れることを彼らは知っている。運び出した象牙がどこへ行くのかは、彼らの関心事ではない。切られた状態でもいい値段で売れる、そういった需要があるということを知っているのだ。
熱帯林の中に町が誕生する
開発が進むということは、伐採会社の基地が森のど真ん中にできることを意味する。切った木材を集め処理する基地には、伐採作業にあたる労働者も住んでいる。それまで誰も住んでなかった森のど真ん中に何百人、何千人という労働者が新たに住む基地ができるのだ。
アフリカでは、労働者が住むところに彼らの妻や子どもはもちろん、親戚からいとこまでが集まる。労働者が1人やってくると10人、20人が一緒に来て暮らし始め、ブッシュミートを食べることになる。人が住んでいなかった森に家畜はいない。電気がなく冷蔵庫も使えないので、保存することもできない。基地の周辺の小動物を銃猟や罠猟で捉え、自分の家族を養っているのだ。燻製になった真っ黒いブッシュミートが、基地の中で売られていることもある。道路があるので伐採会社のトラックで、小動物が何十匹、何百匹も運ばれることもある。
1990年代初頭、伐採会社の近くのある村の人口は200-300人程度であった。その後も2000年ごろまではほとんど変化がなかったが、それ以降あちこちに伐採会社が入ってきたので、村に住む人もあっという間に増えてしまい、かつて200人だった村の人口が今では3倍の600人になっている。
サバンナのウォーキングサファリ
伐採業の進出は、野生生物と自然環境に大きな影響を及ぼしただけでなく、何千年も前からそこに住んでいる先住民の生活も大きく変えた。先住民の文化は変貌したというにとどまらず、失われようとしているというが現状だ。
熱帯林の先住民について考える手がかりとして、アフリカ東部ケニアの草原で暮らす先住民マサイの変容を見てみたい。背が高くて、ジャンプするととても高くまで飛び上がる、赤っぽい服を着て牧畜をしながら何千年も草原で暮らしてきたマサイがいまどのように変わっているかを考えてみたい。
マサイが家畜を放牧してきた土地が、国立公園や保護区になってしまうと、彼らは居住することができなくなる。それでも放牧は許可され、伝統的な生業自体は一応やって良いことになっている。それでも、ライオンを殺すことでマサイの戦士として一人前の資格をもらうという彼らの伝統的な文化が、ライオンを保護しなければならない、獲ってはいけないという野生生物保全との兼ね合いで問題になっている。
また、草原に住んできた中で培われた自然に対する知識、例えばサバンナの薬用植物や動物に関する知識を、マサイの若者たちはだんだんと失っている。最近では放牧している牛のふんを固めて作っていた住居の壁をビニールシートでカバーしたりすることもあるそうだ。形は昔のままだが、素材が違っているという家屋も出てきているのだ。かつてはあまり町に出なかったので教育も受けていなかったマサイの中に、近年、高等教育を受ける若者も出てきて、伝統文化と野生生物保全との折り合いを考えるというような先進的な考え方を持ち始めているという。
ケニアにはたくさんの国立公園があり、日本からも多くの観光客が訪れている。観光客を対象に、マサイはショーとして伝統的なスタイルのダンスを披露している。もちろん伝統的な意味でのダンスもやるのだろうが、何月何日の夜何時からディナーパーティに合わせてダンスをするといったビジネスにしているのだ。観光ロッジの運営者もマサイを雇うと観光客へのアピールになるので、赤い服を着た人をホテルのボーイとして立たせている。それを見て、観光客は、「すごいなあ!」と喜んだりするのだ。
最近はやっているサバンナを歩くツアー、ウォーキングサファリのガイドとして、マサイはもっとも有能だ。自然の知識を持っているので、ウォーキングサファリのガイドとして働いて現金収入を得ている人もいる。土産物売りをしているマサイも多い。彼ら自身が伝統的なやり方で作った物を商品として売っているケースもあるが、明らかにマサイとは関係ないとわかる物を売っているケースもある。マサイが作ったのではないのに、マサイが売っていればマサイの伝統的な品物だと思ってお土産に買う観光客がいる。特に、日本人はいいお得意さんだと言われているそうだ。
熱帯林で暮らす人々にとっての開発
アフリカ熱帯林の先住民は狩猟採集民で、かつては「ピグミー」や「ピグミー族」と呼ばれていた。しかし、今ではそれは蔑称だというので○○地域に住んでいる△△といった民族名で呼ぶのが普通なのだが、ここではわかりやすく「ピグミーさん」と表記する。「ピグミーさん」は何千年もの昔から熱帯林に住んでいて、狩猟・採集をしながら、原始的な自然に、熱帯林に依存しながら生きてきた。背丈が小さい小柄な人たちとしても知られている。
マサイで分析したことを、「ピグミーさん」に当てはめて考えてみるとどうなるのか。熱帯林地域は伐採によって縮小しているので、彼らが伝統的な生活を送ることのできる場所は縮小していて、すでに熱帯林からあぶれだしているというのが現状だ。また、町の人がブッシュミートを大量に獲るために野生生物も少なくなっている。かつて狩りや罠猟で獲っていた動物すら獲れなくなっている。動物のいる場所に行って動物を獲りながら移動していくという、ある社会単位で移動しながら伝統的な生活を維持するための熱帯林が残っていないという状況の中で、定住化が進んでいる。定住化して、狩猟という彼らのアイデンティティーを発揮することができない、普通の農耕民になってしまっているのだ。
また、コンゴ政府は政策として、「ピグミーさん、もう森から出て来なさい」と呼びかけている。定住が進まないと人口調査がうまくできないし、選挙のときに「ピグミーさん」にもちゃんと投票してほしいのだ。「ピグミーさん」たちはいまだに身分証明書など持っていないが、登録させ選挙権を持たせるという政策が進められている。ガボンにも「ピグミーさん」たちがいるが、ガボン政府は、「森の中に住んでいた野蛮な民族はもうわれわれの国にいない」と言いたがっている。だから政策として、森の中に住んでいる人たちはさっさと森の中から出てきなさいと言っている。
「ピグミーさん」たちが「ジェンギ」という名の古典的な歌を歌い、何月何日にどっかのお父さんが亡くなって何日か目に当たると、その日に歌とか踊りをやるという習慣は健在だ。しかし最近では町との接触が多くなり町の音楽が入って来るので、「ピグミーさん」も町の音楽の方がいいや、ということになってきている。この傾向が続くと、何十年後かにはもともとの歌や踊りよりもディスコに行った方が楽しいということになり、歌も踊りもすっかり忘れてしまうだろう。その可能性は十分にある。
植物の薬用性、この植物は食べられるか、このキノコは毒キノコなのか、この蛇は毒蛇なのか、この獣道を通るとどこに通じるのかなど、「ピグミーさん」の熱帯林に関する知識は豊富だ。彼らは、コンパスも何も持っていなくても自由に森の中を歩けるという能力を持っていた。外部の人間だと迷うような所でも、必ず迷わずに同じ場所に戻ってくる。体の中にアンテナみたいなものが入っているようだ。しかし、森の生活から離れると、そういう能力や知識もなくなってしまう。森の中に住んでいたころ「ピグミーさん」たちは、木の葉や草を屋根と壁代わりにして、ドームみたいな家に住んでいた。最近は村に定住して、ビニールシートを使ってドーム状の小屋を作っている人もいれば、土とか木材を使って仮の家を作っている人もいる。
教育についてもマサイと同じで、かつては学校教育を受ける機会はほとんどなかった。最近は少しだがキリスト教の教会に通う人もいる。宣教師や神父が行っている布教活動を受けた「ピグミーさん」は、素直に言われたとおりに入信している。そして、文字を読める「ピグミーさん」は聖書を読んでいる。がくぜんとするような風景だ。
熱帯林地域におけるツーリズム
熱帯林地域ではときに、罠猟の物まねや「ピグミーさん」の伝統的な歌と踊りをショーとして見せて小銭を稼ぐようなことはあるが、ケニアの草原で展開されているような大規模なツーリズムはない。一方で、細々と行われているツーリズムにとって「ピグミーさん」はガイドとして重要で、また伐採する人も「ピグミーさん」をガイドとして雇用する。「ピグミーさん」は森の中をくまなく自由自在に歩けるし、また有用材を指定して探してくるように指示すると探してくれるからだ。研究・調査をする人も、きわめて有能な助手として雇っている。このように雇用されるチャンスがあるので現金収入を得ることがあるが、「ピグミーさん」の場合、お金を手にするとほとんど酒代に使ってしまっている。貯蓄するとか、自分で稼いだお金を妻に渡すといったことはいっさい考えていない。10年ぐらい前まで服を着ていなかった、男女ともにちょっと大きい葉っぱで大事な所を隠すぐらいのかっこうだった「ピグミーさん」も、いまはみんな服を着ているが、お金の使い方になじんだとは言えないようだ。
「ピグミーさん」とマサイを比較すると、マサイは国立公園から締め出されたものの放牧自体はできており、従来どおりの生活基盤があると言える。「ピグミーさん」の場合、熱帯林そのものがなくなりつつあり、生活の基盤さえ危ういというのが現状だ。
国立公園に対する見方が180度変わった
また、マサイの場合、高等教育を受ける人が出てきて、野生生物や自然保全は大事だがわれわれの文化も大事なので何とか維持していきたいといった先進的な考えを持つ若者も出ている。一方、「ピグミーさん」は自己主張をしない。なぜしないのかよくわからないが、自己主張している場面に遭遇したことがない。その結果、状況に流されている感じがする。お金が入ってくればお金に、伐採業者が入ってくれば伐採業者の思惑に、国家の政策が出されれるならば政策に流されているようだ。自分たちの文化を継承する意志があるのかもしれないが、自己主張しないので、そういった意志がないように見られている。その点でマサイと明らかに違う。特に問題になるのは、若い人たちが森の中を歩く能力をだんだんと失っているという現実だ。そのことに関わって、国立公園に対する見方が一部では180度変わってしまったということも起きている。
1993年にわれわれの働きかけでンドキ国立公園ができたころ、「ピグミーさん」が伝統的な生活をすることを擁護する人権団体は、国立公園ができると「ピグミーさん」が締め出されてしまうと批判した。それから20年近くたち、伐採業で森がどんどん縮小し、「ピグミーさん」の生活基盤さえ残ってない現状を見て、かつては国立公園設置を批判した人権団体も、もう何も言わなくなった。
国立公園があることで自然環境保全も伝統文化存続も可能になる、国立公園のおかげで動物も残っていて、動物たちが国立公園外にもやってくるので何とか狩猟・採集が可能になっているというのが現状であり、国立公園がなくなれば本当に何もなくなってしまう。「ピグミーさん」の伝統どころの話ではないのだ。
熱帯林地域でのエコツーリズム
熱帯林地域に位置するンドキ国立公園でも、またその近くでもエコツーリズムが試みられている。しかし、熱帯林は見通しが悪く、音や痕跡などで動物がいることはわかっても実際に見るのはなかなかたいへんだ。バイ(湿地性草原)のように開けた場所であれば、観察台のようなものを作り、そこで動物を観察することも可能だが、ごく小規模なものしかできない。
アフリカ熱帯林地域まで来るような観光客は、サバンナでキリンや象をすでに観ていて、サバンナでは見ることのできないニシローランドゴリラなどを目当てにやってくる。ウガンダやルワンダ、コンゴ民主共和国東部の山岳地帯にすむマウンテンゴリラを観るツアーも人気がある。マウンテンゴリラを観た人はいてもニシローランドゴリラを観た人はあまりいないので、熱帯林の奧までやってくるのだ。
自然環境とか野生生物を守り、しかも経済的効果があるからエコツーリズムはいいことだと考えている人も多いだろう。ゾウを密猟する、象牙を売るなどの違法行為が起こるのは経済的に貧困だからだ、現金収入が欲しい地元の人がいるから、エコツーリズムによって彼らを雇用すれば経済的貧困には陥らないだろう、という発想なのだろう。
エコツーリズムの第一のメリットにあげられているのは、エコツーリズムによって雇用創出ができるということだ。いままで収入のなかった地元の人が定期的な収入を得て、経済的支援になるというのだ。第二に、熱帯林における生物保全につながる、しかも、先住民がもともと住んでいる熱帯林の自然保全も同時にできることだという。先住民が昔ながらの狩猟・採集を安心してできる場所が確保できるというのだ。
しかし、実際にエコツーリズムを試みるとさまざまな問題が出てくる。まず貨幣経済の浸透という問題がある。ついで政府の政策の影響がある。ケニアやタンザニア、南アフリカなどの国々は、ツーリズムによってかなりの国家収入を得ており、ツーリズムは国家的な事業と言える。ところが熱帯林の場合、サバンナと違い、大規模なツーリズムを行うことができない。熱帯林の中にたくさんの人を運ぶことはできないし、もしたくさんの人が来ても熱帯林の中はうっそうとしていて見通しがきかない。そのため、ケニアやタンザニアのサバンナと同じやり方ではツーリズムは発展しない。
ではどうするかというと、先住民を利用したツーリズムをやることになる。先住民の伝統的な歌とかダンスをショーとして見せるということになるのだ。ショーのために雇用された先住民が得たお金は、貯蓄や家族のために使われるわけではなく、ほとんどが酒代になっている。村で活用して欲しいと村長に渡し、村民会議を開いて使途を決めてもらった謝礼が、結果的には村長のポケットに全部入ってしまっているというケースもある。このように、収入機会の創出が地域貢献になっていない。それは、ツーリズムの概念がケニアやタンザニアのように高い段階に行ってないからだろうが、収入機会の創出が人々の生活や地域の改善につながるには、もっともっと時間のかかることかもしれない。
現状では、先住民一人一人が得たお金は欲望充足、例えば酒が飲みたいといったことに使われている。一方で、国立公園の入園料が森林省に収められた後、それが一体どこに行って何に使われているのかがわからない。国立公園の入園料から、維持費やスタッフの経費が支出されるはずなのだが、そのためのシステムがまだ何もないのだ。
『アフリカNOW No.93』特集:アフリカ熱帯林が直面する課題と日本
アフリカ熱帯林Q&A
アフリカに進出した中国企業による開発の課題 西原智昭