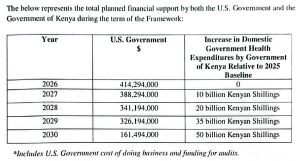Findings from my stay in South Africa after ‘Post-Apartheid’
『アフリカNOW』105号(2016年6月30日発行)掲載
宗村(安齋)敦子
むねむら(あんさい)あつこ 1988年新潟県生まれ。上智大学文学部史学科卒業、大阪大学大学院文学研究科文化形態論博士前期課程修了。博士後期課程より関西大学大学院経済学研究科(経済学専攻/アフリカ経済)に在籍。研究テーマは「1930年代の南アフリカ西ケープにおける缶詰め産業」。関西大学経済政治研究所アフリカ環境班準研究員。2016年5月から1年半の現地調査を始めた。
南アフリカ史を学び始めた経緯
大阪からケープタウンまでで14,335km。カタールのドーハとジョハネスバーグを乗り継ぐとしたら、トランジットを除いてもゆうに20時間はかかる。これほど遠い国へ行くことになるとは、つい最近まで想像がつかなかった。それもそのはずだ。大学に入学してからというものの籍を置いてきた西洋史研究では、普段アフリカが紙幅を割いて言及される機会は相当限られている。まさかアパルトヘイト後、さらに言えばポスト・アパルトヘイト「後」と呼ばれる今の南アフリカへ行くことは考えたことすらなかった。
日本にいながら南アフリカのことを知る機会は一般的にはほとんどない。1988年生まれの私にはアパルトヘイトの記憶はほとんどなく、日本でも反アパルトヘイト闘争の盛り上がりがあったことはつい最近まで知らなかった。ネルソン・マンデラ(Nelson Rolihlahla Mandela)の名前は知っていたとはいえ、好きだった世界史の教科書の末尾にあったのを覚えている程度だった。彼が何をして、南アフリカでどのように記憶され、また私が生まれる前の日本でどれほど親しまれた名前だったのかを知るようになったのはごく最近のことだ。
私が南アフリカの歴史研究に足を踏み入れたきっかけは卒業論文だった。大学4年生だった私は論文執筆のためにJ・A・ホブスン(John Atkinson Hobson)『帝国主義』(”Imperialism–A Study”, 1902)を読み、彼が特派員としてボーア戦争勃発直前に南アフリカに行った数ヵ月に着目した。とくに『帝国主義』の執筆に利用された彼の『南アフリカ戦争』(”The War in South Africa-Its Causes and Effects”, 1900)を夏季休暇の間に読み、南アフリカ社会への想像はかきたてられていった。これ以降私の関心は、ボーア戦争後の植民地体制と英国自治領化以降に南アフリカで形成された人種問題に絞られていった。大学院でのこの5年間では南アフリカを訪ねることにより、今まで以上に私の世界観や日本社会の捉え方は日々修正を加えられている。
南アフリカへの渡航
4年前の南アフリカへの渡航は、私にとって初めての海外経験であった。滞在したのはわずか1ヵ月。大阪大学にいた当時の私の研究環境では南アフリカを訪ねた経験のある人はおらず、旅行会社でも名前を出すだけで驚かれるありさまだった。危険な都市ジョハネスバーグのある国、アパルトヘイト後の得体のしれない国。それが渡航する前の、私を含めた西洋史研究室での南アフリカの印象であった。
実際のところ、これまで訪ねてきた西ケープの内陸地域の印象はまったく異なっていた。ケープタウンからステレンボッシュ、さらにパール、ウースター、ウェリントンに向かう途上ではワイン用のブドウ畑が左右に広がり、ところどころにタウンシップが見えた。道路すれすれに牛が放されており、信号待ちの間に時々車に近づき野菜や果物などを販売する人が訪ねてくる。ケープタウンを夕方に歩かない限りは、渡航前に恐れていたような危険にこれまであったこともなく、私が持つ南アフリカへの印象は格段に良くなっていると感じる。
しかし、このような牧歌的な町中ですら、1994年以降に作られたモニュメントや博物館とは別に、時折アパルトヘイトの痕跡を目にする。ウェリントンでインタビューをした時のこと。1945年生まれでこの町に70年も住んできた彼女は、町中のみならずワイン工場や
農場も案内してくださった。その際に見かけたのは、1980年代から横断歩道の傍らに設置されていたグレート・トレックの記念碑や、いまだに教会に飾られていた1960年のコモンウェルス脱退を祝う街中のパレードの写真だ。インタビュー中も彼女からは、アパルトヘイト中の学校の分離についてのみに留まらず、彼女の家族のルーツや、祖父がウェリントンでアフリカーンス語学校を始めた最初の教師だったことなども話していただいた。
ここではアパルトヘイトの時代を生きていなかった私ですら、かつて彼らの側から見てきたであろう華やかなアフリカーナー・ナショナリズムの記憶を追体験することができる。研究テーマには直接関わらないものの、無意識のうちに滞在中アパルトヘイトの話題に触れることにためらっている。この地域の印象がもともとJ・M・クッツエー(John Maxwell Coetzee)の小説『マイケルK』(”Life & Times of Michael K”,1983)などからきていたため、このような話を聞くにつれアパルトヘイト中の華やかな記憶からいかに距離を取るべきかに悩まされている。
日本社会の捉え方への変化
南アフリカについての日本における発言や南アフリカへ渡航中にかけられた言葉により、今ではこれまで当たり前のように過ごしてきた生活環境にも違和感が生まれつつある。昨年、南アフリカにおけるかつての人種分離を肯定した発言として、曽野綾子氏の記事は在日南アフリカ大使館などからの批判を受け、大きな注目を浴びた(1)。すぐさま抗議が起きたとはいえ、2016年になっても彼女の著作が書店で人気書になっているのを見ると、日本において人種分離がはっきりと断罪されないことは、今なお私に衝撃を与えている。
日本での人種差別への抗議の一過性や中立論の多さが気になりだしたのは、昨年末に大阪市内のヘイトデモを見たときからだ。「難民反対」を名目にした当該デモでは30人規模の小さなデモ隊を100人以上の警察が警備し、沿道からカウンター(抗議行動)が大きな音を立ててヘイトデモに抗議する。町の様子はまさに「賛成・反対・中立」に分かれており、多くの通行人は中立を表明するかのようにデモ隊を避けるでもなく沿道のカウンターに冷たい視線を投げていた。警察がカウンター側を向きながら背後のヘイトデモを警備する様子は、自主的に集まったカウンター以外に人種差別を断罪する者がいないという現状への危機感を持たせている。
エンパワーメント
南アフリカへ滞在していると、偶然出会っただけの人の言葉に力づけられることがある。多くの南アフリカ人は日本から一人で訪ねたことを告げるだけで驚嘆したリアクションを取る。実際には他の極東からの旅行者にも会うこともあるため、なぜ日本から来たことに驚かれるのか、その理由はわからない。それでも日本にいると「いつ結婚するか」「いつ学業をやめるか」「南アフリカを訪ねることに親は反対しないか」ばかりを尋ねられる私にとって、訪ねた先で「ブレイブ」と呼ばれるのはいつもうれしい。
とても勇気づけられた出来事がある。ウェリントン滞在中に地元の博物館に史料を見せてもらっていたときのことだ。通い続けて親しくなった学芸員や地元の大学生のアルバイトに、街中で会ったときに家族のことを聞かれ、私は2年も顔を合わせていないと答えた。決まりきったことを言われるに違いないと身構えた瞬間、彼らは顔を崩して「クール!」と叫んでくれた。私の人生では初めて独立して生活していることが肯定された瞬間だった。
滞在中にはその場限りで初対面の人に助けられることが多々ある。前述のC さんしかり、車で町中を案内してもらったあと「また会えますか」と尋ねたときに、「私70歳だし、生きていたらね」と答えてさようならのあいさつを交わした。電話番号が手元にあるのみで、最後に会ってからメールを取り合っているわけでもない。ケープタウンでお会いした福島康真さんによれば、南アフリカ人は「住む」(live)を「滞在する」(stay)と言い換えることがあるそうだ。この言葉は「自分の居場所は固定されておらず、いずれどこかへ流れていくだろう」という将来の見方を言い表した言葉だという。とても気に入っている言葉で、今では私も、近いうちに日本を離れて遠い場所へ流れていくかもしれないと思っている。
(1) 編集部注:『アフリカNOW』102号の特集を参照。