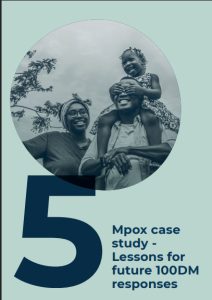Women’s grassroots struggle and possibility of literature
『アフリカNOW』110号(2018年3月31日発行)掲載
※本稿は、2017年5月27日に開催された研究会「反アパルトヘイト運動と女性、文学」に置いて会場の参加者から出された質問などを受けた、3人の発言者のコメントをまとめました。
佐竹純子さん 日本反アパルトヘイト女性委員会の1985-1988年を振り返る
津山直子さん 反アパルトヘイト運動を牽引した女性たちの先進的な活動
くぼたのぞみさん 南アフリカ女性の日キャンペーンで駆け抜けた1年
司会(牧野) 佐竹さん、くぼたたさん、津山さんの話を聞いて会場からさまざまな質問やコメントがありました。ここでは、(1)アパルトヘイト後の南アフリカの憲法の素晴らしさと現在の南アフリカの現実とのギャップ、(2)佐竹さんとくぼたさんの発言のなかにたびたび出てきた「普通(の)」ということの意味、(3)武力闘争と性暴力の両面から解放運動のなかの暴力の問題、という3点について、それぞれの発言者からコメントをお願いします。
くぼた 私が答えられることって、そんなにないと思ったんですが、言葉に携わっている間として、「普通」という言葉について一言。1980年代後半に、本当にビギナーとして、何もわからないまま反アパルトヘイト運動にかかわったときに、いろいろなメディアから入ってくる情報、あるいは本から見えないものを「普通」と呼びました。普通の女たちの暮らしが知りたいと。というのも、前面に出てくるのはほとんど男たちの話で、書いている記者も男性が多かった。今のように女性の記者が活躍する時代ではなかったように思います。知っているのは、松井やよりさんぐらいでした。だから、その壁の向こうにあるものを知りたいというときに、「普通」という言葉を使ったように記憶しています。
普通と普通でない人とは、いつでも分断されるんです。同じことを言っていても、この人は特別であると。フェミニズムもそうなんです。佐竹さんと津山さんが話してくれた南アフリカの女性たちの歴史を見るとわかるように、明らかに女性たちの活動・主張はフェミニズムです。運動としてはそう言っていいんです。だけど、言った途端に囲われる。特別な人たち、フェミニズム、怖い、怒っている人たち、アンハッピーだからそういう主張をする、男にもてない人たちみたいなニュアンスを、べったり張られるんです。そういうところと闘っていく、そうではない、ともう一回ラベルを引き剥がしたり、揺さぶりをかけて崩したりすることが、実は文学者の仕事なんですけれど。そういう意味で、いつでも、普通と普通でない人というのは区別される、同じものが。というのが私の感想です。
佐竹 「普通」ということで言えば、今の私はこの言葉に違和感があるし、使いませんが、あの時点で、くぼたさんが言われたようなことも含めて、「普通」という言葉を『ローズと、ノンヴーラと、南アフリカのふつうの女たち』でも使っていたんだと思います。さっき、私は、「普通の」というのを「草の根の」に置きかえてみたり、最前線にはいなかった女性たち、と言ったりしました。その後で、津山さんが、解放運動の最前線にいた人たちと、そうではなかった人たちをつなげてくれてよかったです。「普通」という言葉を、今の私はそんなふうに受けとめています。
次に、暴力のことです。一言で言うと、非常に語りが難しいものを表現できるのが、やっぱり、文学なのだろうと思っています。そういう意味で、例えば、『デイヴィッドの物語』の翻訳をしたくぼたのぞみさんと協力した海野るみさんたちに、すごく敬意を持っています。南アフリカの文学で、そのあたりのところを、真正面から捉えている作家の作品があるし、南アフリカの中でそういうことを議論して、声を上げ続けている人たちもいて、実際にそういう議論の場に居合わせたこともあります。日本もたいがい男社会ですが、文学というのは何か変える可能性があると思います。
くぼた 私が好きなのは、読み手を引っ張り込んでしまう作品。クッツェーは、ノンフィクションとフィクションの境目を取り払いたい思いで書いている人なんですが、読ませてしまうテクニックのすごさがある。でも、作品のなかで、はっきり断定はしないんです。ただ、読者はすごく深いところで揺さぶりをかけられて、自分で答えを出さないとならなくなる。今までの自分じゃいられなくなる、自分と向き合わざるをえなくなる。そういうのがすぐれた作品だろうと私は思うんです。
1980年代にANC がペンも武器であるとして、あらゆる手段を反アパルトヘイトの運動のために使う戦略をとった。1988年にクッツェーが「フィクションと歴史は別々のものである」と言って、ものすごい議論になった。つまり、文学は武器として使われるものではなく、ずっと昔からあったのだと。ナディン・ゴーディマ(Nadine Gordimer)(1) なんかはANC のメンバーだった人ですが、クッツェーとゴーディマは政治的スタンスが違うと、ことあるごとに比較される時代があった。そして、アパルトヘイトがなくなったときに、反アパルトヘイトのために書いてきた人たちは当座、書くことがなくなったように見えました。
南アフリカから出てくるものって何か元気ないな、という時代がしばらく続いたように思います。若い人が特に。だけど、ずっと書き続けていた人たちは、ずっと書いている。例えば、アンドレ・ブリンク(André Brink)とか、ゴーディマとか、クッツェーもそうですが。白人の作家が圧倒的に多い。まあ、さまざまな意味で彼らは特権的な立場、世界の趨勢が見える位置にあったわけですが。
文学はある程度、距離をとらないと、運動の中に入ってしまうと、長いスタンスで考えたときに力をなくすと、実感として、言葉のレベルで、ずっと思っていました。”Staffrider” は私も読んでいました。1980年代までの”Staffrider” って輝いていたんです。だけど、その後は、今の南アフリカの状況をどう伝えるかというときには、なかなか伝わってこない。実況中継的なものは時間がたつと古くなっていく。それは、実はすごく大事なことです。文学って、やっぱりそういうところも含めて、非常に大きななにかを背負わされているジャンルで。闘争の「ための」文学というのは限界があると、私ははっきりと思います。
佐竹 私は、そのあたりのところでは、くぼたさんと感覚が違います。反アパルトヘイトのメッセージを主張してきた作家にもいろんな人がいます。くぼたさんもよくご存じのゼイクス・ムダ(Zakes Mda)はずっと一貫して書いています。むっちゃおもしろいです。ゼイクス・ムダは、アパルトヘイトの時代に、詩から始めて芝居もはっきりと反アパルトヘイトの主張で書き、そのころは活動しながらなので、小説を書く余裕は十分になかったのでしょうが、解放後、自由に書ける環境が整いたくさん書いています。彼の小説では、反アパルトヘイト運動、アパルトヘイト下でのさまざまな問題と現代のつながり、あるいはアパルトヘイト以前のことも描き、アパルトヘイトの前も後も見すえた上で、現在の解放がどうなるのかを考えさせられます。
現代の南アフリカには憲法と現実のギャップがあるし、私も個人的にいろんなこと、特に暴力のこととかHIV/ エイズのことを思い出して、すごくつらくなることもあるんですが、文学に可能性があると思っています。他方、ライフヒストリーを誰が記録するかという課題があります。女性委員会では工場労働者など黒人女性たちの聞き取りを読みました。しかし、それを聞き出して書いたのは一体誰かというと、白人の女性たちだったのです。聞き取りの意味は何か、どういうところを拾い出すか、どう起こして文章にするかというのは、重要な議論の対象です。
もっと南アフリカのフィクションを紹介する仕事もしたいなと思っています。ノンフィクションや聞き取りだと注意が必要な個人情報などへの配慮も、創作であれば言いたいことを書けます。私は、それは力になると思います。現代の南アフリカの文学には、レイプの問題や、女と男の問題だけでなく、セクシュアル・マイノリティーのことなど、いろんな新しいテーマに関わる作品が出ています。
かつて女性たちの声を聞きたいと聞き取りやライフヒストリーを読んだのは、直に南アフリカに行かれなかったから、ということもあります。今も、文学を通して、女性たちのメッセージを見つけていけるから、南アフリカの文学をそういう意味で、やっぱり伝えてきたいと思うんです。
津山 普通、草の根、最前線ということばが出ました。私は反アパルトヘイト運動の最前線にいた人たちは、草の根の人たちだったといえると思います。一番危ない最前線で闘い続けたのは、草の根の人たちでもありました。佐竹さんがずっとつながってきたソウェトのノムザモ・パークの女性たちも、最前線で、アパルトヘイトの差別と抑圧と困難に日々直面しながら、反アパルトヘイト運動に参加していました。
1990年にANC 女性同盟の全国大会に参加したのですが、ANC が合法化され、30年ぶりに南アフリカ国内で開催できた大会でした。それまで、ザンビアに本部を置く亡命組織でしたが、南アフリカ国内でもANC を支持し、運動を進めてきた人たちも大勢いて、初めて一同が顔を合わせ、公で議論できた感動的な場でした。でも、役員選挙では、国内で運動の最前線にいた人たちより、国外にいてANC の組織の中でリーダーだった人たちが多く選ばれました。国内では政府の弾圧があり、ANC というのは表に出せなくて、秘密裏に運動し、組織化もできなかった。翌1991年に行われたANC 全体の大会でも同じことが言えましたが、国内の最前線で活動してきた人たちが多く選ばれていたら、その後のANC のあり方も違っていたかもしれません。
憲法と現実のギャップがある一方、憲法があるから踏みとどまっているところ、進展したことも、もちろん多くあります。他の社会について語るときに、同時に自分の社会を見たり、どう変えられるかを考えることが重要ですが、女性の権利ということでは、日本は選択的夫婦別姓でさえ、30年以上の女性たちの運動があるにもかかわらず変えられないでいます。南アフリカの人たちと同じように悩みながら、互いに学びながら、運動や活動していくということを続けてきました。
草の根の女性たちが書く、ということについては、アパルトヘイト時代のほうがかえって書ける場があったかもしれません。言論への規制が厳しかったからこそ、書く場を作った。先ほど話に出た”Staffrider” だけではなくて、NGO が出していたものや識字クラスから生まれたもの、もっといろんな媒体がありました。民主化後にNGOへの資金は減り、終了してしまった活動も多いのですが、草の根での識字や発表の場はいつの時代も重要だと思います。
私は、エレノア・シスル(Elinor Sisulu)が義理の両親のウォルターとアルベティーナのことを書いたもの(2)やジャーナリストで活動家だったズベイダ・ジャファ(Zubeida Jaffer)が書いた本(3)などが好きです。アパルトヘイトが終わった後、アパルトヘイト時代にどう生きてきたか明らかにできるようになり、ライフヒストリーとして共感したり、反アパルトヘイト運動のヒストリーとして新たに知ったり、気づくことが多くあります。
くぼた あちこちのウェブサイトで見る限り、ここ20年くらい、過去の記憶を掘り起こして物語化していく、という本がものすごくたくさん出ていますね。
津山 真実和解委員会(Truth and Reconciliation Commission : TRC)で出てきた膨大な真実を、それを語った人自身が自分の言葉、英語ではなくて自分たちの、例えば、コサ語だったりツワナ語で書こうという取り組みもありました。
くぼた 南アフリカの公用語11言語のうち、ヨーロッパ言語の2つではない言語で作品を書くことに対して賞がありましたが、数年前それがなくなったそうです。かつてコサ語だったと思いますが、こんな分厚い本が出たとニュースになったりしていました。
ただ、全体的に振り返って1960年代の抵抗運動をもう一回見直すとか、そういう動きがたくさん本になっています。お父さん、お母さんはどういう人だったのかというような本です。他方で、南アフリカではSF 的なものとかクライムノベルがすごくはやっていますね。そうした本が書店にたくさん並んでいるという話を聞きました。すごく両極端だなと思います。
津山 歌だと、それこそ11の公用語全部の歌がそれぞれはやってヒットするんだけど、そういう意味では、やはり文学は、ハードルが高いのかな……。
くぼた 本を読むという習慣をみんなが持っているわけじゃないというところが大きいのかもしれませんね。読むといっても、新聞、雑誌で終わり、みたいな感じなんでしょうか。日本でもどんどん減っていますけれども、小説を読むということ自体、非常に少数の人たちがやっている状況です。文学はものすごいパワーを持っていますので、誰かが書いていくべきだし、育てていかなければいけない文化だと思います。
佐竹 一番最近に南アフリカへ行ったとき、メアリー・バートン(Mary Burton)さんが若い黒人女性たちと一緒に話していた場面に出会いました。バートンさんは、反アパルトヘイト運動に関わり、TRC のコミッショナーにもなった白人女性です。彼女が、TRC のことはよく知らないけどそれを伝えていきたいから演劇活動をしているという若い黒人女性たちと、今後の南アフリカをどうしていったらいいかと議論していました。そういう光景にはすごく励まされますよね。その一方で、レイプをめぐっていろんな大変な経験をしたという話も、同じ会場の中で語られていました。
津山 1956年に女性たちの大きな抗議行動があったことや、その前にFEDSAW という全国組織ができたことに触れましたが、各地で女性たちが議論や行動する場ができ、それらが形になって大きな運動になりました。突然、全国組織が出てきたわけじゃなくて、そこに至るまでにさまざまな人種を超えた女性たちが、勇気を持って語り、行動したということが大事なのだと思います。それは現代でも同じことが言えますね。
司会(牧野) 最後に、くぼたさんと佐竹さんから、日本で反アパルトヘイト運動に参加した経験について、一言ずつ話してください。
くぼた あの当時は3人の小さな子どもの母親で、ほとんど専業主婦、専業母だったんです。1988年にやっと一番下の娘が小学校に入り、ちょっと夜も出かけていいかなと思えたときに出会ったのが反アパルトヘイト運動だった。だから、「普通」の女ってじつは自分のことだったんです。まさに、名もなき、おしめを洗っていた私だった。それが出会いによって変わりました。楠原さんを始めほかの人たちに場をつくってもらって、本当に感謝しています。おまけに、ビギナーなのにハラレまで行ってこいと言われました。たまたま、仕事でマジシ・クネーネ(Mazisi Kunene)の翻訳を引き受けて、南アフリカのことを知っている人に聞きに行こうと、足を運んだのがそもそもの始まりだったんです。
佐竹 私も、いっぱいいろんなものを受けてきたから、それを次の世代につなげていきたいと考える年になってきました。そういう意味で、出版社の理論社の働きって重要ですね。今日の研究会に参加しておられる荒井きぬ枝さんから、お父さんで理論社をつくった小宮山量平さんのことを聞き、改めて思いました。1960年代や1970年代、アフリカの人が何を目指して、どんな声をあげていたというのは、理論社が出した本でしか読めなかったのです。古本屋で探した本をいっぱい持っていた人が、最近、蔵書をくれたんです。むっちゃうれしくて、宝物だと思っています。これまで私らが学んできたことを次の世代にもつなげていかなくては、という気持ちになります。
(1)南アフリカ出身の作家。1923年生まれ。1991年にノーベル文学賞を受賞。
(2)Sisulu, Elinor, Walter & Albertina Sisulu: In our Lifetime,New Africa Books, 2011
(3)Jaffer, Zubeida, Our Generation , Kwela Books, 2005