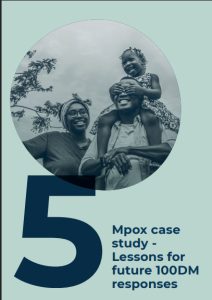『モザンビーク解放闘争史~「統一」と「分裂」の起源を求めて』
インタビュー 著者:舩田クラーセンさやかさん、編集者:橋本育さんに聞く
『アフリカNOW』 No.77(2007年7月発行)掲載
「解放闘争史」というタイトルをめぐって
『アフリカNOW』編集部(以下、編集部): 舩田さんが執筆された『モザンビーク解放闘争史~「統一」と「分裂」の起源を求めて』(以下、本書)を通読してみて、特に舩田さんが各地を尋ね歩いたりインタビューを重ねた実証部分については、これからのモザンビーク研究にとってベースになるような成果をつくりだしているという印象を受けました。またその意味で、本書の「厚さ」もひとつの魅力にもなっていると思います。
舩田: 本書をネット書店で検索してみると、なんと「東洋政治」に分類されていました。ネット書店では東洋政治と西洋政治そして日本政治というカテゴリーしかない。ここでの「東洋」とは西洋以外のすべてを指しているという点で、このこと自体が一種のオリエンタリズムを表していますね。モザンビークがアフリカの国であるということがすぐに思いつかない人にとっては、「解放闘争史」という題名だけで、アジアのどこかの国についての本なのだろうと思ってしまうかもしれません。
橋本: 本書のタイトルは、実は小社(お茶の水書房)の社長が付けました。舩田さんは、別のタイトルをイメージされていたようですが、出版助成の申請(1) の前日の打ち合わせのときに、社長が30分ほど考えて、これしかないと言って、このストレートなタイトルに決まりました。メインタイトルにまず「モザンビーク」という国名が絶対に必要だろうという点は納得できるのですが、社長としてはどうやら「解放闘争史」という語句がなによりも気に入っているようです。
舩田: 実は本書のサブタイトルの方が、私の博士論文のメインタイトルの主要部分でした(笑)。博士論文のタイトルにも「モザンビーク」という国名と「解放闘争」という言葉は入れていたし、ほとんどのページで解放闘争に言及しているので、本書のタイトルが普通にわかりやすいものであることは間違いないでしょう。しかし、私としては解放闘争史を書きたかったわけではありません。それでも結果として見ると、解放闘争史を書いてしまったということになりますね。また、今まで日本ではモザンビーク研究の基礎になる本を誰も書いていないから、そのこともふまえて本書を書くしかなかった、だからこんな厚さになってしまった、という事情もあります。
編集部: 解放闘争史という言葉からは、東西冷戦の時代において西側の支配からの解放をめざすということがまずイメージされ、モザンビークにおいてもFRELIMO(2)はこうした解放をめざしていたといえます。本書は、FRELIMOを支持する立場から書かれたものではありませんが、「解放闘争史」というタイトルがメインになることによって、タイトルと内容に落差があると受けとめられることも考えられませんか。
舩田: 確かに「解放闘争史」というタイトルからは、FRELIMO のために書いた解放闘争史であると受けとめられることも少なくないでしょう。しかし私は、FRELIMO のためでもRENAMO(MNR)(3)のためでもなく、草の根の人々に視座を置いた<解放闘争史>を書こうとしたのです。さらに、国際関係とのつながりや南部アフリカ地域という視点も重視しました。つまり、「分析の対象としての解放闘争」を取り上げたつもりです。その意味では、「21世紀型の<解放闘争史>」と呼べるかもしれません。
現在においてもまだ、あるいは現在ますます、アフリカの解放闘争史を研究することは危険性を伴っています。ジンバブエやタンザニアはそのような例といえます。モザンビークでも、こうした危険性がまったくなかったとはいえませんが、モザンビークでは学問に対するオープンな姿勢があったので、他のアフリカ諸国と比べて、もう少し自由な環境で解放闘争史を研究することができました。なぜモザンビークにこのような学問的風土があったかというと、モザンビークが独立した直後、外国から協力者として大量に来た人びとが理想に燃えてモザンビークの学術機関を創設したという歴史があり、オープンな議論と実証を重視する傾向が現在でもある程度保たれているからです。こうした人たちは今でも大学などに残っており、その人たちがいるからこそ多くの資料が集められ、自由に閲覧することもできました。
しかし、これがいつまで続くのかはわかりません。事実、私が博士論文を書き上げた前年(2005年)から、文書館などでFRELIMO 文書を自由に閲覧することはできなくなりました。この事情の背景には、解放闘争史を自由に研究されることに対するFRELIMO 政権側の危機感があるのかもしれません。どんな活動でも失敗はつきものです。それが当然なのですが、権力の根拠が闘争にあるとなると、失敗は都合の悪いものとなります。私がFRELIMO 文書を閲覧することができるようになるまで7年かかりました。長年の信頼関係の構築なしには、資料室内に立ち入ることすらできなかったのです。閲覧できるようになってからは片っ端からFRELIMO 文書を読んでいったのですが、こうした作業はもう自由にはできなくなりました。
時代の変化と研究、という意味でいうならば、私がモザンビークでの調査を開始した1990年代には、モザンビークの1960年代から1970年代の解放闘争を経験した人々が多数生きていて、直接いろいろなことを聞くことができました。しかし、その半分以上の人たちはこの世にもういらっしゃいません。このように、私が大学院生のときに与えられていた機会は、私より若い研究者にはもうないということを実感しています。
モザンビークにおける「統一」と「分裂」
編集部: 本書のサブタイトルは『「統一」と「分裂」の起源を求めて』になっていますが、本書の中では最初の先行研究に関する論考以外の箇所では、「統一」自体についてはあまり触れられていませんね。この点については、舩田さん自身がまだ整理しきれないのでいるのか、それとも今後の課題として残っているのでしょうか。
舩田: この点は、自分自身の整理の問題を越えている…というのが感想です。解放闘争開始から45年、独立から30年が経ちますが、この課題は当初(特に1960年代に)考えられていた以上に難しい、というのが実情ではないかと思います。本書は、この困難な課題を考える糸口を、かつて目指された「統一」、その過程で生じていた「分裂」から探ってみる、ということをめざしています。外部者の私が、「統一」の未来像など示せるわけはないので、まずは歴史的展開から再考してみようとしています。
当然ながら、解放闘争期にモザンビークでめざされた「統一」があります。そのことは、本書の第3章と第4章で詳しく取り上げた通りです。独立直後には、この「統一」思想の影響がモザンビーク政治のあちこちに見受けられましたが、現在ではこの「統一」自体が大きな問題をはらむものとなっています。
モザンビークの特殊な事情として、「統一」と言う場合、「白人や混血をどう取り込んでいくか」という問いが、「アフリカ人同士の違いをどう乗り越えるか」と同様に重視される傾向があげられるでしょう。解放闘争期、「白人も、混血も、アフリカ人の異なった『部族』同士も、違いを乗り越えられる思想」として、社会主義が重要な役割を果たしました。「いかなる人種であろうとも、人間による人間に対する搾取は許されない」というスローガンが繰り返されたわけです。つまり、モザンビークの「統一」とは、社会主義の志向を帯びたものでした。では、アフリカ人同士の激しい殺し合いに至ってしまった独立後の武力紛争を経て、そしてポスト冷戦期の現在、このような傾向を帯びた「統一」を「統一」の中身として語ることができるか、というとそれは難しい。モザンビーク人自身がそう感じている。
FRELIMO の書記長であったモンドラーネ(Eduard Mondlane)や独立後の初代大統領のマシェル(Samora Machel)は生まれながらのアフリカ人ですが、彼らを支えた思想的バックボーンには、やはり混血の人たちや白人左翼の強い影響が見受けられます。望むと望まないとかかわらず、彼ら自身が西洋文明の中で育ち、モンドラーネの妻は白人でした。こうした指導者によって達成された独立や革命は、農村部の大多数のアフリカ人にとってはとても遠い世界での話でしかなかったのです。本書は、そのような特徴を帯びた地域社会に視座を置いて、モザンビーク史の展開を見つめたものです。限界の一方で、混血の人たちや白人左翼がいたからこそ、モザンビークの解放闘争がまとまって進展してきたことも事実です。この人たちが自分のためではなく、もっと高い理想のために自分の命を捧げて闘っていたからこそ、独立が達成できた。しかし、モザンビーク農村の現実と運動の目指しているものの間には乖離(かいり)があった。現在のモザンビークもこうした「ねじれ」を抱えていて、多様性のどこに焦点をあてて「統一」していくのかということが問題になっています。
また、「統一」の議論で重要な点に、「モザンビーク」という枠組みが上から与えられている点が関わってきます。この枠組みはそこに暮らしている人々が選んだものではなく、あくまで周辺の旧英国領植民地とポルトガルの綱引きの結果として線引きされたものでしかない。つまり、モザンビークの国家的特徴は、「英国領ではない点」や「ポルトガルの植民地であった点」に集約されてしまう傾向にあります。例えば、「ラテン的な点」、「ポルトガル語」、「混血性」、「人種融合」などです。しかし、これはかつてポルトガル植民者がレトリックとして利用していた特徴でもあり、この特徴を強調することは、現在のモザンビークでは注意が必要です。かといって、先に述べた「社会主義」も、現在のモザンビークにおける「統一」のめざすべき思想とはなっていない。つまり、モザンビーク人自身が今、「模索」の時期に入っていると言えます。「敵」である植民地権力があった時代より、「統一」を口にするのは難しい状況です。
「モザンビーク」が「モザンビーク」として「統一」し独立するということは、日本のわれわれが考えるほど自明のことではありません。モザンビークの人々は、上から与えられた枠組みに疑問を感じながらも、主体的に選び取って、そこから一歩を踏み出さざるをえなかったという複雑で困難な事情を抱えています。その試みは、つまり「モザンビークという国」の形成は、実質的には、今から30年前の1975年の独立のときから始まったばかりのものという点は強調して良いでしょう。
また、モザンビークの独立は、FRELIMO の軍事的・政治的な勝利の結果としてもたらされたものであるというよりは、当時の国際情勢、特にポルトガルのサラザール・カエターノ政権の崩壊(1994年)という要因によって、いわば「棚ぼた式」に達成できたという事情も関わっています。つまり、「統一」の試みが道半ばで、モザンビークは独立に至った。そして独立後には悲劇的な武力紛争が勃発しました。本書は、解放闘争と独立後の武力紛争の「断絶」ではなく「連続性」に注目して、「統一」の課題がいかに以上に述べた内的課題だけでなく、外部状況的(冷戦構造、脱植民地化、アパルトヘイト体制)にも難しかったのかを明らかにしようとしています。
モザンビークの現代史において「統一」と「分裂」は常にテーマであって、今後もこの点については変わらないでしょう。このこと自体は、モザンビークだけでなくアフリカのどの国も直面していることですが、モザンビークの場合、そのことを30年におよぶ武力・暴力状況の下で問われざるをえなかったという事情があります。私がモザンビークの文脈で「統一」を固定的に捉えないようにしているのは、FRELIMO がいう「統一」の限界が歴史的に明らかだからです。独立後にFRELIMO が「統一」を強調するとき、その背後には「排除」の論理が隠されていました。そのことと、後の武力紛争は密接に関わっている。だからといって解放闘争時にFRELIMO がめざそうとした「統一」が駄目だった、といっているわけではありません。「統一」は時代ごとに、その時代に明らかな課題に直面し、それを乗り越えようとする人びとの試みの数だけあり得るものであり、外部者のわれわれがそれを固定的で所与のものとして掲げることは望ましいことではない、と言いたいのです。
編集部: モザンビークでは、1975年の独立そして1992年の和平合意以降にも政権の座にあるFRELIMO による「集村化」=急速な農業化路線があり、その失敗について、また「集村化」に対する反発が反対勢力とへの支持だけでなく武力対決にも結びついていったことについても、本書では語られていますね。
舩田: モザンビークの場合、「集村化」の問題も「統一」と「分裂」をめぐる問題と切り離して考えることはできません。日本の研究者の多くは、例えば中国における人民公社などの「集村化」の問題を戦争と切り離して、生産手段や社会主義の理念の実現の一形態として語っています。しかし中国においても、人民公社を対日解放戦争と切り離して議論できるでしょうか。
モザンビークの植民地解放闘争時におけるFRELIMO の「解放区」は、独立後も「共同村」(4)の実験の場であり、「解放区」が解放のためのオアシスのような場所であったかというと、村人に聞くとそうでもなかったようです。解放戦争に勝利するため、解放や防衛のためという理由で住民の自由や主体性を制限し、住民の行動を縛っていくことにもなっていた。植民地解放闘争時の「解放区」に生じたこの矛盾を抱えたまま、独立後には国家の政策として、FRELIMO 政権は「共同村」政策を導入しました。この政策は、同政権が掲げていた社会主義の理念を実現するための手法として導入されたことになっていますが、私はそれだけではないと考えています。植民地権力にとっても、解放勢力にとっても課題であった、広大なモザンビークに散らばる農村住民をいかに効果的に掌握するか、という点に関する不安を解消するために、この政策を導入したと考えています。そしてこの「不安」は、独立時にFRELIMO が「統一」を達成できていない、と認識していたが故に強く感じたものであることは間違いないでしょう。更には、独立直後に紛争が勃発したことも、この「不安」を的中させることになってしまいました。
本書では、モザンビークの中心地となっている南部や都市ではなく、最も辺境の地(北部)の農村住民の視点からモザンビークの近現代史を問い直しています。「植民地解放闘争=栄光なる解放闘争史」も、直接住民の話を聞いたり、その後の現実を考えると、やはり暴力でもって「統一」をめざさざるをえなかったことが後に残した問題は、乗り越えがたいほど大きかったといわざるをえません。国家レベルの政治からすると「美しい」話も、草の根の人々からみると、消し去りがたい亀裂をもたらした話となります。例えば、解放闘争の「裏切り者」の扱いは、FRELIMO の公式見解、つまりは独立後の国史での描かれ方と、地域社会での捉えられ方とは大きな違いがあります。これが歴史観の問題に留まらない理由は、FRELIMO が独立後一党体制下で権力を握る中で、この歴史観に基づいた政策を実施したことによります。具体的な事例としては、本書で扱ったモザンビーク北部に暮らすマクア・ロムウェ人の扱いがあります。確かに、武装闘争を選ばざるをえなかった時代状況があります。冷戦、ポルトガルの独裁政権、アパルトヘイト体制などです。その意味で、日本もまた責任を負っています。また、他のアフリカ諸国と異なり、武力闘争を経たからこそ得られたナショナリズムの基盤ということもできるでしょう。しかし、草の根レベルに解放闘争期の暴力の経験が根強く残り続けたことは事実であり、後へのその影響については無視できるものではありません。
ただし、このことは、「分離・独立」といった国家レベルの話とも異なります。本書の図3「紛争終結時におけるRENAMO 統制地の分布状況」を見るとはっきりしますが、ある州や地域がまとまってRENAMO統制地になっているというよりは、全土的にスポット状態でRENAMO の統制地が存在していました。現在はこのスポット状態がもっと細分化されていて、「分裂」がより根深くなっているし、個人化しているともいえます。
その結果、国家的プロジェクトである開発政策や援助から、特定の人々が取り残されるという問題が発生しています。例えば、生活に不可欠な水、学校、保健センターなどが、RENAMO 支持者の多い場所からわざと離れた場所に設置される、RENAMO 側の人たちがつくった学校が壊されて、その後にオフィシャルな学校がFRELIMO 側にいった人たちの居住地につくられる、といった事態が生じています。この結果として学校にも行けなくなると、今度は政権側から「今住んでいる場所を出て、新たな場所に住めばよい」と言われてしまう。これは、まさに「集村化」の論理ですね。こうしたことがずっと行われてきて、排除の論理が末端の生活のレベルまで行き渡っていて、国家から見捨てられた人々が生じてきたのです。
「独立という名の平和と繁栄はまだ到来していない」
舩田: 本書の最初に「独立という名の平和と繁栄はまだ到来していない」という村の女性の発言(5) を引用していますが、この一言こそが、モザンビークの現在を象徴しているといえるでしょう。人々が口にする「独立という名の平和と繁栄」には、「国家(6)に保護してほしい、戦争や飢えから解放されたい、平和の下での繁栄を期待していた」ことが表されています。しかし現実には、人々は、自分を保護してくれ平和をつかさどってくれる国家というものを経験していない。独立後の国家が持ち込んだものは戦争や飢えじゃないか、植民地時代にも戦争や飢えはあってもこれ程ひどくはなかった、という気持ちにならざるをえないのです。
私にはこの言葉が、国家との関係で響くものがありました。踏みにじられっぱなしの側の言葉を聞いてしまったからには、決して国家権力の側にいってはいけない、そう感じました。だからこそ私は市民社会にこだわって活動してきました。国家の側からは決して見えないものがあり、国家権力というものが踏みにじってしまうものに視座を置いて、生きていこうと思いました。実は、私の研究の中身と活動の中身は、実は直接リンクしてないのですが、このこだわりだけは一貫しています。
自分自身の経験を振り返ってみると、この草の根の人々の「平和と繁栄」の希求に個人として応えようとしたときもありました。今思うと、それは奢(おご)りですね。国連PKO 活動に参加したりしましたが、やはり私には帰る場所があって嫌になったら逃げられるし、給料がなくなったらいないかもしれないと考えてしまう。しかも、本書を書いてもなお私自身は「よそ者」であり、草の根の人々の気持ちがわからない、わかるわけがないということを強く意識しています。それでも人々の願いを聞いてしまい、その願いに応えようとしない権力の姿を見てしまった以上、とことん「よそ者」として関わる道筋とは何だろう、と考えるようになりました。そこで行き着いたのが「自分の社会」、つまり日本、NGO 活動でした。
その一方で、実はこうした関わり方の限界も率直に実感していて、やっぱりアフリカに行って何かしたい、以前は草の根の人々のためだとか、その中に入り込んで何かをやろうとしたから限界が見えたが、今度は「よそ者」として草の根の人々とできることをやってみたくなったのです。これは、2008年にTICAD IV(第4回アフリカ開発会議)が終わるまでは「おあずけ」状態ですが。当面は、日本でできることをやるしかないでしょう。また、やるべきことも多い。私自身は研究者で大学という場で教育に関わり、かつNGO のメンバーでもある。私の立場からすると、NGO のメンバーと研究者は、同じものをめざしている割には手法が違う、何となくリンクされていないと実感しています。もっと両方を兼ねる人が増えてくればよいと期待して、活動しています。
橋本: その点に関して、私がアフリカ学会の学術大会に参加したときの印象を思いだしました。私が参加したことがある他の多くの学会の学術大会では、研究者・院生、そして出版社の営業担当・編集者が少しだけ加わるという状況でした。しかしアフリカ学会では、研究者だけでなく、NGO 関係者は当然のように参加しているし、さらにジャーナリストや行政官、しかもアフリカの行政官も参加している、こんな学会は始めてだと思いました。私自身は、アフリカの研究者の割と多くの方は、同時にNGO 活動にも参加されているという印象を持っていたのですが。
編集部: 舩田さんは1994年に始めて国連ボランティアという立場で、モザンビーク北部ニアサ州の農村部に国連平和維持活動(PKO)の選挙支援担当官として行かれましたね。本書の「はじめに」ではそのときの経験を振り返ってみて、紛争地となった地域の住民と話す機会が多くあったにもかかわらず、「今分かることは、この時点の筆者にとって、何を聞いても実際は『聞いていなかった』に等しかった」と書かれています。そしてこの記述に続いて、10ヵ月の任期を終えてニアサを離れる小型飛行機の上で、次はどこの任地に行こうかと期待をもって話し合っている同僚の一方で自分は、ニアサで出会った人々の沈黙の奥に何が沈んでいるのかを考えていた、とも述べられています。この経験を通じて舩田さんは、PKO やその下での平和構築への理解とはかけ離れた、草の根の人々が容易には語りえなかった何かがあるという直感を持たれたようですね。
舩田: その直感がどこから来たのか、なぜそのときに立ち止まれたのか。このことを改めて問い返してみると、やはりそこには個人的なことが関係しているのだと思います。自分の生まれとか育ち、女性であったこと、学校と闘ってみたことがあったこととか、そうした個人的な事情があって、そのとき直感的に「まずいことをしようとしている」と思い当たったのです。当時の私が、PKO による平和構築の道筋に納得していたわけではありませんでした。納得していなかったからこそ、実際はどうなのだろうと見てみたかった。第三世界を一人旅していた経験からも、PKO によってカンボジアなどでは順調に平和構築がすすんでいるといわれても、直感的にそんなことはありえないのではないかと思っていました。また当時は大学院生だったので、論文の素材としてPKO の現場を見てやろうという気持ちもありました。実際、直感どおりであった一方で、そのような国際的な平和構築への関与や努力の重要性も認識しました。だからこそ、草の根の人々の主体性と国家や「国際社会」のギャップをまずはきちんと押さえたい、そう思ってこの本を書きました。
本書の書かれ方/読まれ方―次の世代に伝えるために
橋本: 私は本書を読んで、文献や資料が限られていたからなのかもしれませんが、政治家や紛争の当事者だけでなく、現地の人々への聞き取りがかなり多く、しかもそれが巧みに配置されていることがまず印象に残りました。聞き取り調査やインタビューが多い場合、本の構成の仕方として、ある人物に託して理想や問題を語ったり、ストーリー性をもたせるという手法がありますね。こうした手法はドキュメンタリーやルポルタージュではよく使われることですが、研究書でもそうした手法を使って大部なものを読ませるということはよくあります。それに比べて本書では、これだけ多くの人たちから聞き取りをしているのもかかわらず、その人たちにはもたれかからずに、淡々と人々の証言を使っている。聞き取り相手とのこうした距離の取り方は、大部の著書を読ませるという点では不利かもしれませんが、私自身は気に入っています。本書から躍動感をもらってはいけない、本書で描かれている歴史を日本の読者は楽しんではならないのです。
舩田: 容易に手に入る資料に依拠して、感情移入して書くのは簡単です。ある時代のある一面だけをみて本を書いても、それは事実とは相当異なったものにもなりかねない。それだけでなく、歴史を誤って誘導してしまうことにもなります。私が研究する過程で知りたかったことは、そのとき現場でどうであったのか、それはなぜなのか、ということです。この「なぜ」の答えは、その時代の現場にのみあるわけではありません。それこそ、国際政治や150年前の歴史に遡(さかのぼ)ることも重要でした。そのことも、本書を「堅い」ものにしてしまったかもしれません。
現場でいろいろな話を聞きました。聞き取りを始めてから4年ほどは、本当に何も書けなかった。聞き取ったことを人に話すことも、研究報告をすることもできなかった。やろうとすると、泣いてしまう自分がいました。植民地支配、30年の戦争の経験を一人一人の経験に落とし込んだ話として聞いてしまうと、それはあまりにも重かった。当たり前です。自分に子どもが生まれるまで、この聞いてしまった「重さ」を他者である私のような者がどうしたらよいかわからなかった、途方に暮れていた、といえます。その時期実は、特定の人の苦悩に入り込んで書こうとしていました。しかし、あるとき気づいたのです。そうしてしまうことで、その人が抑圧したかもしれない相手の苦悩にはたどり着くことができなくなってしまう、という可能性に。解放戦線で闘っていた人がもしかしてすぐ横の住民を殺しているかもしれないし、実際そうしたことはいくらでもありました。そういう時代だったからこそ、どんな人に対してもその人に寄り添ってはいけない。もしかしてその人が言っていることと実際にやっていることが違っているかもしれない。今度はその人が言っていることを調べざるをえない。そうするとまた違った話がでてくるかもしれない。人々の語った言葉に入り込んでしまいたいところをあえて押さえ込んで記述に組み込んでいくと同時に、誰であってもその人の話したことが事実なのかどうか「裏」をとりまくりました。そうすると、そうではない話がどんどん出てくる。だから人々の証言だけでなく、警察のもの、軍のもの、植民地行政官のもの、活動家のメモなど、書いてあるものもとことん探すようにもしました。また、書いてあるものについても、本人に会いに行ったり、そのとき一緒にいた助手や被対象者を探し出して、「裏」を取りまくりました。
なぜそこまでしたのかというと、これはすごく「ヤバイこと」を扱っているという自覚があったからです。現代アフリカ政治の根幹は植民地支配から独立に向かう時期にあって、野党であれ与党であれ、いつも独立のときの正統性に戻って自分の立場を主張しようとします。そして、この時期のことはわれわれと関わりのない話では決してない。冷戦期のことですから。徹底的に学術的に、歴史的に調査することで、私が聞き取りをした人にも、私に資料をくれた人にも迷惑がかからないようにしようとしました。危険はまったくないわけではないですが、それでも、今気づいていることは言っておかなければならないと自覚していました。
このような政治的な難しさと聞き取った内容の重さから、長い間書けなくなってしまいました。でも私は「書かなければ」ならなかった。聞き取りをした人たちの時間を奪って、辛い記憶も思い出させて、さらに家族のサポートももらっているし、調査には日本の皆さんの税金も使っているからのですから、ともかく「書かなければ」ならないのです。まあ何とか書けたのは、モザンビーク・ニアサ州のマウアという空間に焦点を絞って、その中の小さな村の人の移動を中心に書いたからからかもしれません。その範囲であれば、人の言葉ではなく動きを追うことができましたから。
編集部: 橋本さんが先ほど「本書から躍動感をもらってはならない」と言われましたが、編集者としては、そのことに困難さを覚えられませんか。読者は本を読んで何か自分でわかるものを引きだそうとするし、編集者にとっては魅力を覚えるところがあるからこそ本を出版したいとか、売れるのではないかと、通常は考えるでしょう。そこをいわば自制しながら編集作業を進めていくといくことは、とても大変な作業ではないかと推測しますが。
橋本: 今、現代沖縄に関する研究書を書いてもらおうと企画していますが、私としては「おもしろく」書いてもらおうとは思っていません。なぜならば、自分の目の前にいる沖縄の人々あるいは東京などに在住している沖縄出身者のことを考えたときに、東京の出版社が「おもしろく」書いてもらった本が売れたとしても、そのことを通じて、政府から沖縄にこれまで交付された何兆円というお金の流れ方から生み出されたものに協力するようなことをしたくないからです。沖縄の人々からみても「きつい」本になるかもしれませんが、よそ者である東京の出版社が沖縄の本を出版するときには、「節制」するということがとても重要だと考えています。ただ、もちろん著者とは、より多くの人に読んでもらうためにどう工夫すべきかは、ずっと話し合っています。
舩田: 私としては、モザンビークを担う次の世代の人々にこそ本書を読んでほしい。だから本書を英語とポルトガル語に翻訳することは、私の中ではすでに決まっています。いろいろな事情でとりあえずは日本語で書きあげてしまいましたが、日本語版しかないままでは、これまで10年以上も私の研究・調査を支援してくれたモザンビークの皆さんに応えることができません。だから、英語版とポルトガル語版を出さないと本書は完結しないのです。
一方で、本書の英語版とポルトガル語版を出した後で、もっと一般の人向けのものも書きたいとも考えています。本書を書くときには、自分自身でも慎重すぎたという思いもあります。1行ごとに、「この1行に書いていることに私がどれほどの責任を負えるのか」、と自問自答を繰り返しながら書きました。その結果、「注」の数は全部で1,300 くらいになってしまいました。それは学術本としては当たり前のことなのですが、しばらくしたらもっと普通に読んでもらえる本を書こうとも考えています。
最後に
橋本: 私は、本書をポスト・コロニアリズムの本として宣伝することを提案してみましたが、舩田さんは、それでは植民地支配の批評になってしまうという理由で反対されました。しかし私は、ポスト・コロニアリズムの研究者にこそ本書を読んでほしいと思います。舩田さんの慎重さは、単に事実をきちんと確認したいからということだけでなく、ポスト・コロニアリズムの批評性をもって、植民地主義を経てきた世界の歴史と現在を研究されているからこそ生じてきたものだと受けとめています。ポスト・コロニアリズムの研究者には、この慎重さをもってして、これだけの歴史書ができるんだということをわかってほしい、この人たちにこそ本書を読んでほしいのです。文学から何から「楽しむ」でしまうというポスト・コロニアリズムの叙述スタイルに対して、実は私は疑問をもっています。そしてこの点からすると、このような節制された叙述スタイルの本が出ることの方が、しかも研究者であればこの抑制のきいた大部なものを読み続けていくことの方が大切ではないかと、私は考えています。そしてこの考え方からすると、数千部売れるような本はとてもつくれるものではないし、読まれるものでもない。でも、それは仕方ないことなのです。
舩田: 最後に、執筆が終わっての心境を。私は、ただ真実を突き詰めたかったわけではなかったし、しかも博士論文を書いているときは辛かった。ただ突き動かされるものがあってこれを調べ、書いたとしか説明のしようがない。現実を聞いてしまい見てしまった者としては、何が何でもこれを世に出さなくてはならないと、ほとんど信念に近い気持ちを抱いていました。また、執筆時はちょうど出産したばかりで、生まれたばかりの子どもの世話をしなくてはならない、子どもが寝静まったと思ったらまたすぐに泣きつかれてしまう、そんな大変さを抱えた時期でもありました。子どもが生まれるということはとても幸せなことなのに、書くときには喜んじゃいけない。モザンビークで出会った人々の歴史の重みを聞いてしまった者としては、辛くても書かなくてはならないという気持ちだけで、1行づつ書きすすんでいったのです。
本が出るということは、本来はうれしいことなのに、人々の生死の重さにまだ応えきれていないなという気持ちや、やり残した感ばかりが残っています。うれしいのに喜べないということは、「アフリカ好き」という感覚についても言えます。NGO やボランティア、一個人としては「アフリカが好き」という気持ちで物事を進められるのですが、研究者としてはその感覚が執筆の邪魔をしないようにと、必要以上に気を配ってしまったかもしれません。「アフリカ好き」という感覚にもたれかかって、そこで妥協したくなかった。アフリカは多様で、日本から遠くて、日本にはあまり類書がないからという理由で、感覚に頼った書き方をするという妥協をしたくなかったのです。が、先ほどの話に戻りますが、今度は「アフリカ大好き」という気持ちで何か書いてみたいです。
若い研究者へのメッセージですね。(私も「若い」つもりなのですが…。院生ということですね、はい。)私が大学院生のときに、東アジアの現代史を研究している院生や先生方の叱咤(しった)激励が一番刺激になりました。アフリカ研究には、史料や先行研究の限界がどうしてもつきまとう。「遠い」という理由から、日本では結構、乱暴で大雑把な議論がまかり通りがちです。でも、そのレベルに安住してはいけない、という点を常に自覚させられました。大変なことかもしれませんが、次世代の皆さんには、資料・文献の調査にしてもインタビューや聞き取りにしても、本書での作業を最低限のレベルとして実施してほしいと考えています。(この「厚さ」にする必要はありませんが…。)
●インタビュア:『アフリカNOW』編集部 斉藤龍一郎、茂住衛
【注】
(1)本書の作成にあたって、独立行政法人日本学術振興会から2006年度科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の交付を受けた。
(2) モザンビーク解放戦線。ポルトガル植民地支配からの統一解放戦線として武装闘争を推進。モザンビーク独立後は一貫して政権与党の立場にある。
(3) モザンビーク民族抵抗。モザンビーク独立後16年におよぶ武力紛争を勃発させた反政府ゲリラ勢力。
(4) Aldeia Comunal。モザンビーク独立後にFRELIMO 政権が、農村部における社会主義政策の実践と戦略拠点の建設を目的として建設した集落。
(5) 本書2ページに掲載されているムホコ村の女性の発言。
(6) 国家といってもその理解は多様であり、例えば本書の著者が調査したマウア人の言語ではエラポ(elapo)と言うが、この言葉は国家を指すだけでなくチーフ領を指す場合にも使われる。
モザンビーク解放闘争史~「統一」と「分裂」の起源を求めて 舩田クラーセンさやか著 お茶の水書房 2007年2月 [amanzon]