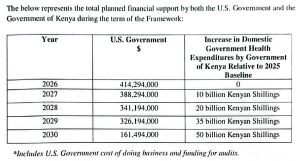『アフリカNOW』84号(2009年3月31日発行)掲載
執筆:茂住 衛
もずみ まもる:『アフリカNOW』編集部。AJF理事。近年、日本でもアフリカ映画やアフリカを舞台にした映画の上映の機会が増えたことを契機に、アフリカの映像表現やアフリカの描かれ方に注目している。
5月9日より東京・渋谷のユーロスペースにて公開されるドキュメンタリー映画『チョコラ!』。「チョコラ(chokora)」とは、スワヒリ語で「拾う」を意味する言葉だが、転じて、鉄くずやプラスチィクを集めたり、物乞いや小間使いをしながら生きるストリートチルドレンをさげすんで呼ぶ場合にも使われる。この映画は、このタイトルが示しているように、ケニアの首都ナイロビ(Nairobi)の中心部から北東約45Kmに位置する人口約10万人の街ティカ(Thika)を舞台に、この街で暮らすストリートチルドレンの姿を撮っている。
このように説明すると本作品の内容について、どうしても貧困や悲惨さと結びついたある固定的なイメージが想定されてしまうかもしれない。だが本作品は、ティカで暮らすストリートチルドレンの多様な姿をありのままに撮ることによって、この固定的なイメージとは異なり、貧困ではあっても、ケニアのストリートを舞台に、子どもたちの生きている時間を描き出すものになっている。
今年の2〜3月にかけてこの映画の試写会が開催され、筆者も鑑賞すると同時に、監督の小林茂さんと編集を担当する秦岳志さんにインタビューする機会を得た。このインタビューをもとに、制作者側からの本作品への思いと、筆者が感じた魅力について紹介してみよう。
本作品は、小林さんが、1999年からティカでNGOモヨ・チルドレン・センターを運営する松下照美さんに、「ティカの子どもたちを撮ってくれないか」と依頼されたことがきっかけになり、2008年春に完成した。腎不全の病を抱える小林さんは、松下さんからの依頼を受けて、人工透析が必要になる前にティカでの撮影に入ろうと決断。2006年6月から約5ヶ月をかけて現地での撮影が行われた。「撮影前から、松下さんを主人公にしたモヨ・チルドレン・センターの宣伝映画にはしない、ストリートで暮らす子どもたちのありのままの日常を撮る、ということは決めていました。しかし、実際に現地に行ってから、そのことがいかに大変なことなのかに気付かされましたね。ストリートで暮らす子どもたちと関係ができて、実際に子どもたちの日常生活を撮ることができるまでに時間がかかり、相当にあせりました。松下さんとモヨ・チルドレン・センターに集まる子どもたちだけで完結した作品をつくるのであれば、すぐにでも撮影を開始することができたでしょう。しかし現実には、子どもたちは街中のストリートで暮らしています。子どもたちの日常と子どもたちを取り巻く世界を描くためには、ストリートで生きる子どもたちや街の人たちとの関係をつくり、撮影する自分たちのあり様を認めてもらわなければならない。そのためにはまず、毎日毎日子どもたちと一緒に歩く、食堂など人々が集まるところに片っ端から入って、自分が何をしているのかを説明することから始めました」と、小林さんは語る。
撮影期間は約5ヶ月間だが、実際の映像のほとんどは、最後の1ヶ月くらいで撮影。また、知り合った子どもたちに撮影することを了承してもらっても、実際に撮影をはじめようとすると、「お前たちがいると警察に目立ってしまう」と抗議され、ケニア政府の撮影許可書が出るまではいっさい撮影しないと約束したこともあった。「撮影は一時中断しても、その間に一人でカメラも持たずにティカのスラムにある学校を訪れたり、モヨ・チルドレン・センターで行われているサッカーの練習などを通じて、子どもたちに新たな仲間を紹介してもらったりしていました」(小林さん)。
ある被写体を撮るために、その被写体との関係をきちんとつくる。ドキュメンタリー映画をつくるためにはごく当然のことであったとしても、実はこれこそが最も困難なことなのかもしれない。本作品では、撮影される側が会話の途中で撮影している側にも話しかけるという場面が何度も見受けられ、この場面がまた、両者の関係のあり方を示唆するものになっている。逆にこうした関係性が軽視され、作り手の意図や主観だけで一方的に撮られた作品は、その被写体に対するある種のステレオタイプのイメージを繰り返すだけにとどまってしまうのではないか。
本作品を編集した秦さんは、撮影開始前から編集を担当することに決まっていたそうだが、撮影現場には同行していない。それは、「撮影現場に行くと妙な思い入れが生まれてしまい」、編集者として「第三者的な目で見たときにどのように見えるのかを監督にぶつけていくという仕事がやりにくくなる」(秦さん)ことを避けるためでもあった。だが秦さんは、本作品の制作と編集の過程において、通常の編集者以上に、実際には体験していない撮影現場に「思い入れ」を抱いてしまったようだ。被写体の子どもたちとの関係性が映し出された120時間分の映像のどこをカットして、どのように構成して映画作品に仕上げていくのか(公開作品の長さは1時間34分)。それは、スタッフと延々と話し合いながら、その場その場であるシーンをつくっては壊し、壊してはまたつくる、という作業の繰り返しであった。「こうした作業を何十回も繰り返して行く中で、自分たちがどこに引っかかっているのか、どのようなシーンや瞬間にひかれたのか、それは映画として魅力あるものになっているのかなどが見えてくる。それでも最後の最後になって、全体の構成ががらっと変わるという可能性も常にあります」と、秦さんは語る。
筆者が特に印象に残っているシーンを紹介しよう。ティカにあるキャンドゥドゥ・スラムに最近移り住んできた女性と二人の子ども。三人で一つのベッドに潜り込むと同時に、最初はとてもかすかに(しばらくは、映画の音声だと気付かなかった程だ)、そして徐々にはっきりとした音で、家の外からのスラムの夜の喧噪が聞こえてくる。その喧噪に包まれている時間は、「私」の記憶と結びついて、その瞬間の「幸せ」を呼び起こすものになった。
ケニアのストリートチルドレンを撮ったドキュメンタリー映画であるために、貧困やエイズ、子どもたちに拡がるシンナー中毒などの問題があることは、映像からいくらでもかいま見えてくる。この女性にしても、HIV感染を抱えながら、昼の洗濯仕事だけでなく夜も働いているのだ。だが本作品は、こうした問題の存在も人々の生きる場に包み込むことで、幸せも不幸も、楽しさも苦労もある生の実感を、観る側にも想起させるものになっている。
このことを象徴しているのが、本作品の最後になるが、夜の路地裏で、子どもたちがたき火にあたりながら、借りてきたペンキ缶でトマトピラフをつくって食べているシーンであろう。小林さんはこのシーンについて「外から撮るのではなく、中で一緒に火にあたっている人間の一人として撮りたい。そのようにして関係をつくっていきたいし、観客もその中の一人であるかのように感じてほしい」と語っている。かなりの強火で炊きあげられ、缶の底の方がお焦げ(というか、ほとんど炭に近い)になったトマトピラフはとてもうまそうで、誰かがトマトピラフに大麻を混ぜ込んだらしいのだが、子どもたちは底抜けに陽気で、お互いに取り合ったり分け合ったり、けんかをしたり仲裁したりしながら、トマトピラフにむしゃぶりついている。そのうちに、さっきまで鍋として使用していたペンキ缶をパーカッションにして、いつのまにか歌とダンスが繰り広げられる。
このシーンを観ながら筆者は、タンザニアのムアンザを舞台にしたドキュメンタリー映画『ダーウィンの悪夢』(原題:Darwin’s Nightmare、Hubert Sauper監督、2004年)で描かれた、ストリートチルドレンが食べ物を奪い合っているシーンを思い出した。このシーンで映し出されているある子どもの口を大きく開いたゆがんだ表情は、この映画のテーマを端的に象徴するカットとして、映画のフライヤーやDVDの表紙を飾っている。いずれも、アフリカの街で暮らすストリートチルドレンが食事をするシーンを撮っているにもかかわらず、この明らかな描かれ方の落差をどのように受け止めたらよいのか。『ダーウィンの悪夢』のこのシーンにおいて、撮影している側と撮影される側はどのような関係にあったか。たとえ一つの同じ風景をみていたとしても、実は違うものがみえていたのではないだろうか。