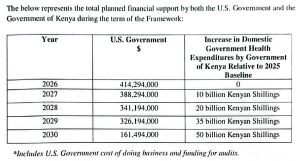‐Journey to Japan‐
『アフリカNOW』 No.21(1996年発行)掲載
昨年1月にセミナー・交流のゲストとして来日したジンバブエのNGO、PELUM Associationのジョン・ウィルソン氏が滞在中の日本旅行記を送ってくださいました。全29頁に渡るものですが、今月から連載でその抜粋をご紹介をします。彼の見た日本はどんなだったのか、西日本ツアーやセミナーに来られなかった方もどうぞご一緒に参加ください。
1996年1月12日
(飛行機の中で)正確に言うと、この旅は昨日から始まっている。昨日シトレ夫人(注:同じく来日ゲストのクリスチーナ・ツアンガニジさん。通称シトレ夫人と呼ばれている)をハラレの駅に迎えに行ってからだ。彼女の来訪は疲れきったわが家に-モザンビークからの長旅から帰ってきたばかりでみんな疲れていたのだ-元気を持ってきてくれた。この旅は彼女にとってはジンバブエの外に出る初めての旅なので、彼女はとてもわくわくしていたし、喜んでいた。
(ヨハネスブルグの空港で)我々はさっきからつるつるの床と明るいジョバーグ(注:ヨハネスブルグ)の空港でずっと待っている。日本人のミガタという女性(注:南アフリカの旅行代理店のスタッフ)が我々を迎えにきてくれて、もう一人のゲストミセスモヨがブラワヨから到着したら3人でトランジット用に予約したホテルに向かうことになっている。
ところで、飛行機から見たハラレ周辺はまったくの緑一面であった。リンポポ川は水が流れていると言うより、ただの地表が見えていたと言ってもいいほどであった。ジョバーグに近づくにつれて、町の全景が見えてきて、生活のスタイルのコントラストを映し出していた。
1996年1月13日
(ホテルにて)昨夜はとうとうミセスモヨ二に出会えなかった。彼女はどうやら南アフリカに入国するトランジットビザを取得してなかったらしい。入国が認められなかった為、彼女は空港の中で一夜を過ごさなければならなかったようである。シトレ夫人と私はホリデイ・インに泊まった。どの部屋にもラジオとテレビがベッドサイドにおかれていて、いごごちが良い。ドアのキーはカードになっていて、鍵の代わりに差し込むようになっている。私にも、シトレ夫人にも初めて。
(飛行機の中で)もう45分もキャセイパシフィックの機内で離陸を待っている。シトレ夫人も私もまた窓際の席を確保できた。運が良く隣2席も空いているのだ。(やった!これでぐっすり眠れるぞ)実はさっきまで隣に若いひどく人種差別的なオーストラリア人の男が座っていたのだ。彼は席につくなり、私に「ひとつ後ろの黒人の女性の(シトレ夫人のことだ!)隣に座らなきゃいけないのかと思っちまったよ」と言ったのだ。おかえしに言ってやった。「君が隣に座らずにすんで彼女にとって本当にラッキーだったね」と。彼は困惑したようだった。そして空いている席を見つけて安っぽい小説を読みに席を移ってしまった。
ミセスモヨにはまだ出会えていない。私は機内を歩き、ミセスモヨらしき女性何人かに声をかけてみたけれど、みんな人違いだった。彼女が機内にいることをただ願うだけだった。ミス・ミガタが昨日のうちに彼女の居場所を教えてくれればよかったのに。
1996年1月14日
ようやく香港についた。実に長い旅だった。特に私の時間の感覚がおかしくなってしまったからだろう。ここでは朝の9時なのだが、昨日までハラレはまだ、夜中の3時なのだ。飛行機はほとんど海の上を飛んでいた。こんなに長い間地上を見られなかったことには本当に驚いた。機内にある地図では飛行機はそんなに海岸から離れて飛んでいるようには見えなかったから。
香港から東京に向かう飛行機の中で、だんだんと東洋にいくのだという気持ちになってきた。機内の乗客の顔つき、配られる時間や雑誌の字:あれが読めるなんて奇妙だったらありゃしない! 機内食もほんとうに東洋の香りだった。あるソースをかけただけで、口のなかが吹っ飛びそうになった。あとで分かったのだが、別の液体の中に混ぜるのだったそうだ(注:わさびのことか?)東洋の人の国籍なんて顔からはまったく予測がつかない。実際可能かどうかも不思議だ。飛行機はずっと厚い雲の上を飛んでいた。何も見えない。くしゃみがとまらない。花粉症のせい。フライトは本当に長く、世界の向こう側に行くのだという感じ。突然、今の自分の周りの文化と自分自身の文化とがどれほど離れているのかを感じた。今までそんなこと考えもしなかったが、そう思っているうちに、窓から富士山が見えた。東京に近づいているのだ。山の形が火山であることを示している。雲の飢えに頂上がでていて、山頂は雪で覆われていた。そうそう、香港でようやくミセスモヨに出会えた。ほっとする。