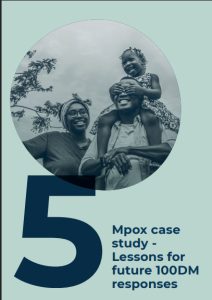-映画「薬はだれのものか」から何を学ぶか―
2017年4月 国際保健部門ディレクター 稲場 雅紀
1.「薬は誰のものか(Fire in the Blood)」公開の意味
2013年のワシントン国際映画祭社会正義賞を受賞したドキュメンタリー映画「薬は誰のものか(Fire in the Blood)」の日本語版が、アジア太平洋資料センター(PARC)によって製作され、2017年の今、日本で公開されることは、大変大きな社会的意義のあることである(※)。
この映画は、サハラ以南のアフリカなど、「途上国」=南の世界におけるエイズの猛威が極限に達した2000年前後に、途上国でのエイズ治療実現の門を閉ざした知的財産権(特許権)の世界化と、人命の損失を無視して知的財産権による利益に固執した先進国の新薬開発系製薬企業の問題を暴き、治療薬へのアクセスのために身を賭した南アフリカ共和国のエイズ活動家、ザッキー・アハマットらの闘いを描き出している。
ときは2017年、この映画が描き出した時代から十余年がすでに過ぎ去っている。しかし、治療アクセスと知的財産権をめぐる闘いは終わったわけではない。むしろ、2017年の地平に立つ私たちは、当時と様相を大きく異にするかたちで、数年前に始まったこの闘いの「第2幕」の渦中にいるということができる。
「第2幕」の時代背景は、以下のとおりである。ここ十余年で、アフリカをはじめとする途上国では、曲がりなりにも1500万人以上がエイズ治療薬にアクセスできるようになった。HIV陽性者をはじめとする当事者や市民社会のグローバルな闘いが、世界を動かした。この数字は、闘いの成果を物語る。一方、国内外の貧富格差は当時よりも拡大し、タックス・ヘイブンなどによる租税回避や途上国からの不正資金流出、法人税下げ競争などによる公的セクターのやせ細りが世界全体で進行、貿易ルールについても、世界貿易機関(WTO)のドーハラウンドが後景化し、二国間・多国間の自由貿易協定・経済連携協定の乱立という、より悪いシナリオに移行している。その中で、医薬品開発も、命を救う公共財の開発という目的は、イノベーションの加速化と利潤追求というもう一つの目的と混ざり合って溶解しつつある。
あとで詳しく解説するが、私たちがいま、直面している「治療アクセスと知的財産権」をめぐる闘いの「第2幕」は、ある意味つかみどころのない、より難易度の高い闘いだ。えてして原点を見失いがちになるこの時代に、私たちが何に直面しているのかの水準点を端的に示してくれるのが、十数年前の「闘いの第1幕」だ。この映画は、この「第1幕」について振り返ってみる上で、格好の素材を提供している。
2.「第1幕」をよりよく知るために=誰がいかにして勝ったのか
まずは映画「薬は誰のものか」を通じて、この「第1幕」を振り返る旅に出てみよう。以下は、この映画を踏まえて、この「第1幕」をさらによく知るための<歴史の道案内>である。実はこの映画には、歴史の流れや事実関係において、いくつか指摘しなければならない点がある。以下の「道案内」を使って、事実関係の確認をしながら、歴史の流れを見ていこう。
(1)前史:知的財産権至上体制の確立=WTOとTRIPs=
この物語の前史は、1980年代、レーガン共和党政権下の米国にさかのぼる。自動車をはじめ、日本などからの安価な工業製品の輸出攻勢にさらされていた米国が、貿易戦争での後退戦を跳ね返し反転攻勢をかける窮余の一策を、85年の「ヤング報告」で提示した。これが「知的財産立国」である。知的財産権保護を世界化することで、発明者の利権を囲い込み、そこで得られる利益を研究開発に投資することで、技術革新における米国の優位を永続化する…「ヤング報告」に込められたこのストーリーは、91年のソ連崩壊による世界単一市場の形成によって具現化する。世界貿易機関(WTO)の登場である。
冷戦期において西側世界の貿易ルールを形成してきたGATT(関税と貿易に関する一般協定)は、冷戦の終焉と同時に世界化され、1994年に作成されたマラケシュ協定の下、世界貿易機関(WTO)が成立した。このマラケシュ協定の一部をなす条約として、加盟国すべてが参加を強制されたのが「貿易関連知的財産権協定」(TRIPs協定)である。このTRIPs協定において、全加盟国は、知的財産権の調和化(ハーモナイゼーション)との聞こえのよい言葉の下に、物質特許を認め、特許権による独占権を20年とするなど、先進国ベースの「高い水準の知的財産権保護」を旨とする知的財産権保護法を、一定の猶予期間の後に制定しなければならなくなった。例えば物質特許を認めない特許法を有していたインドは2005年までに、また、技術移転の必要な後発発展途上国は2006年まで(のちに2016年まで、さらに2033年までに延期された)にTRIPs水準の特許法を制定することが義務付けられた。これにより、知財権至上主義体制の世界化が実現したわけである。
(2)エイズ危機と医薬品独占への闘い
知的財産権が肩で風を切っていた90年代後半、アフリカをはじめ全世界の脅威となったのがエイズ危機である。80年代初頭に登場し、米国のゲイコミュニティをいったんは崩壊の危機に追い込んだこの感染症は、90年代、今度はサハラ以南アフリカを危機に陥れた。初頭には世界全体で800万人程度であったHIV陽性者の人口は、2000年には3倍以上の3000万人にまで拡大し、そのうちの7割がサハラ以南アフリカに集中していた。特に南部アフリカでは、成人の5人に1人がHIV陽性となり、地域の経済・社会が破滅に瀕する事態となった。また、タイ、カンボジア、インドなどでもHIVの急速な拡大がみられたほか、世界の多くの地域で、男性とセックスをする男性(MSM)、セックスワーカー、薬物使用者、先住民、外国人移民といった、差別や迫害の対象となっているコミュニティを中心に巨大な感染拡大が生じるに至った。
90年代後半の段階で「エイズ治療の導入」に舵を切ることでエイズ危機の拡大を防いだのがブラジル、危機を乗り越えたのがタイであった。先進国では、96年の三剤併用療法(HAART: 高活性抗レトロウイルス治療)の導入によって、エイズは「死の病」から「管理可能な慢性疾患」へと変貌したが、これら2か国は、その特許法が欧米レベルの「高い知財権保護」を含んでいなかったことから、自国で合法的に製造できるエイズ治療薬を、インドから原材料を輸入しながら製造し、ブラジルは自国民に無料で、また、タイは自国の公的医療制度(30バーツ政策:1回あたり30バーツ(=100円)で病院にかかれる国民健康保険制度)にエイズ治療を導入することによって、治療薬を供給した。米国はこれを激しく非難し、ブラジルに対してはWTOへの提訴まで行った。しかし、この政策の結果、ブラジル・タイはエイズによる死者はおろか、新規感染も大きく減らし、「ブラジル・モデル」「タイ・モデル」といわれるエイズ対策の成功を実現したのである。
逆に、過酷な影響を受けたのは、世界最大のHIV陽性者人口を抱えた南アフリカ共和国であった。同国はアパルトヘイト時代を通じて、白人支配のいわば「先進工業国」であり、先進国並みの知的財産権保護法を有していた。そのため、エイズ治療薬はおろか、各種の日和見感染症の治療薬についても、多くの人々の所得に釣り合わない高価格で販売されていた。南ア政府は、自国の「薬事法」を改正する際に、TRIPs協定を踏まえつつ、非常時には特許権を自国のメーカーに強制的に実施させることができる「強制実施権」と、世界の最も価格の安いところで購入することができるという「並行輸入」条項の導入を図った。そうしたところ、新薬開発系製薬企業39社が改正薬事法を「憲法違反」として一斉に南ア政府を訴えたのである。さらに、知的財産権保護政策を主導した米国クリントン政権のアル・ゴア副大統領はわざわざ南アに乗り込み、当時のムベキ副大統領に薬事法の撤回を求め、拒否されると経済制裁をほのめかして威嚇するに至ったのである。
ここで立ち上がったのが、もともと反アパルトヘイト運動の活動家で、その後LGBT解放運動に取り組んでいたマレー系南ア人活動家、ザッキー・アハマットに率いられた南アフリカ共和国のHIV陽性者の団体「治療行動キャンペーン」(TAC)であった。彼らは南ア政府の「法律の友」として法廷で政府を支援しつつ、日和見感染症の治療薬のタイからの並行輸入を実施するなど、様々な取り組みを展開した。この闘いは、さらに、80年代の米国での巨大なエイズ危機と、それを無視し続けたレーガン政権に対する実力での闘いを起源とする米国のHIV陽性者のラディカルな運動体「ACTUP」(力を解放するエイズ連合:AIDS Coalition to Unleash Power)と、ACTUPが国際的な治療アクセス実現のために創設した「Health GAP」(保健への世界的アクセス・プロジェクト:Health Global Access Project)の全面的な支援を得るに至った。ACTUPは99年の米大統領選でアル・ゴア候補の選挙運動に対して大規模な抗議行動を展開、さらに同年のWTOのシアトル閣僚会議への反対運動に結集した。結果、同閣僚会議は中止に追い込まれたのである。
また、この「薬事法裁判」は、「強欲に走る製薬企業とそれを支える米国」対「徒手空拳で闘う南ア政府とHIV陽性者たち」という図式を、世界全体に印象付けることとなった。世界中で展開された署名活動では瞬く間に三十数万の署名が集まり、社会的責任投資(SRV)の市場では、投資家が裁判に関わる製薬企業への投資を嫌忌するといった状況も生じた。結果、2001年になって、製薬企業は一斉に裁判を取り下げ、この裁判は南ア政府側の実質上の勝利に終わったのである。
一方、途上国でのエイズ治療の実現への道筋を具体的に切り開いたのは、国境なき医師団(MSF)であった。エイズ危機の中、「エイズ治療を導入しなければ救うべき命を救えない」と決意したMSFは、本映画に主役級で登場するインドのジェネリック薬企業「シプラ」社(Cipla)と連携し、安価な三剤混合薬を入手、アフリカ各地でのパイロット・プロジェクトに導入した。一方で、三剤混合薬を誰にでも導入するのでなく、まず日和見感染症の治療をしっかりと行い、それに成功した人々を中心に投薬を行い、途上国の人々が実際にエイズ治療の導入にしっかりと応じることができることを論文で検証、途上国でのエイズ治療の実現にしっかりとした道を開くことに成功したのである。
(3)WTO「ドーハ特別宣言」による決着
エイズ危機の深刻さと、こうした市民社会の組織的な取り組みが、知的財産権至上主義体制に風穴を開けていった。それが最終的に結実するのが、本映画にも登場する、9.11同時多発テロの後に発生した「炭疽病危機」と、それを背景にした、WTOドーハ閣僚会議における「ドーハ特別宣言」である。この宣言によって、WTOの各加盟国は、国民の健康が危機にさらされた場合、医薬品の特許に関して強制実施権を発動することができること、国民の健康上の危機に関する判断は各国がその主権に基づいて自ら判断できることが決まった。医薬品の知的財産権保護に関する「柔軟性の確保」と表現される体制がここに実現したのである。
その後、特にエイズに関しては、MSFによる取り組みや論文を根拠にしながら、世界保健機関(WHO)と国連合同エイズ計画(UNAIDS)が共同で2003年には「2005年までにエイズ治療を必要とする300万人に治療を届ける」とする「3×5戦略」を策定、2006年には「エイズ治療・ケア・予防への普遍的アクセス」が世界的な目標となるに至った。エイズ治療アクセス1500万人を実現するに至る流れは、このようにして主流化したのである。
(4)「象」に対する「鍛え抜かれた蟻」の闘い
この映画では、アフリカのエイズ禍以前の95年にWTOに導入され、「知的財産権の世界化」をもたらしたTRIPs協定が、クリントン財団や「米国大統領エイズ救済緊急計画」(PEPFAR)より後になってから出現したかのように描かれている一方、このTRIPs協定に風穴を開けた「ドーハ特別宣言」に触れられていないなど、この問題の所在や闘いの歴史の流れについて、いささかわかりにくい点がある。また、「治療アクセスと知的財産権の闘い」の第1幕を勝利に導いたのは、わずかな数の活動家や専門家たちであったかのような描かれ方になっている。しかし、これまでの振り返りからわかるのは、この勝利は、傑出した個人の「点」の闘いとしてかちとられたわけではなく、世界のHIV陽性者やそこに連帯する人々の「層」としての闘いによってこそかちとられたのだ、ということである。実のところ、知的財産権の世界化という「象」に対する、「蟻」の挑戦が、限られた個人の「点」の闘いで勝ち取られるはずはないのである。
実際にそれが「象」に対する「蟻」の闘いであったことは事実である。しかし、その「蟻」とは、80年代の米国のエイズ・ラディカリズムや、90年代のIMF・世銀の構造調整政策との闘いを起源とし、それらに鍛え抜かれた、グローバルな市民社会の「層」としての「蟻」であった。それが、地球規模の脅威というまでに膨れ上がったエイズ危機の、巨大な犠牲の上で、その勝利を勝ち取った、というのが、「治療アクセスと知的財産権の闘い」の実相だといえる。私たちが「治療アクセスと知的財産権の闘い」の第1幕から学ぶ必要があるのは、実はそのことなのである。
3.現代の「治療アクセス」問題の実相:普遍性をめぐる闘い
この「第1幕」から十数年を経て、2017年に生きる私たちが直面しているのが、この「治療アクセスと知的財産権の闘い」の「第2幕」である。WTOドーハ特別宣言による「第1幕」の事実上の決着以降、この世界では、相反する二つの流れがつくられてきた。それが再び、人々の命を左右する「健康と医療」という交差点でぶつかり合うことで、数年前に「第2幕」が切って落とされたわけである。
では、この「二つの流れ」とは何か。2017年を生きる私たちの地平は、「第1幕」とどこが共通し、どこが異なるのか、以下みていこう。
(1)世界で1500万人以上のエイズ治療アクセスを可能にしたもの
まず、最初の流れは、必須医薬品へのアクセスをはじめ、必要な保健医療サービスへのアクセスを万人に保障していこうという流れである。この力あればこそ、「治療アクセスと知的財産権」の闘いの第1幕は、少なくともエイズに関しては、「治療アクセス」の側が勝利し、その後、アフリカをはじめとする「途上国」=南の世界でみても1500万人以上がエイズ治療にアクセスできるようになった。これは、21世紀の最初の十数年において人類が経験した最大の進歩の一つである。
これを実現したのは、まず、HIV陽性者をはじめとするグローバルな当事者の運動であり、それをサポートした市民社会である。もう一つは、その市民社会に背中を押され、2000年当時の巨大なエイズ危機の脅威に対して、平時にはなしえない緊急対応をとることを決意した国際社会である。この映画にある通り、世界はエイズを前にして、2001年、一つの疾病を対象としたものとしては初めて、国連特別総会を開催、2002年には「世界エイズ・結核・マラリア対策基金」(グローバルファンド)を設立、さらに2003年には米国が「大統領エイズ救済緊急計画」(PEPFAR)を開始、これまでとは比較にならない投資がエイズ対策に注ぎ込まれることとなった。また、インド製の安価な治療薬の導入によって、2006年には「エイズ治療・予防・ケアへの普遍的アクセス」が国際目標となるに至った。
これまで、利潤が上がらない、市場性がないという理由で十分な投資なく打ち捨てられていた、エイズ・ワクチンやマラリア・ワクチンの開発、マラリアや結核の新たな治療薬、さらには、内臓リーシュマニア症やトリパノソーマ(アフリカ睡眠病)といった「顧みられない熱帯病」の治療薬開発などについても、「顧みられない疾病のための治療薬イニシアティブ」(DNDI)などのNGOや、「エイズ・ワクチン推進構想」(IAVI)といった公的機関・民間企業・NGO・当事者を結ぶ各種の<製品開発イニシアティブ>(PDP)の設立などによって投資が拡大し、新規開発の進捗が期待できるまでになった。
新たな財源の確保のための取組も進んでいる。フランスが音頭をとって始まった「航空券連帯税」(国際旅客便のチケットへの安価な課税)は韓国、チリなど10ヵ国に広がり、その原資を、一般的なエイズ治療薬に耐性ができてしまった人のための第2・第3選択薬や子ども用のエイズ治療薬、多剤耐性結核薬などのジェネリック薬の定期的大量購入に活用する国際機関「ユニットエイド」(UNITAID)が設立された。さらに、この原資を基に、知的財産権と治療アクセス問題に正面から向き合う「医薬品特許プール」(MPP)が設立された。これは、先進国の新薬開発系製薬企業が開発した新薬の特許権を、一定の資金支払いと引き換えにプールし、疾病負荷が重い途上国に限定する形で、インドなどのジェネリック薬企業に製造や改良などのライセンスを与えるメカニズムである。現在までのところ、MPPが対象とする治療薬は、HIV/AIDSと、近年になってC型肝炎の治療薬に限定されているが、すでに、米国のギリアド・サイエンシズ社や、グラクソ・スミスクラインとファイザーが共同設立したエイズ治療薬開発企業ヴィーヴ・ヘルスケア社などがこのメカニズムによって新薬の特許権をプールし、インドなどのジェネリック薬企業が、アフリカ向けなどにより安価な形でジェネリック薬を輸出するといった動きが始まっている。
(2)知的財産権至上主義からの反撃:闘いの第2幕
こんな「いいことづくめ」の中で、「治療アクセスと知的財産権の闘い」の第2幕がなぜ切って落とされなければならなかったのか。それは、以下に見るもう一つの流れによるものである。
先ほど、「第1幕」は「治療アクセス」側の勝利に終わったと書いた。この「第1幕」が展開されたのは、世界貿易機関(WTO)のドーハ開発ラウンドにおいて展開され、その舞台は、WTO加盟国が強制加入を義務付けられた「貿易関連知的財産権協定」(TRIPs協定)においてであった。「第1幕」勝利の過程は、その舞台、すなわちWTO自体が交渉に行き詰まるプロセスでもあった。第2幕は、この同じ古いステージにおいてではなく、新しいステージにおいて始まった。TPP(環太平洋経済パートナーシップ協定)といった、二国間・多国間の自由貿易協定・経済連携協定のステージである。またしても主役は米国、準主役は日本や英仏といった西側先進国、その相手は中所得国および低所得国である。
米国の貿易関連知的財産権政策をけん引するのは、新薬開発系製薬企業とその連合体である「米国研究製薬工業協会」(PhRMA)である。PhRMAの激しいロビー活動の影響で、その代弁者となった米国政府は、すべての自由貿易協定・経済連携協定の交渉において、「高いレベルの自由化」の旗印のもとに、「TRIPsプラス」という名のパッケージの採用を提案している。これは、米国が参加するあらゆる自由貿易協定において、WTOのTRIPs協定以上の水準の知的財産権保護の制度を導入するというものである。
この「TRIPsプラス」の中でも大きな問題になってきたものが、TPP交渉においても記憶に新しい、いわゆる「データ保護」と、「常緑化」(エヴァーグリーニング)である。「データ保護」とは、新薬の臨床試験のデータへのアクセスを特定年数認めず、これを「保護」するというものである。結果、ジェネリック製薬企業は、特許権保有者が持つ臨床試験データを参照することができないため、自ら独自に臨床試験を行わなければ、ジェネリック薬を開発することができなくなる。TPP交渉においては、米国がこの「データ保護」期間を12年にすべきと主張、オーストラリア、ニュージーランドやその他の中所得国は、それに対応して5年を主張し、米国と並んで知的財産権については強硬論者である日本が「間をとって8年」と提案して、<ガラス細工の妥結>をみることになった。
もう一つの「常緑化」(エヴァーグリーニング)は、特許期間(20年)が迫ってきた薬について、微小な改善や変化を加えて新たに特許権を更新することによって、独占権や利益をより長期的に得られるようにする、というものである。「TRIPsプラス」においては、特許の対象が、新たに開発された医薬品のみならず、既知の医薬品の新たな使用法や異なった製造方法などにも拡張しており、「常緑化」の要件が各段に広がる形となっている。
「常緑化」をはじめとする「TRIPsプラス」のパッケージは、医薬品の製造・販売について、「高いレベルの自由化」どころか、先進国の巨大な新薬開発系製薬企業に、長期にわたる商品独占権と巨額の収入を提供し、ジェネリック薬企業を市場から排除することを意図したものである。この異様なまでの執念は何か。
新薬開発系製薬企業は、「新薬開発には膨大な資金がかかる」という。それは一面の真実ではある。しかし、新薬開発に向けた基礎的な研究の一定部分は、実は公的機関によって、公的資金を活用して行われている。問題はむしろ、巨額の広告宣伝費や、企業買収を繰り返した挙句、その巨大さと極端な高利益体質を維持しなければ安定した生存が望めなくなった新薬開発系製薬企業の業界そのものにある。もう一つは、前章の冒頭で見たように、「知的財産立国」は日本との経済競争に悩んだ米国が1985年のヤング報告によって打ち出したのが最初であるというところにヒントがある。「今先んじている者」が「知的財産権」の世界的囲い込みにより、永続的にイノベーションの先頭に立つ。この仕組みが、90年代のWTO発足による知財権の世界化によって「先進国クラブの優位」へと拡張され、今に至る。人の命を左右する医薬品、特に新薬について、「先進国クラブ優位」を維持するには、新薬開発系製薬企業が、現在のように先進国にあり、巨大でなおかつ極端な高利益体質の状態に置かれなければならない。さもなければ、インドや中国など一部の技術の高い新興国からの企業が、その地位を脅かさないとも限らないということになる。
「第2幕」のもう一つの焦点は、「中所得国」と、「非感染性慢性疾患」(生活習慣病)の治療薬にある。新薬開発系製薬企業の利益の最大ボリュームは、先進国における「非感染性慢性疾患」の治療薬であるが、実際には、糖尿病や高血圧、ガンといった非感染性慢性疾患は先進国以上に、途上国・新興国において猛威を振るっており、それへの対処はまだまだ手についたばかりである。ここに新たな市場を開拓することで、新薬開発系製薬企業としては、膨大な利益を手にすることができる。そのためには、競合相手となりうる存在を知的財産権によってあらかじめ市場から排除しておくに限るということになる。
ひとつ先進国側にとって都合が良いのは、2016年以降の途上国の開発資金戦略として、2015年にアディスアベバで開催された「第3回国連開発資金会議」で打ち出された「アディスアベバ行動アジェンダ」において、途上国の開発について、援助よりも民間資金と途上国それ自体の財源を重視する方向性が打ち出されたことである。これによって、中南米や東欧・中央アジア、東南アジア・南アジアなどの主要な中所得国については、膨大な貧困層が存在し、また、無料・安価な公共医療制度や公的保険制度、効率的な税制が整っているわけでもなく、先進国主導の貿易ルールが修正されたわけでもないのに、いわゆる「援助」の対象からの「卒業」が叫ばれるようになった。つまり、これらの国々における、特に「緊急性」がないとされる多くの「非感染性慢性疾患」については、アフリカのエイズ問題などと異なり、「高い水準の知的財産権保護」を維持して構わないという政策環境が整備されたということになる。
(3)生命をめぐる闘い=「すべての人に健康を」
世界はいったい、どちらを向いているのか。「第2幕」をめぐる私たちの立ち位置にとって、大きなヒントになるのが、2016年から30年までの世界の開発戦略として打ち出された「持続可能な開発目標」(SDGs)である。
2015年9月、世界の193か国の首脳が国連で一つの文書を採択した。「SDGs」と、これを含む政策文書「我々の世界を変革する=持続可能な開発のための2030アジェンダ」である。2016年から全世界が実施段階に入ったこの「SDGs」の全体スローガンは「だれ一人取り残さない」(Leave no one behind)であり、健康に関する目標(ゴール3)には、「すべての年齢のあらゆる人の健康的な生活を保障し、福祉を増進する」と書かれている。さらに、保健ゴールの根幹となっている「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」(ターゲット3.8)には、「必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む」と明記されている。すなわち、ここで掲げられているのは、「すべての人に健康を」というスローガンである。「第1幕」で問題になったのは、グローバルな危機を作り出した「エイズ」という単一の感染症であった。しかし、「第2幕」の土俵は、エイズといったパンデミック(地球規模感染症)だけではない。途上国における非感染性慢性疾患や、いまだに多くの子供たちの命を奪っている呼吸器疾患、下痢症といった「ありふれた」感染症なのである。
「第2幕」の渦中にいる私たちの前で、二つの流れがぶつかっている。私たちはどちらに向かって歩むべきなのか。すべての人が、生まれた場所や経済階層、ジェンダー、人種、民族、国籍を超えて、命を救う必須医薬品と保健医療サービスにアクセスできるメカニズムを、グローバルに作ることをめざすのか、それとも、世間が騒ぐ一部の保健問題には「例外」を作りつつも、生まれた国や階級によって「命の値段」が異なる世界を当然とするのか。「治療アクセスと知的財産権の闘い」の第2幕は、第1幕以上に普遍的な、「いのち」をめぐる闘いなのである。
以上
※「薬は誰のものか(Fire in the Blood)」日本語版の上映、DVD販売については以下をご覧ください。
アジア太平洋資料センター(PARC)
ドキュメンタリー映画 「薬は誰のものかーエイズ治療薬と大企業の特許権」(ディラン・モハン・グレイ監督、2013年、インド)
http://www.parc-jp.org/video/sakuhin/fireintheblood.html
1990年代~2000年代のアフリカや途上国の「エイズ危機」と、途上国のHIV陽性者たちの治療アクセスを阻んだ知的財産権(特許権)の問題を告発した映画「薬は誰のものか」。日本語版の制作にはAJFが全面協力しました。