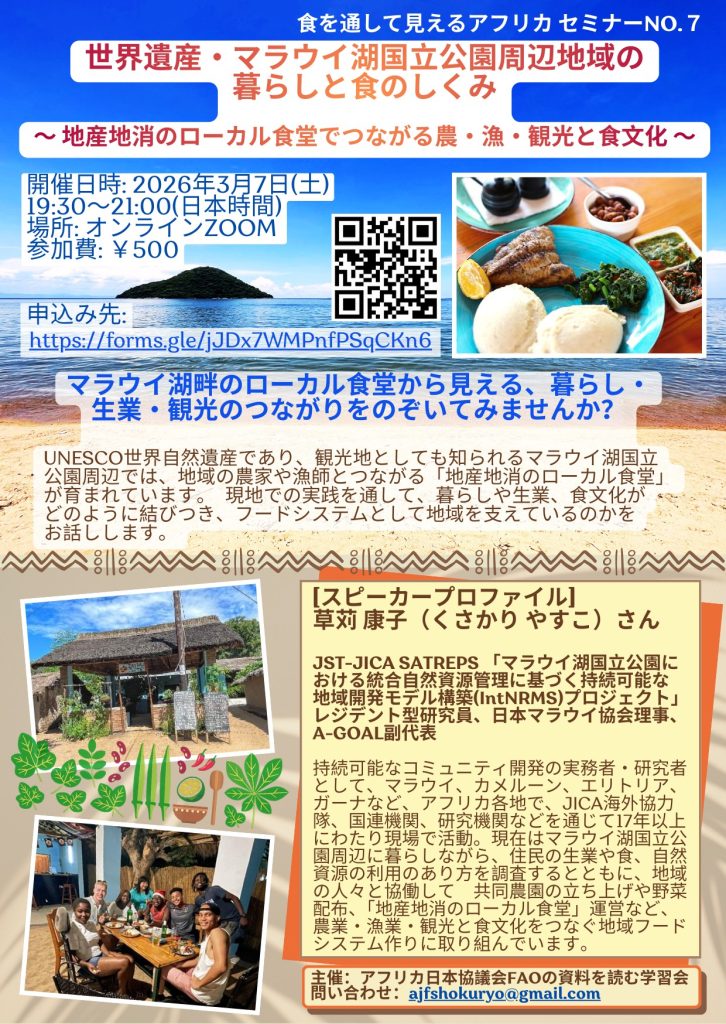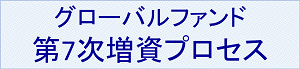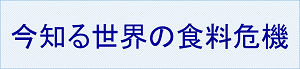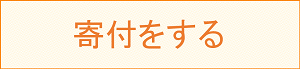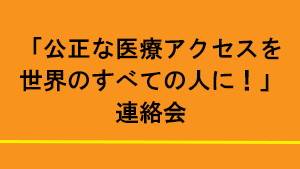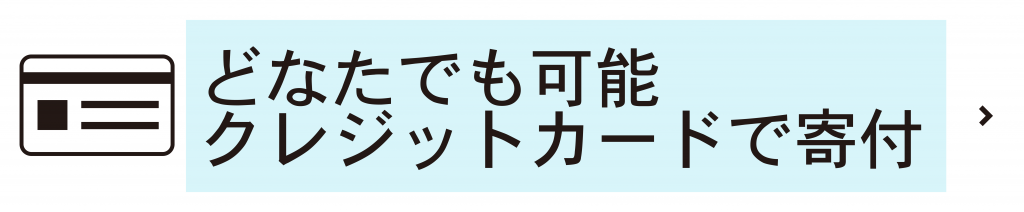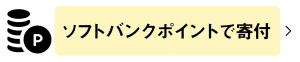成果文書交渉では熾烈な駆け引きも
軽んじられてきた非感染性疾患・精神疾患

9月25日、米国・ニューヨークの国連本部で、非感染性疾患(NCDs、いわゆる「生活習慣病」)と精神疾患を対象とした「第4回非感染性疾患の予防と管理および精神的な健康と福祉の促進に関する国連総会ハイレベル会合」が開催される。非感染性疾患(NCDs)、精神疾患、薬物による疾患などは、途上国でも深刻な被害をもたらしており、その影響は、高齢化の進行や、食生活の大きな変化による肥満や大気汚染の深刻化、多発する戦争や治安悪化によるトラウマ、気候変動など環境要因も含めた強制的な人口移動、デジタル化の進行によるストレスや若年層の「ゲーム依存」、依存性の高い薬物のマーケティングといった様々な要因によって悪化する状況にある。
一方、途上国の保健政策や援助政策において、NCDsや精神疾患は感染症に比べて低い優先度しか与えられてこなかった。これには、実際の感染症の脅威に加えて、NCDsや精神疾患の影響が実際より低く見積もられてきたこと、特に中所得国などにおいてNCDsの要因となる塩・砂糖・脂肪などを多く含む超加工食品などを大量に販売して距離を上げてきた国際的なフード産業やレバレッジ産業、アルコール・タバコ産業などの巨大なロビー力、さらに先進国による圧力などが要因となっており、いわゆる「健康の社会的決定要因」(Social determinants of health: SDH)に加え、「健康の商業的決定要因」(commercial determinants of health)などとも言われている。保健政策のトレンドから言っても、2001年に制定された貧困半減のための世界目標である「ミレニアム開発目標」(MDGs)にはNCDs・精神疾患は含まれなかった。2016年から2030年までの目標である「持続可能な開発目標」(SDGs)では、ようやく、「非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1削減するとともに、精神保健・福祉を促進する」ことを謳うターゲット3.4が、「心血管障害・癌・糖尿病・慢性呼吸器疾患により、30-70歳の間に死亡する確率」(指標3.4.1)と「人口10万人当りの自殺率」(3.4.2)という指標を伴って導入された。しかし、取り組みは遅々として進まず、NCDs対策に関する世界的なネットワークである「NCDアライアンス」によれば、NCDsによる若年死亡率を3分の1低減するという目標を達成できそうなのは世界で19か国・地域に限られ、逆に、20か国ではNCDs死亡率が増加しかねない状況である。
NCDsの主要な危険因子「大気汚染」
NCDsの主要な危険因子の一つとして近年改めて注目されているのが大気汚染である。人の健康に影響を与える大気汚染には、排気ガスを含め、炭素の燃焼によって汚染された外気によるものと、室内での不適切な燃料による料理や暖房、照明によるものとがある。大気汚染を原因とする死者数は年間700万人を数え、世界全体の死者数の10%に及ぶ。2025年3月に南米コロンビアのカルタヘナで開催された「大気汚染と健康に関する第2回世界会議」およひ同年5月に世界保健総会で採択された「大気汚染の悪影響への保健セクターの対応ロードマップ」で、世界保健機関(WHO)加盟国は、2040年までに2015年比で大気汚染による死者数を半減するという目標を掲げた。欧州連合は大気汚染防止の政策を強化し、外気汚染による死者数の低減に向けて努力しているし、ネパールやケニア、ガーナなどは調理の燃料をより適切な液化石油ガス(LPG)やエタノール、電気などに置き換えることで室内大気汚染による死者の低減に向けて取り組んでいる。今回のハイレベル会合では、大気汚染の課題をNCDsの取り組みに入れ込んでいく上で重要な機会となっている。
注目される「精神疾患とNCDsの相互連関」
今回のハイレベル会合は、国際保健においてメンタルヘルスの優先順位を上げる上で重要な機会である。メンタルヘルスに関する国際的な市民社会ネットワークである「世界のメンタルヘルスのための団結」(United for Global Mental Health)によれば、世界全体で年間840万人が精神病院などの精神科施設に入院しており、収容期間も、全体の13%が1年以上、7%が5年以上に及ぶ。施設に隔離されてしまえば、社会から切り離されて復帰が困難になるうえ、施設内での人権侵害や強制的もしくは不適切な治療なども行われている。精神医療が進んだ国では、施設収容から地域社会でのケアと包摂に移行しているが、多くの途上国はその段階にない。精神疾患は「障害換算生存年」(DALYs)で見ると、全疾患の13.5%を占めているが、各国政府は精神疾患について保健予算の2~3%、低・中所得国だけで見ると1%前後しか使っていない。SDGsの指標3.4.2の「自殺」については、死者数が毎年72万人に及んでいるが、世界25か国では自殺を「犯罪」として扱っており、これらの国々では、自殺がタブー視され、自殺未遂者や家族などが支援を受けにくくなり、統計データも不正確となるという問題がある。さらに、近年注目されているのは、精神疾患とNCDsの関連性である。うつ病の患者が心疾患で死亡するリスクはそうでない人と比べて最大4倍も高いとされる。また、たばこやアルコールなどの物質嗜癖は、がんや糖尿病などのNCDs、また、認知症などを引き起こす要因となっている。こうした精神疾患とNCDsの相互連関を読み解くことは、双方の適切な診断と治療にとって重要である。
成果文書=弱められる文言
このように、今回のハイレベル会合は、国際保健の進展に向けて大きな可能性を持つが、成果物となる「政治宣言」の文面に関する交渉は、取り組みを前進させるには厳しい状況にある。薬物による疾患の被害を削減するための市民社会のネットワークであるモヴェンディ・インターナショナル(Movendi International)によると、政治宣言の最初のドラフトでは、アルコールをたばこ同様の健康に有害な製品として扱ったうえ、その街を減らすための課税政策やWHOによるアルコール政策パッケージである「SAFER」についての言及があったが、第2ドラフト以降では、これが著しく弱まった上、業界用語がちりばめられるようになった。また、NCDアライアンスによれば、当初はあった砂糖入り飲料への課税についての言及が削除され、プライマリー・ヘルスケア施設でのNCDs・メンタルヘルス用医薬品へのアクセスに関する目標数値も、80%から60%に引き下げられるなど、内容は大きく後退している。NCDsアライアンスのアドボカシー・政策担当のマリンケ・クレミン氏は、今後も成果文書の文言修正が大規模に展開される可能性があり、また、一定の合意ができて、文書確定に向けた「沈黙期間」(宣言の最終ドラフトが交渉に寄って確定した後、一定の期間を指定して、明示的に反対を主張する国がないことを確認する期間)を破る国が続出する可能性もあると述べている。テドロスWHO事務局長は、たばこ・アルコール、砂糖入り飲料など体に悪影響を与える製品への課税を50%引き上げることによって、「5年間で世界全体で3.7兆ドルの追加収入を生み出し、数百万人の命を救うことができる」と述べているが、その道は険しそうだ。