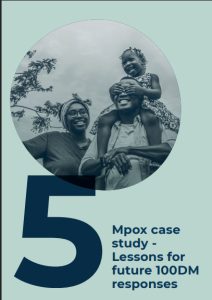Report ”POP AFRICA”
『アフリカNOW』83号(2009年1月31日発行)掲載
執筆:茂住 衛
もずみ まもる:1994年に、セネガル・ゴレ島でのジャンベとアフリカンダンスのワークショップに参加するために初めてアフリカを訪問。2002年にAJF幹事(現、理事)に就任し、以降『アフリカNOW』の編集と理事の仕事を担っている。
「POP AFRIC アフリカの今にノル?」。このコピーのセンスにまず直感的に反応したのは、私だけではないだろう。2008年11月15日と16日の2日間にわたって、東京・世田谷にある国士舘大学世田谷キャンパスで開催されたこのイベントは、さらに次のように呼びかける。「普段着のディープなアフリカ:その美学・音楽・力学・知恵の深みにハマる2日間」。とらえどころがなさそうで、でものぞいてみたいという期待感はさらに高まり、仕事の締切に追われ、私にとっては「早朝の」午前中から企画が始まったが、結局は2日間の企画のかなりに参加してしまった。
このイベントの参加報告をすることは、『アフリカNOW』の読者にとってももちろん有意義なことだと、私は考えている。そして報告記事であれば、実施された企画の内容にそった説明が求められるだろう。だが今回は、企画の内容について具体的に報告することよりも、私がなぜこのイベントに引きつけられたのかについて問い返してみる。そしてこのことから、私個人の感想にとどまらずに、〈アフリカ〉に関わることについて、ひとつの問題提起をしてみたい。
コピーのセンスに「踊らされた」私は、このイベントに「ノリ、ハマって」しまったが、私はどのように引きつけられたのだろうか。プログラムの多くが「研究発表」で占められていたこのイベントに、私はどうしてかくも単純に「ノリ、ハマって」しまったのだろうか。
ありきたりの言い方をしてしまうならばこのイベントは、2日間で23の研究発表と2つのパネルディスカッションがあり、平行して映像が上映され(残念ながら、映像はほとんど見ることができなかった)、日本のアフリカ系ミュージシャンによるトーク+コンサートや懇親会もある、いわばアフリカ学会の文化人類学バージョンやポップカルチャー篇であるといった説明ができるだろう。だが、この説明がとりあえずは妥当なものであったとしても、それだけではもちろん私が実感したこのイベントの魅力を言い表したことにならない。私にとって、研究発表のテーマの多くが興味を引かれるものであり、顔見知りの発表者や参加者が何人かいたという親近感があったことは間違いないが、それだけでもない。
私が「ノリ、ハマって」しまった理由としてまず思い浮かぶのは、いくつかの発表やディスカッションでの発言から、発言者自身の「研究対象」への関わり方がストレートにかいま見えた、それぞれの発言者が実感しているであろう楽しさや魅力が、「研究発表」というスタイルの中でも伝わってきたということだ。
文化人類学や文化研究(カルチュラルスタディ?)などの分野では、多くの場合において、研究対象の社会や文化に対する参与観察(participant observation)がごく基本的で不可欠な研究手法になっている。そしてこの手法は、研究対象に対する理解を深めるために効果的である一方で、観察の客観性を失ったり、一面的な見方になりやすいということもよく指摘されてきた。
だが、このイベントでのいくつかの研究発表からは、こうしたありきたりの指摘ではとても捉えきれない、発表者の主体的な関わり方が提示されていたことに、私は強い印象を覚えた。これらの発表者にとって、自らの発表の対象になった出来事や事柄は、単なる「研究対象」として客観的に存在しているだけであるよりは、自らの日常的な実践と直接に結びついて「今ここに」存在しているのではないか。
例えば、アフリカンダンスのワークショップに参加してダンスを楽しむことがそのまま研究発表にストレートに結実したり、日本でも行っているヒップホップの音楽づくりをアフリカでも現地のミュージシャンと共同で行い、その過程から研究発表を組み立てる。こうした行為を「研究手法としての参与観察」の枠組みのみで捉えてしまうと、その行為の意味や魅力が半減されてしまう。これらの発表者の研究発表と、トーク+コンサートに出演した3人の日本のミュージシャンン(武田ヒロユキさん=ジャンベ、向山恵理子さん=ニャティティ、ハヤシエリカさん=ンビラ)が語ったり、演奏したり踊ることは、共にひとつの場における同質の行為であると、私には容易に実感することができた。そして、この状況が〈アフリカ〉と〈日本〉のポップな関係を象徴しているのではないかと考えると、また楽しくなってくる。
さらに、〈アフリカ〉のポップに関わる多彩な切り口からの研究発表やディスカッションの場に居合わせたという事実に重ね合わせて、これらの切り口のまとめ方にも心ひかれるものがあった。このイベントの1日目の9つの研究発表は3つのセッションに、2日目の14の研究発表は4つのセッションに、次のようにまとめられていた。
1日目:「アフリカと日本のポップな関係」〜 Ⅰ 日本のアフリカ的世界、Ⅱ 越境するアフリカ的美学、Ⅲ 日本のアフリカ音楽
2日目:「アフリカのポップカルチャー」〜 Ⅰ 売る/ごまかす–起業家としてのアーティスト–、Ⅱ 集う/ふるまう–ニューメディアと自己表現–、Ⅲ まねる/混ぜる–ブリコラージュとしてのアート–、Ⅳ 魅せる/妬む–商品、誘惑、フェティッシュ–
手元にあるプログラムに記載された名称を単に書き写しているだけだが、こうしたまとめ方を見ていると、〈アフリカ〉とその影響を受けた〈日本〉のポップな今のあり方をどのように再構成していったのかという、主催者側の問題意識がかいま見えてくる。それだけでなく、私自身の日常的な社会との関わり方も、こうして再構成できるのだろうかという想像もできる。ちなみに、2日間の企画の最後の全体会には、このイベントの雑多な魅力とその余韻を示すかのように、「ポップアフリカのディープな残響」という名称が付けられていた(主催者側が特に意図したわけではないだろうが)。
ここまで述べてきたように、私にとっては魅力的なイベントであったが、その一方で、いわゆるアフリカの「開発系」の関係者の参加は全般的に少なかったようだ。個人レベルでは、「開発系」の仕事に従事している人でも、このイベントに多大な興味を抱いて2日間の企画のほぼすべてに参加した方にお会いしたし、〈アフリカ〉に関わる多様な分野に応じて個々の関係者の関心領域も異なっていることも当然であろう。それでもこの現状が、日本においては〈アフリカ〉の異なる分野に関わる関係者同士の相互交流が限られていて、分野ごとに「分裂」している現実を示唆しているのではないかと考えてしまう。そしてこのことは、最後の全体会の場においても、話題のひとつとして取り上げられていた。
もちろん、こうした現状認識自体が妥当なことなのか、妥当だとしてもそこにどのような問題が内在しているのかなどの点は、当然にも問い返される。ここではこうした論点について考察する余裕はないが、このイベントのプログラムに掲載されていた企画の趣旨の一部を引用して、アフリカのポップカルチャーについて考えることが、アフリカの開発を考える際にも持つ意義の一端を提示してみたい。
(前略)アフリカのポピュラーカルチャーは、プロや専門家主体の何か明確な分野(ジャンル)というよりは、誰しもが容易に参加できる日常的な実践です。それは普通の人々が、喜び、悲しみ、怒り、怒り、妬み、などの感情を表現する方法です。それはまた自分と他人を認識し、仲間をつくり、そして権力者に対抗するための手段でもあります。そしてそれはいわゆる伝統的な要素を保ちながらも、世界の多様な文化を取り入れ変化し続ける、変幻自在な文化でもあります。