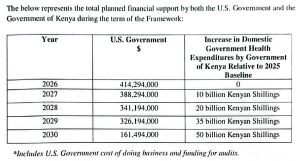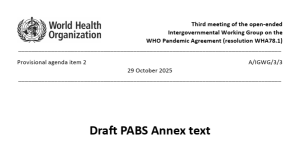亀井伸孝さんが語るー『森の小さな〈ハンター〉たち』を手がかりにアフリカ子ども学を考える
Thinking about Studies on African Childhood by tracing “Little “Hunters” in the Forest”
『アフリカNOW』90号(2011年1月31日発行)掲載
語り手:亀井伸孝
かめい のぶたか:大阪国際大学准教授。理学博士。手話通訳士。専門は文化人類学、アフリカ地域研究。1996年からカメルーンにおける狩猟採集民バカの子どもの研究を始め、あわせてアフリカの手話とろう者に関する研究に携わる。著書に『手話でいこう-ろう者の言い分 聴者のホンネ』(ミネルヴァ書房、2004年)、『アフリカのろう者と手話の歴史-A・J・フォスターの「王国」を訪ねて』(明石書店、2006年)、『手話の世界を訪ねよう』(岩波ジュニア新書、2009年)、『森の小さな〈ハンター〉たち-狩猟採集民の子どもの民族誌』(京都大学学術出版会、2010年)など。
森の小さな〈ハンター〉たち-狩猟採集民の子どもの民族誌
京都大学学術出版会
2010年2月20日 第1刷発行
縦組、本文292ページ
定価:3,400円+税
ISBN:978-4-87698-782-5
※ 本稿は、2010年9月9日に開催された「『森の小さな〈ハンター〉たち』を手がかりに『アフリカ子ども学』を考える」でのトークの内容を編集しました。
アフリカの子どもたちについて考える
私の博士論文をもとにした『森の小さな〈ハンター〉たち-狩猟採集民の子どもの民族誌』という本が、2010年2月に刊行されました。この機会に、かねてからアフリカの子どもたちに関心を寄せている人たちに議論をする機会を持ちませんかと呼びかけて、今日の集まりになりました。
日本では、アフリカの子どもを見る眼差しが、貧困や暴力、内戦あるいは性暴力といった、どちらかといえばアフリカの子どもたちは恵まれない気の毒な存在なのだというものになりがちです。マスコミの報道、国際機関やNGOの人道支援キャンペーンも、アフリカの子どもたちはこんなに大変だという話で埋め尽くされてしまっている感があります。それだけでは、アフリカの子どもたちの本当の姿が見えてこないのではないかと、AJFのスタッフと話し合って意気投合したことから、この機会を持つことになりました。
調査にのぞむスタンス
今日はこの本と私の研究を紹介し、今後、皆さんと議論したいテーマについて触れたいと思います。私の専門は、文化人類学とアフリカ地域研究です。かつて霊長類学や動物学を勉強したことがあり、自然科学的な行動の観察を通して学ぶ生態人類学に近い立場で調査をしてきました。取り組んできた調査の一つは、狩猟採集民およびアフリカの自然の中で暮らす子どもたちの調査で、もう一つはアフリカのろう者、つまり、手話を話している耳の聞こえない人たちの調査です。私自身もフランス語圏西アフリカの手話を覚えて、ろう者のコミュニティに入り、手話で織りなされている文化の世界や言葉の世界に参与しながら学んでいます。
この二つの大きなテーマは、それぞれ別個に取り組んでいますが、私の根底に流れている関心の対象は、言葉や遊びのように、どんな社会でも見られるが、それぞれの社会や文化によって少しずつ修飾されて異なっているものにあります。具体的には、社会や文化あるいは年齢や性によって少しずつ現れ方が違っているさまざまな言葉や遊びを集めて比べてみたり、似かよっているところを見つけたりすることに興味を持っています。
『森の小さな〈ハンター〉たち』は、中部アフリカのカメルーンの熱帯雨林で暮らしている、「バカ」という民族名の狩猟採集民の子どもたちの暮らしぶり、生業活動や遊び、学校教育など、子どもたちがすることなすことをひととおり記録した民族誌です。人類学者がよくやる参与観察という調査方法に基づいて、遊ぶなら一緒に遊ぶ、狩りに行くならついていく、果実の採集をするのであれば一緒に木に登って果実を採るというように、観察対象となる人たちと一緒のことをやる。自分も体験しながら仲間入り、というか、私は狩猟採集の方法をまったく知りませんので、「小さな先生」である子どもたちに弟子入りして、一緒に狩りをしながら森の歩き方を教えてもらうという方法で調査をしました。
この本は、実際には失敗の中で生まれたという一面があります。狩猟採集民の大人の本格的な狩猟や採集などの調査をするのは、とても疲れるのです。狩猟採集民は、一日に何十キロも平気で森の中を歩きます。ここでうまいものがとれるから朝早く起きて行ってこようといった感じで行動します。私も最初は同行しなければと思い、がんばって一緒について行ったのですが、日が暮れても家にたどり着けないということもありました。私ひとりがくたびれて、「ごめん、もう歩けない。休ませて」などと言って、結局、狩猟チームの足を引っ張りまくったのです。森の調査をするには強靱な体力がいるなと実感し、子どもたちの方がまだ体力的には勝負できるんじゃないかと思って、子どもたちに弟子入りしました。ところが、子どもたちの足も引っ張ってしまいました。子どもたちは背が低いので、どんなにやぶが茂っていてもヒョイヒョイと潜って、どこまでも駆け足で行ってしまいます。私は「待ってくれえ」と言いながら、後をついて歩いて回ったのです。
またこの本では、狩猟採集民の子どもたちが学校になかなか通わないというシーンを描いています。最初は学校という定点から、どんな子どもたちが集まって、先生はどんな授業をしているのかなどの事柄を懸命に記録していました。そうすると毎朝、何時に子どもたちが集まってきて、一列に並び、歌を歌い、それからよくわからないフランス語を「アー・ベー・セー」と復唱し、そして昼になると、配られるバナナを喜んで食べて、パーッとクモの子を散らすように消えてしまう、という記録が続いてしまいます。もちろん、そこから見えてくることもありますが、味気ないもので、学校が終わって散った後の子どもたちの暮らしがどうなっているのだろうと考え始めました。それから、森の中に入っていった後の子どもたちの方に、調査の軸足を移しました。そうすると、ハッと見えてくることがありました。
子どもたちへのインタビューは非常に難しいのです。子どもたちは、学校でフランス語を勉強しますが、流ちょうには話せませんので、現地の言葉であるバカ語を覚えないと話に応じてくれません。また、子どもたちは飽きっぽいので、一対一で机を並べて、「さあ、あなたのなんとかについて聞かせてください」などと言っても、そんなことには飽きて、すぐに出ていってしまいます。インタビューにはこうした難しさがあるので、一緒に何かをやりながら参与観察することに軸足を移すことにしました。記録することにこだわらず、一緒に遊んでみようと肩の力を抜いたことによって、いろいろと経験できたこともありました。
このようにすることができた背景には、有名な霊長類学者で人類学者でもある伊谷純一郎さん(故人、京都大学名誉教授)が、放送大学の取材のために、たまたま私が調査しているカメルーンにいらしたときの経験があります。日本を代表する、世界的にも有名なこの大先生がアフリカのフィールドで何をするのかと思ったら、現地の人の言葉もわからないのに、いきなり「これ、ちょっともらってもええか」と関西弁で言って、つまみ食いを始めたんです。でも、現地の人はまったく嫌がらない。そのときの私は、他人が食べているものに手なんか出したら、それは調査倫理に反するのではないかなどと考えていたのです。でも、伊谷さんは「うまいな、これ」などと言って、にこにこしながら一緒に食べて、現地の人たちに、にこにこと受け入れられていました。また、子どもたちがサッカーを始めると、70歳を超えた大先生が一緒にサッカーをしたり、踊ったりしているのです。あっ、これの方がむしろ自然な調査のスタイルなのだと思いました。先に調査項目を決めて、片っ端から順番に形式張ったインタビューをするよりは、まずは一緒に遊んでみよう、つまみ食いをしてみよう、といった具合に肩の力を抜くことができました。
子どもたちに弟子入りする
私の調査地は、カメルーン東南部の赤道に近い熱帯雨林地域です。狩猟採集民バカの人たちは、熱帯雨林の中に丸いドーム形の伝統的な家屋を作り、その中に家族で暮らします。この家は、女性が手近な枝や葉っぱを集めて、パッパッパッと短時間で作ってしまいます。この家にしばらく住んだら放棄して、別の場所に移動し、家そのものは自然に朽ちていきます。だいたい水場が近くて、狩猟や採集に適している住みやすい場所をよく覚えていて、ひととおりぐるっと回ったら、また来年はここに来ようかという感じで移動しています。いつも決まりきった、住み慣れた場所を確保しています。伝統的には、森の中を移動しながら暮らしていたのですが、近年は林道ができ、最近では時々、車も通るような開けた場所に、農耕民が建てる農村の家屋のようなものを建てて、そこで暮らしたり、あるいは伝統的な森の中の暮らしに戻ったりと、往復するような暮らし方をする人も増えています。
調査に入ったとき、私は髪もひげものばしていました。そんな人間が来て友達になろうと言っても、子どもたちはびっくりして、泣いて逃げてしまいます。で、どうしたものかと考えて、最初に使ったのはアメでした。子どもたちに声をかけてもみんな逃げて、柱の陰に隠れてしまいますが、それでもおそるおそる近づいてくる少年が必ずいるんですね。最初はそういう大胆な子どもになついてもらい、やがて、臆病な子どもたちも近づいて来てくれるようになりました。
また、旅の恥はかき捨てだと、子どもたちがよく真似て踊っている伝統的な精霊のダンスを踊ったりもしました。髪が長かったので、髪を前に垂らし、揺さぶって踊ったら、大受けしました。子どもたちのための一発芸のつもりが、大人たちも喜んで家から飛び出して、集まってきたのです。ちょっと恥ずかしかったのですが、反響はありました。子どもたちと一緒におもちゃ作りもしました。子どもたちは、森の木の枝や葉っぱなどの素材を使って、ナイフで器用に削ったりして、いろいろなおもちゃを作ります。子どもたちが狩猟に行くときには、一緒についていきました。そうしているうちに、こんな変な色白の人は初めて見たけれども、この人は無害だし、面白いことをやったりする、いろんなことを面白がる人だと、子どもたちが受け入れてくれるようになります。やがて、「ノブウ(私の現地名)、行くぞ」と、向こうから誘われるようになったのです。本当に弟子あつかいですよね(笑)。
また、私は、寝泊まりしていた自分のテントの外側に屋根を張って、テーブルとベンチを作り、そこに日がな一日座って、時々ふらっと散歩に出て帰ってくるといった暮らしをしていました。屋根の下にあるテーブルとベンチは、「子どもたちの家」と名付けて、子どもたちが自由にいつ入ってきてもいいことにしました。テーブルの上には時々アメを置いておきました。そこに座ってぼんやりしていてもいいよ、といった感じで日々すごしていると、子どもたちも緊張感がなくなり、この人は本当に無害だし、時々なんか面白いことをやって笑える人だと思われ、仲良くなってきます。子どもたちも何となく居着くようになり、なじんできました。
そうなると、子どもたちに「今日は一日、何をしてたの?」「朝は何をしたの?」と聞くと、「狩猟に行ってきたの」「昼はバナナを食べて、夜はだれだれと一緒に踊った」なんて具合に、雑談モードから、朝昼晩の行動や日常活動について話を聞くこともできるようになります。仲良くなった頃合いを見計らって、さりげなく雑談混じりのインタビューを始め、やがてそれが日課になりました。毎日毎日、日が暮れるくらいの時間に、今日は一日何をしてきたのかというデータを朝から順にとることができたのは、こうした居場所や仲良しの関係があったからだと思います。もちろん私も、一生懸命バカの文化のことを学びましたし、子どもたちの言っていることがわかるくらいまで、バカ語も上達しました。
バカ語を覚え、子どもたちが毎日何をしているのかをひととおり観察するまでには、半年ぐらい時間がかかりましたが、その間は、スケッチが非常に役立ちました。『森の小さな〈ハンター〉たち』の中で「フィールドで絵を描こう」という一章を設けましたが、発行後の反応を見ると、この章が一番好評でした。私は元々、生物学を専攻していたので、いろいろな骨格標本や葉っぱ、果実などの絵をていねいに描く生物学スケッチの訓練を受けたことがあります。カメルーンで調査地に入ってからカメラが壊れてしまい、さあどうしようと思ったときに、写真が撮れないなら絵で記録しようかなと、仕方なく始めたのですが、絵を描くと正確に記録できるだけでなくて、描いた絵は、子どもたちにとても受けました。言葉を使わずに子どもたちに受けることができ、非常に重宝しました。そして、子どもたちがバカ語で私に物の名前を教えてくれることもありました。この人が絵を描くのは面白いぞと思われて、みんなが「この果物を描いて」と言ったりし始めました。私の方も楽しくなって、絵をどんどん描いていると、大人まで並び始め、「家でとれた毒蛇だ、絵を描いてくれ」という話にもなります。そうすると、私が意図していないものもいろいろ見せてもらえるきっかけになります。果物などがたくさん採れたときには、「ノブウ、これ食べて」とくれることもあり、絵を描くということだけで関係も広がり、知識も増え、仲良くなり、本当にいいことずくめだったと実感しています。
森の中で何をしているのか
子どもたちは時々、やりを持って森の中に入っていきます。別に獲物が捕れるわけではありません。葉っぱを刺したり、パパイヤを一個採ってきたりしていました。意気揚々と森の中へ出かけていったら、手ぶらで帰ってきたりはしません。動物がとれなくても、おかずになるようなキノコなどを、葉っぱでくるんでぶら下げて持ってきたりします。転んでもただでは起きないというか、手ぶらでは帰らない。何かを見つけて、拾って帰って来るという姿は、やはりたくましいなと思いました。
10歳くらいの女の子たちが、遊びで小屋を作ることもあります。大人たちが作るドーム型の本格的な家屋ではなく、その要素を取り入れた簡素な小屋を作るのです。なたを使ってパパッと葉っぱと枝を切り取って小屋を作り、中に敷物をしいて、女の子4人で転がって遊んだりしています。やはり、大人の女性の仕事を女の子たちが遊びにする、男性の仕事は男の子たちが遊びにする、という傾向がはっきりとあります。まだ幼い4、5歳の頃は性別に関係なく一緒に遊んだりしていますが、10歳ぐらいにもなるとやはり自分の性別を強く意識して、大人のロールモデルからネタを借りてきて遊びにするのです。バカの社会では、大人の女性がドーム型の家屋を作る仕事をすることと、少女たちが小屋作り遊びをすることには、密接な関係があるように見えました。
おやつにバナナを食べようというときは独り占めをせず、居合わせた子どもたちで平等に分配します。ときには見ている私にも小指の先ぐらいのバナナのかけらをくれるということもあります。これは、狩猟採集民の経済のあり方と関わっていると思います。とれた獲物をその人や家族が独占するのではなく、同じ集落の人たちで均等に分け合う、そのことによって、たまに大量に獲物がとれたり、逆にまったくとれなかったりしたときのリスクを平坦化するという経済のあり方です。子どもたちはそうした規範を、おやつの分配において見事に取り入れていました。ときには遊びで捕まえてきたクモを意気揚々とぶら下げて帰ってきて、君は足二本、といった具合に平等に分配していました。私ももちろん分けてもらったので、むしゃむしゃと食べる振りをしました(笑)。
女の子たちは、なたを持って、イモを採りにいきます。うきうきとした遊びの感覚で出かけていくのですが、実際に本物のイモが採れることもあるので、なかば採集活動であるとも言えます。ただ、10歳未満の子どもが掘るイモはさすがに親指くらいの大きさのかけらみたいなものなので、その世帯や集落の生計を支えるほどの成果になることはほとんどありません。ですから大人もあまり期待せずに、イモが採れなかったからといって別に怒るわけでもなく、「採れなかったのか、あはは」で終わります。でも、本人は楽しくてしょうがない。こういった活動は、一応は狩猟や採集のつもりでも、まったくとれないこともよくある、いわば生計に貢献しない生業活動です。男の子たちは狩猟、女の子たちは採集と、対象が動物と植物であるという違いはありますが、毎日、こうした狩猟採集活動に没頭していた姿は、とても印象に残っています。
ミミズを掘って、釣りのえさにすることもあります。ミミズしかとれなくても、ミミズがいたぞということ自体が一種の狩猟採集活動で、充実した楽しいひとときになるのです。女の子たちは、川をせき止めて、水たまりの水をかい出して、そこに閉じこめられた魚やカニを手づかみでとるという伝統的な漁労方法によるかい出し漁をすることもあります(表紙イラスト)。大人の女性がこれをやると、鍋に何杯も、集落の人たち全員を養っても余るぐらいの大量の漁獲高を上げます。それに対して、5、6歳の女の子たちが小川に行って泥かきをしても、結局は何もとれないで帰ってくることがよくあります。これも生計に貢献していない生業活動ですが、それでも許されている。魚やカニがとれるとおやつになるので、本人たちはもちろんうれしいでしょうが、獲れなくても別にそんなに悲しくもないし、困ってもいないのです。そんな遊びとも生業活動とも分類しがたい活動がいろいろと見られました。
私が調査した地域では、近年、狩猟採集民でありながら、一方で農耕をする人たちも増えています。農耕は、狩猟採集とは違い、どこかに行けば獲物がとれるものではなく、草を刈り、耕し、植え付けをして、何ヵ月後にようやく作物が収穫できるという、投資をしてから回収するまでに時間がかかる生業活動になります。ですから、子どもたちの場合も、農耕遊びはほとんど見られません。大人が農作業に行くときに、子どもやおいっ子、めいっ子を連れて手伝いをさせるという、大人の仕事を手伝うという形での農耕への関わりはありますが、狩猟や採集のように子どもたちがキャーキャー言いながら畑を耕しにいくという姿は、見ることができませんでした。
男の子がわなを作って遊ぶとか、あるいは最近は銃を使った狩猟も増えてきたので、中空のピストン状のパパイヤの茎を銃身に、植物の柔らかい部位を弾にして、後ろから棒で押すと弾を打ち出すことができるおもちゃの銃を作ったりもしていました。またボーリングのように転がしたパパイヤを、迎え撃つチームがやりで射るという遊びもありました。面白い遊びだなと思って、日本のいろんなところでこの遊びの写真を見せると、パパイヤを転がして遊ぶなんて、なんて食べものを粗末にする人たちなの、というような反応もあります(笑)。確かに日本では、パパイヤは一個何百円もする高価なぜいたく品かもしれませんが、カメルーンのあの地域では、雑草のようにそこらへんに茂っています。捨てた種から、勝手に生えてくるのです。そうした植物の素材を組み合わせて遊んでいるのです。
子どもたちは、伝統的な精霊の衣装も作りますが、大人がお祭りで使う衣装を作るのとは別に、自分たちの髪飾りを作ったり、あるいは布をくるくるっと巻いてお人形さんごっこをしたりもします。コロを何本か並べて板を乗せて、みんなで乗り込んで坂道を滑り落ちるという遊びもありました。これは伝統的な狩猟や採集とはまったく関係なく、街道沿いをパーッと通り過ぎる自動車を見て、それにヒントを得て発明した遊びのようです。こうして、自分たちで手近な素材を組み合わせて、遊ぶのです。
遊びと文化
これまで述べてきたように、子どもたちの遊びが伝統的な文化の再生産に役立っているという側面は、確かに見受けられます。男の子が狩猟遊びを、女の子が採集遊びや小屋作り遊びをするのはその一例で、伝統文化を練習し再現する教育になっているという見方もできます。しかし、特に教育にも訓練にもなってない、子どもたちが勝手に面白がってやっている遊びも多いので、すべての遊びを教育や訓練の一環であると解釈するのはちょっと無理があると思います。むしろ、子どもたちが勝手に遊びを自在に組み合わせて文化を創っているというように捉えた方が、出発点としては重要かなと思っています。たとえば、子どもたちは中空のパパイヤの茎を使って、その辺の枝と組み合わせて、飛行機も作ります。もちろん、飛行機には乗ったことはないし、こんなものを一生懸命に作ってもパイロットになれるわけでもないのですが、森のはるか上空を時々通り過ぎる飛行機を見て、こういうものを作って、飛ばして遊んだりしていました。
狩猟や採集によく似た伝承遊びの場合は、子どもなりに一人前の風格で狩猟や採集チームを作り、幼い子どもたちを引き連れて森の中に出かけていました。このように、子どもたちは実際に大人の振るまいをよく見て、遊びに取り入れます。一方で、自動車や飛行機作りのように、大人の真似をして伝統的な文化の再生産に役だっているだけでなく、子どもなりに面白いと思ったものを雑多に取り入れて、いろいろな遊びを作ったりもします。
また、大人が「こうしなさい」「こういう遊びをした方がいい」「こういうゲームのルールで」などと言って、遊びを与えることはしません。だいたい10歳すぎくらいの子どもたちが、幼い子どもたちを引き連れて遊びや狩猟や採集を組織して、みんなで出かけていきます。私の方は、年長の子どもに引き連れられている5、6歳の子どもたちから、「ノブウ、来い」などと言われて引き連れられていました。子どもたちの中での長幼関係に基づいて、年齢の比較的高い子と低い子が一緒になって連れ立っていくということが多いのです。そして子どもたちは、手近な道具や素材を使って、勝手に遊び方や使い方を覚えていました。
男の子と女の子の遊びの違いは、やはり顕著に見受けられました。男の子の遊びは大人の男性の活動によく似ていましたし、女の子の遊びも大人の女性の活動によく似ていました。日本の遊びとは違う点もあり、たとえば、動物を解体して料理するままごとは男の子の遊びになります。あるいは、日本では秘密基地を作ったりするのは男の子かなあと思いますが、ここでは女の子が小屋を作って遊びます。大人の男性は狩猟の獲物を獲って持ち帰り、解体して分配して調理をする、大人の女性は家作りをするというバカの社会における性別の分業が、男の子のままごとと女の子の小屋作りにぴたりと適合しているように見えます。男の子らしい遊びと女の子らしい遊びの区分は、どの社会でもだいたい見受けられることだと思いますが、社会によってその割り振り方は違うということが、こうした事例からもわかります。
その一方で、社会や文化は違っていても、たとえば、茂みの中でガサゴソと音がしたときに、「そこだ、そこだ、そら追いかけろ」などと言って、遊びにのめっていく姿は、おそらく日本の子どもたちでもアフリカの子どもたちでも、あるいはヨーロッパの子どもたちでも共通に見受けられることでしょう。文化や社会によらず、共通した遊びの要素が見られる一方で、その要素を組み合わせて特定の遊びの形式を作る中で、その地域の文化や大人の活動をうまく取り入れていると考えられます。つまり、遊びの普遍的な面と、それぞれの文化に依存する面の両方が見て取れるでしょう。
また、動物や植物を見つけて遊ぶということはそもそも楽しいことで、日本のように工業化した社会でも、わざわざ釣りや山菜採りに行ったり、アウトドアスポーツを楽しんだりと、狩猟採集の要素はレジャーとして残されていますね。その点では、狩猟採集活動を楽しむということ自体、人間全体に共通している特徴だと言えるのかもしれません。バカの社会における子どもたちの遊びの数々も、ある日気づいたら大人の狩猟採集活動に近いものになっているようです。子どもたちが立派な狩猟採集民になるための訓練に日々励んでいるわけではなくても、遊びと生業活動が必ずしも明確に二分されていない社会の中で、獲物がとれなくてもなくても面白かったという活動を繰り返していくことを通じて、狩猟採集民になっていくのではないかと、私は考えています。『森の小さな〈ハンター〉たち』の中でも、「子どもは自発的に性別に割り振られた生業活動の集まりに加わり、そのおもしろさを見つけて楽しむようになり、それらの活動を担う成員となる」(p.223)というプロセスとしてまとめてみました。
アフリカ子ども学の三つの方向性
この本は、カメルーンの熱帯雨林の子どもたちの遊びや日常生活の調査・研究という私の博士論文のテーマから派生した本ですが、私には、カメルーンの熱帯雨林の子どもたちに限らず、アフリカの子どもたち全般について学ぶという話に広げていきたいという気持ちがあります(3ページの「『アフリカ子ども学』の構想」を参照してください)。
アフリカの子どもたちについて学ぶことには、三つの方向性があると考えています。一つめは「人類進化へのアプローチ」という方向性です。私がこの本の中で主題として掲げていたのは、人類進化に関わるテーマでした。人間はどうしてこのような生き物になったのかということを考えるとき、近代的教育を受けることは必ずしも普遍的ではないことに気付くでしょう。いくつかの国ですべての子どもたちが教育の対象になったのは、ようやく20世紀に入ってからのことで、しかもすべての国ではありません。近代的教育がまだ普及していない社会が少なくないアフリカにおいて、学校が必ずしも大きな権威を持っていない地域の子どもたちの姿を学ぶことは、人間がもともと持っていた姿を探るための参考になります。こうした社会で子どもたちが何を覚え、学び、育っていくのかを知ることは、生態人類学や心理学が学習や教育に関わる問題を考えるときの参考にもなるでしょう。
二つめは「人間の文化の多様性と学習、成長」という方向性で、文化人類学や民族学に関わることです。アフリカには本当に、さまざまな暮らしぶりをしている人たちがいます。私自身は狩猟採集民の調査を行いましたが、焼畑農耕をしている人たちもいれば、牛やラクダを飼って遊牧しながら暮らしている人たちもいれば、あるいは年がら年中、船を出して海に乗り出していく漁労民、大きな湖で漁労生活を営んでいる人たちもいます。さらには、近代化するアフリカ社会の都市のスラムで育つ子どもたちもいるというように、アフリカにはさまざまな生業に基づく多様性が存在しています。「アフリカ」と一言ではくくれない、多様な育ち方や環境の中で学び育つ子どもたちがいること自体について広く学び、似ているところや違うところを考えていくことは、文化的多様性を反映した子どもの姿を知るためには、とても意義があることです。人間の文化の多様性について学ぶということは、一つめに提起した何百万年におよぶ人類進化という発想とは違い、同時代のアフリカの実像を知るという方向性での研究になるでしょう。
三つめは「アフリカ理解と開発」という方向性、これもやはり同時代に向き合ったテーマです。今のアフリカの子どもたちがどういう暮らしをしていて、将来に向けて保健や教育などの問題をどのように考えていったらよいのかというもので、国際開発研究やアフリカ地域研究などの分野に対しても、さまざまな提言ができます。外部の私たちが同時代の子どもたちと向き合って、子どもたちが何か問題を抱えているとするならば、この子どもたちの文化に即した適切な支援とはどのようなものだろうと考えるときに、子どもの文化を学ぶとことは重要な手がかりになるでしょう。
「人類進化」「人間の文化の多様性」「アフリカ理解と開発」という三つの方向性を提示しました。それぞれ議論の蓄積や方向性は違いますが、並立可能な三つの柱になると思いますし、いずれにしても子どもたちを主役に位置付けた研究が求められているという点が重要なポイントになります。
子どもの力をあなどってはいけないということは、実はいろいろな思想家や哲学者が述べています。たとえば、チョムスキー派に属する研究者は、言語を誰が発明したかという問いに対して、言語は大人たちではなく子どもたちが作ったのだと述べています。文化の継承についても、大人が子どもたちに文化を継承させようと思うから子どもが継承していくのではなく、子どもたちが勝手に面白がって覚えるかどうかによって、文化が継承されるか否かが決まってくる、と主張する人もいます。一方で、社会や文化が変化していくときに誰がそれを変えていくのかという点でも、大人が変わってほしいと言ってもムダであり、結局は子どもたちが勝手に変えていくのだということをプラトンは述べていますし、ベンヤミンなども同様のことを述べています。子どもたちは、大人が思っているほど無力ではないし、弱々しく文化を受けとめるだけの存在でもないことは、いろいろな思想家や哲学者がさまざまな形で指摘しているのです。
それにもかかわらず、教育などの場面では、子どもたちがずいぶん低く見られているという一面があるのではないでしょうか。子どもは、経済的に大人に依存せざるをえないとか、体が小さい、体力が弱い、あるいは知識や経験の量に大人との差がある、などの事情は考慮するとしても、近代的な諸制度の中には、子どもをさらに無力な存在におとしめようとする装置がいくつもあるのではないかと、私は感じています。カメルーンの熱帯雨林地域で狩猟採集民の子どもたちが、意気揚々と生意気にも一丁前に勝手にやりを振り回して出かけていく姿を見ると、日本などの先進国の子どもたちがどうしていつも学校に通わされなければいけないのかと、疑問を覚えることもありました。
近代的な制度は、子どもを、労働をしない、参政権を持たない、教育を受け、保護されるべき存在に位置付けています。アフリカの子どもたちに学びながら、「子どもとは無力で保護されるべき存在だ」という前提をはずし、対話するパートナーとして子どもと出会うという思考実験をすることは、有益で面白いでしょう。「子どもとさしで向かい合う」どころか、「子どもを先生にして弟子入りして」まとめた私の民族誌は、その意味でも何らかのヒントを提供できるのではないかと考えています。
子ども学の視点とアフリカ
「文化人類学者は子どもが嫌いだ」と言われていて、実際にそれをタイトルにした論文もあるくらいです。文化的に未完成な存在で、変化していく存在である子どもは、固定した文化を記述する学問の対象にはなりにくいという先入観があるためか、子どもを直接的な対象とした文化人類学の研究はとても少ないのです。大人の仕草を模倣して受け継ぐ受動的な存在として子どもを位置づけて、育児や教育をする大人について調べるという研究は増えていますが、子ども自身の文化を調査・記述しようという研究は、これまであまりありませんでした。
最近では、大人の男性の健常者だけを描いても、それだけでは社会を写し取ったことにはならないという理由から、女性たちあるいは障害を持つ人たちにもそれぞれなりの文化や歴史があることに注目した研究や民族誌(エスノグラフィー)がちょっとしたブームになっています。こうしたノリにもあやかって、もっと多くの人が「子どもたちの民族誌」に取り組んでほしいと思います。それはもちろん、子どもに対して教育や育児をする大人の民族誌ではなく、子どもたちから直接に学ぶ民族誌です。
その際に参考になるのが、「児童文化」と「子ども文化」の違いです。児童文化は、童話や童謡、絵本、漫画など、大人がよかれと思って子どもに伝えるものです。一方で子ども文化は、子どもたちの間で勝手に伝承されている遊びや、子どもたちが作って、幼い子どもたちも見よう見まねで作るようになったおもちゃなどです。子どもたち自身の中に存在し、伝承され習得されている文化を子ども文化として捉え、児童文化と区別することを主張している人もいます。文化人類学もこれからは、こういう提起に学んでいくべきでしょう。
アフリカは、15歳以下の人口が全体の人口の半分以上を占めるという、子どもだらけの大陸です。少子高齢化でこの先どうなるんだろう、年金の払い手として一人っ子を大切に育てなきゃ、と暗く沈んでいる日本社会から、十何時間か飛行機に乗ってアフリカに行くだけで、もう本当にうじゃうじゃと子どもたちがいるのです。私が小学校を訪ねたりすると、変な外国人を一目見ようと、子どもたちが窓から鈴なりになって顔を出しています。
ガーナでろう学校を訪れたときも、耳の聞こえない子どもたちがわんさか集まってきました。日本にはろう学校が全国で100校くらいありますが、子どもの数が減少し、統廃合が行われています。このままでは、ろう教育という専門性をそなえた教育そのものが失われていくのではないかという見方もあるほどです。その一方で、ガーナなどのアフリカの国ぐにでは、ろう学校にたくさんの子どもが集まってきて、いすも教室も足りない、もっと学校を作らないと、もっと先生を増やさなきゃ、などのことが課題になっています。子どもが多くてにぎやかな反面、まだ何も十分にできていない、子どもに関することにこれからいくつも取り組んでいかなくてはと悩んでいるのがアフリカの現状なのです。アフリカと日本との間にあるこの落差は、アフリカに行き来するたびに実感させられます。
アフリカも経済成長を遂げる中で、いつかは少子高齢化の時代を迎えるかもしれません。しかし、少なくとも私がアフリカ研究を続ける今後何十年かの間に、すぐに高齢化社会になるということはなさそうです(笑)。当面は、人口の半分以上を占める子どもたちが主役の若い社会だと位置付けて、大人が子どもをどう育て教えるかという眼差しだけでなく、あるいは政府が教育や児童福祉をどうするのかという眼差しだけでなく、今この場に多くの子どもたちが暮らしていて、にこやかに平和に暮らしていることもあれば、つらく悲しいこともあったりしながら、子どもたちが自ら生活を切り開いていることを直視する。そしてこれからも、この事実に根ざして、子どもたちにストレートに出会い、子どもたちから学ぶことを基軸にした研究や開発・教育・福祉の支援のあり方を考えていく。このような流れができると面白そうだなと考えています。
「アフリカ子ども学」に、一緒に取り組んでいきましょう! 今日は、暑い中、ご来聴くださりありがとうございました。