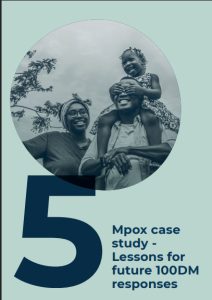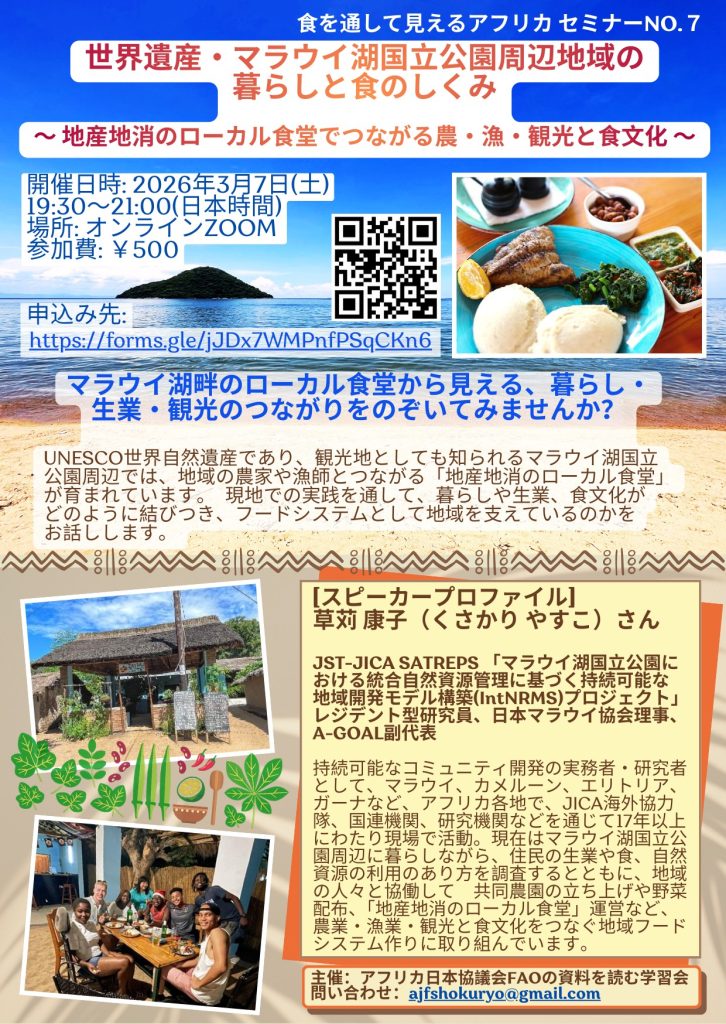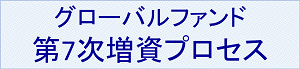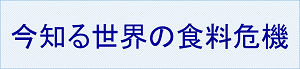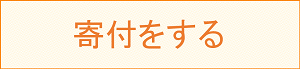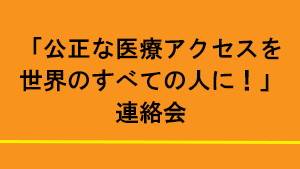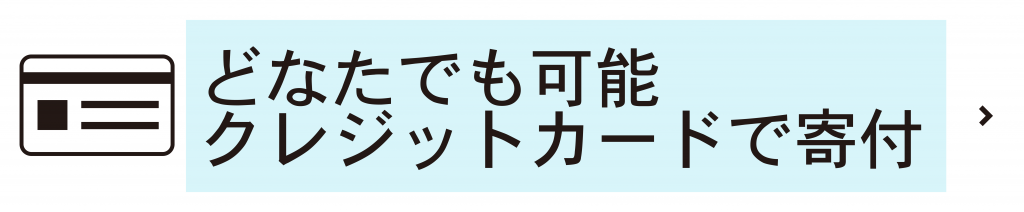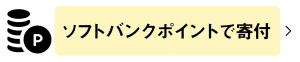2021年12月以降3年以上に渡る討議に付されてきた「パンデミック条約」は5月19日、世界保健総会でWHO加盟国の採決に付され、124か国の賛成により採決された。この決議は、コンセンサスによる採択ではなく、投票によって採決された。これはスロヴァキアが投票による採決を強く要求したからである。結果、反対国は一か国もなかったが11か国が保留に回った。この11か国とはブルガリア、エジプト、イラン、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、オランダ、パラグアイ、ポーランド、ロシア、スロヴァキアであるが、その保留の理由には大きな幅がある。
WHOの東地中海地域を代表して、条約交渉をリードする「ビューロー」の副議長の一つを努めてきたエジプトは、この段階で一部の国がコンセンサスでなく投票による採択を主張したことについて不満を表明した。保留の理由はこれであろう。

一方、投票による採決を強く主張したスロヴァキアは、この条約が国家主権や基本的人権を脅かす恐れがあることなどを理由に挙げた。スロヴァキアは大統領や保健大臣はパンデミック条約を支持する立場をとっているが、ロベルト・フィコ首相は陰謀論・反ワクチン論的な観点からパンデミック条約に反対しており、結果として、陰謀論的な観点を最も強く主張した国となった。国家主権とパンデミック条約の関係や、条約採択後の各国での承認手続きへの懸念を理由に保留の立場に回ったのは、いずれも本来、パンデミック条約の策定に積極的な欧州連合の加盟国であるイタリア、ポーランド、オランダ、スロヴァキアであった。
一方、採択に付されたパンデミック条約の草案では、南北対立の最大の要因となっていた「病原体へのアクセスと利益配分」(PABS)について、制度の趣旨や概略は書きこまれたものの、その詳細については、今後議論する「付属文書」にゆだねられることになった。PABSが実際にパンデミック対応医薬品へのアクセスをどこまで保障するものになるかが不明な段階で、条約への賛成を表明できない、という立場から保留に回ったのは、グローバルサウス諸国、特にイランとパラグアイである。ジャマイカも、中南米21か国を代表してスピーチし、条約草案に高い評価を与えながらも、採決は保留に回った。ロシアは条約の討議の中で一部の国が製薬企業の利益擁護の姿勢をとったこと、新型コロナウイルス感染症パンデミックにおいてグローバルサウス諸国が不利な立場におかれたことなどについて、西側先進国を批判する主張を展開した。
このように、パンデミック条約の採択に当たっては、首相が陰謀論・反ワクチン論の立場に立つスロヴァキアの主張で投票採決となったものの、「パンデミック条約で国家主権・基本的人権が侵される」といった陰謀論的で根拠のない主張は欧州連合に懐疑的な勢力が政権や議会で一定の勢力を構成する一部の欧州諸国等に限定されていた。保留に回った国々の多くは、PABSの制度が、パンデミック対象医薬品へのアクセスを保障するものになるのかどうかに懸念を持つグローバルサウス諸国であった。
これから:パンデミック条約「発効」への長い道のり
PABSに関する「付属文書」は今後さらに討議に付され、これが世界保健総会で採択された後に、各国における批准や承認などのプロセスに付され、60か国が批准・承認などを行った段階で、条約は発効し、第1回の締約国会議(COP)が開催されることとなる。このプロセスは、今回の採択からさらに数年を要するものと考えられる。その点で言えば、今回の世界保健総会でのパンデミック条約採択は、同条約をめぐる物語の第1幕の終了を示すものに過ぎず、今後、第2幕・第3幕でさらなるドラマが展開されるものと考えられる。
懸念すべきは米国・ひいては世界の感染症対策能力の低下
一方、米国トランプ政権はWHO脱退を宣言し、本条約の制定に関する討議には一切参加しなかった。米国はパンデミック対応医薬品の研究開発やパンデミックのサーベイランスなどに関して世界をリードしてきた存在であり、「米国抜きのパンデミック条約」の有効性を疑う声は強い。一方、他のWHO加盟国において、陰謀論や反ワクチン論などに依拠した反対はなく、保留もわずかにとどまったところ、これらに強く影響された立場からパンデミック条約に反対したのは米国だけであったと言える。さらに、トランプ政権は国内政策において、感染症に関するサーベイランスや研究開発の優先順位を大幅に落とし、担当部署を解体・再編するなどして資金を大幅に減額しており、米国自身の感染症サーベイランス能力や研究開発能力も大幅に低下している。これらに鑑みれば、「米国抜きのパンデミック条約」の有効性については大いに懸念すべきではあるものの、より深刻なのは、米国トランプ政権の政策によって、米国自身の感染症対策の能力が低下し、ひいては感染症に対する世界的な予防・準備・対応能力が低下しているというところにあるのではないかと思われる。