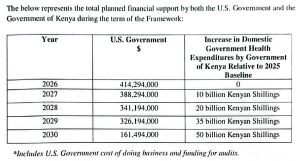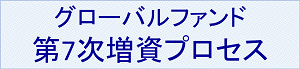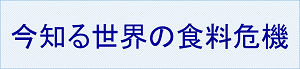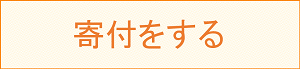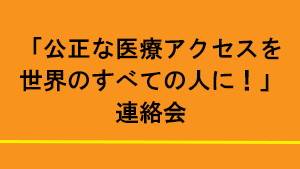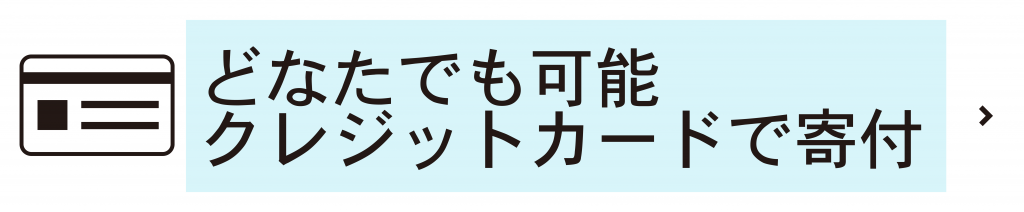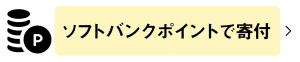ガーナ流家族の作り方~世話する・されることで生まれる居場所~
2025年3月29日、アフリカ日本協議会は新シリーズ「アフリカ玉手箱」の第1回イベントを開催しました。テーマは「ガーナ流家族の作り方」。ゲストに『ガーナ流家族の作り方−世話する・される者たちの生活誌』の著者、小佐野アコシヤ有紀さんを迎え、オンラインと対面のハイブリッド形式で行われました。
この日はオンラインを含め30名ほどの参加者のもとに、小佐野さんのガーナでの体験を通じて日本とは違う家族の形や人と人とのつながりについて考えを深めました。
「家族」って血のつながりだけじゃない?
小佐野さんは、日本では「誰の家族か」「血のつながりはあるか」が重視されがちだが、ガーナではそれよりも「誰が世話しているか」「誰と一緒に生きているか」が大切にされているようだと、提起されました。ガーナでは血縁や婚姻により生まれる関係を超えて、子どもを地域や親戚、知人などみんなで育てる文化が根付いているようです。必要に応じ自然に手を差し伸べる「助け合い」が当たり前のように息づいていて、それが人と人との深いつながりや“居場所”を作り出していると、述べられました。

ガーナの暮らしに学ぶヒント
最近の日本では、子育てや介護が家族に重くのしかかり、孤立してしまうケースも増えています。そんな中で、ガーナのように「みんなで支え合う」考え方は、新しいヒントを与えてくれるかもしれません。
「家族とはなにか?」「つながりってどう作られるの?」といった問いが、参加者それぞれの経験と重なりながら、活発な意見交換が行われたのも印象的でした。ガーナの価値観を知ることは、単なる異文化理解にとどまらず、日本の社会のあり方を見つめ直すきっかけにもなりました。
質疑応答では、日本の地域づくりや地方創生に関心があった小佐野さんが「全く知らない」アフリカを通して新たな視点が得られると感じ、ガーナに関心を持つようになったことや、ガーナで多く見られる「アロマザリング(複数人での子育て)」に共感し、自らの地域活動(例:シングルマザーや高齢者との交流)と重ね合わせる参加者の声が聞かれました。また、家族の在り方を「血縁」ではなく「支え合いの実践」と捉えることの重要性が再確認されたり、多種多様な意見交換で盛り上がりました。
「アフリカ玉手箱」とは?
「アフリカ玉手箱」は、2005年から2015年にかけて開催された「アフリカひろば」の後継イベントです。当時は拓殖大学アフリカ研究愛好会のみなさんとの協働イベントも行っていましたが、その卒業生である田村歩生さんがインターンとしてアフリカ玉手箱に関わってくださっています。「アフリカをもっと知りたい、近づきたい、感じたい」――そんな思いを持つ人たちが集まり、アフリカと日本をつなぐ新しい対話の場をつくっています。
アフリカに関心のある人、関わっている人たちの経験や想いを分かち合い、もっと多くの人にアフリカを身近に感じてもらえるような場にしていきたいと思っています。
アフリカ日本協議会では、今後もさまざまなテーマで「アフリカ玉手箱」を開催していく予定です。「こんなことが知りたい!」「こんな話を聞いてみたい!」というリクエストがあれば、ぜひ事務局までお知らせください。第2回は5月下旬開催予定!テーマは「日本の中のエチオピア」(仮)です
次回も、ぜひお気軽にご参加ください!
<講師プロフィール>
小佐野アコシヤ有紀:1997年山梨県生まれ。2021年東京外国語大学アフリカ地域専攻卒。民間シンクタンクにて子ども・子育て、ケアラー支援分野などの調査研究事業に従事する傍ら、西アフリカ ガーナや日本のガーナ人コミュニティでのフィールドワークを継続し、2023年に『ガーナ流家族のつくり方 -世話する・される者たちの生活誌-』を出版。2025年4月から京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科に在学。